
変形労働時間制とは、一定期間内で所定労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、その期間内で所定労働時間が法定労働時間を超える日があっても、超過分を割増賃金の対象とはしないとする制度です。例えば、繁忙期に所定労働時間を長くし、閑散期には短くすることで、使用者は残業の割増賃金を節約し、従業員は閑散期に余暇をしっかり楽しめるというメリットがあります。変形労働時間制は、宿泊業や農業など季節によって業務量が大きく変わる職場のほか、シフト勤務で1回の労働時間が長くなる医療・介護施設などでも広く活用されており、外国人材を確保する上でも有効です。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
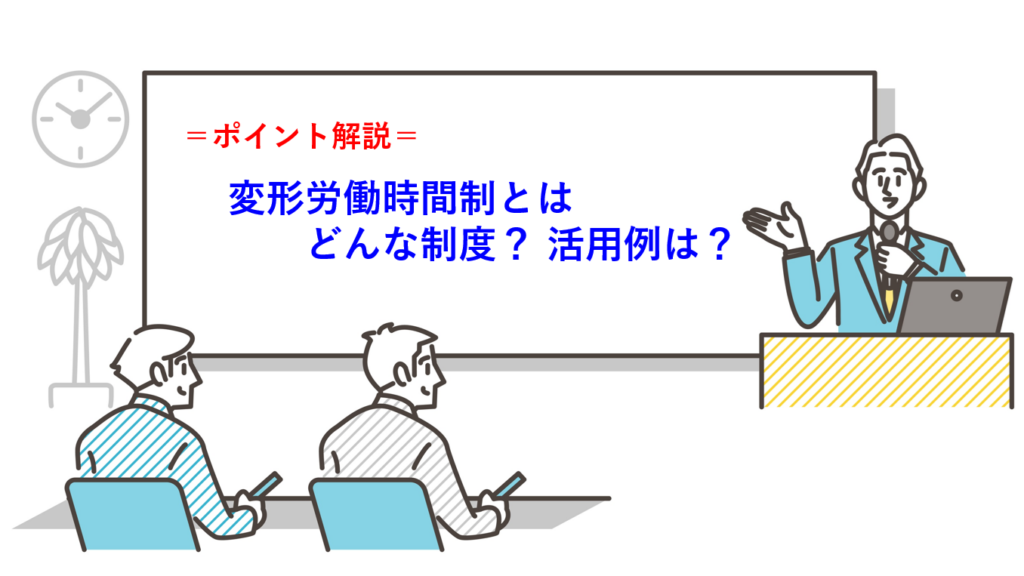
・変形労働時間制:一定期間内で所定労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、その期間内で所定労働時間が法定労働時間を超える日があっても、超過分を割増賃金の対象として扱わないとする制度。
・変形労働時間制の種類:1カ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制、フレックスタイム制
・1カ月単位の変形労働時間制と活用例:1カ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないように所定労働時間を定める制度。シフト勤務で1回の労働時間が長くなる職場(医療、介護、工場、倉庫、タクシー、警備など)や完全週休2日が難しい飲食店などで活用されています。
・1カ月単位の変形労働時間制の注意点:労働日や各労働日の労働時間を事前に設定し、従業員に通知しなければなりません。あらかじめ設定した労働日や労働時間は原則として変更できません。
・1年単位の変形労働時間制:1カ月を超え1年以内の一定期間において、その期間内で平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないように所定労働時間を割り振る制度。
- 1年あたりの労働日数の上限は280日
- 労働時間は1日10時間まで、1週間52時間まで
- 連続勤務は6日まで(繁忙期は最長12日)
- 1週間に1回以上の休み
・1年単位の変形労働時間制が活用されている職場の例:スキー場や観光地のホテル・商店・飲食店、季節商品を製造する工場、セールの時期が忙しい商店、農業など。
◆このページの内容
変形労働時間制とは?

① 通常の所定労働時間と割増賃金
労働基準法は労働時間等について「労働時間は1日8時間以内・週40時間以内(法定労働時間)」「休日は毎週1日以上」と定めています。これを超えて労働させる場合には、労基法36条に基づく労使協定「通称36(サブロク)協定」の締結・届出や割増賃金の支払いが必要です。
〈法定労働時間〉
1日8時間以内
週40時間以内
※商業、理容業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業(旅館・飲食店など)で従業員が常時10人未満の場合は特例で法定労働時間は週44時間以内。
事業者はこの範囲内で「所定労働時間」(休憩は含まない)を設定し、その時間を超える労働(残業)に対しては残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の事業所で1日8時間働いた場合、8時間は法定労働時間の枠内ですが、所定労働時間より1時間多いので、事業者はその1時間に対して通常の賃金の1.25倍以上の残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
② 変形労働時間制
所定労働時間を長めに設定できれば、事業主が負担する割増賃金は減ります。季節や月、または1カ月・1週間の中で業務の忙しい時期とそうでない時期がある事業者の場合、特定の期間で1日の所定労働時間を長く設定し、別の期間で短く設定すれば、全体の割増賃金を節約することができます。これは労働基準法32条で認められており、そのような所定労働時間の設定方法を「変形労働時間制」と呼びます。
つまり、変形労働時間制とは、一定期間内で所定労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、その期間内で所定労働時間が「1日8時間」を超える日があっても割増賃金の対象として扱わないとする制度です。
③ 変形労働時間制の種類
労働基準法に基づく変形労働時間制には「1カ月単位」「1年単位」「1週間単位」「フレックスタイム制」の4種類があります。
これらの制度を職場に導入するには、労使協定の締結や労基署への届け出等が必要です。
変形労働時間制のメリットと注意点

① 変形労働時間制のメリット
・一定期間(年、月、週)内の繁忙期の所定労働時間を長く設定することで、その期間の従業員の時間外労働を減らし、事業主から従業員に支払う残業代(割増賃金)を節約することができます。
・労働者側も、所定労働時間の短い期間には余暇をしっかり活用することができます。
② 変形労働時間制の注意点
・1カ月単位の変形労働時間制では、労働日や各労働日の労働時間を事前に設定し、従業員に通知する必要があります。設定した労働日や労働時間は原則として変更できません。
・変形労働時間制を導入するには、労働組合と協定を結んで労基署に届けるなどの手続きが必要です。
・繁忙期に従業員が加重労働に陥りがちです。変形労働時間制でも、従業員に対する使用者の安全配慮義務は変わりませんので、過労死・過労疾患・労災事故などが起きると、使用者は責任を問われることがあります。
1カ月単位の変形労働時間制

変形労働時間制には「1カ月単位」「1年単位」「1週間単位」「フレックスタイム制」の4種類がありますが、特に使われているのは1年単位と1カ月単位の変形労働時間制です。
① 1カ月単位の変形労働時間制とは?
「1カ月単位の変形労働時間制」では、1カ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内となるように、労働日や各労働日の労働時間を設定します。これによって、所定労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
例えば、月末が忙しい会社なら、月の第1週と第2週の所定労働時間を36時間、第3週を40時間、第4週を48時間と設定すると、この4週間における1週当たりの平均は40時間となり、法定労働時間内に収まります。
このとき、第4週では週40時間を8時間超過していますが、この8時間は所定労働時間に算入していますので、残業代(割増賃金)が発生しません。ただし、働いた時間分の通常賃金は必要です。
② 1カ月単位の変形労働時間制が活用されている職場の例

「1カ月単位の変形労働制」は例えば次のような職場でよく使われています。
- シフト勤務で1回の労働時間が長くなる職場(病院、介護施設、交代勤務の工場、倉庫、タクシー会社、運送会社、警備会社など)
- 1カ月の中で忙しい時期とそうでない時期がある程度固定している職場
- 飲食店など完全週休2日を確保するのが難しい職場
1カ月単位の変形労働時間制の場合、1日の労働時間の上限がありません。このため、夜から翌朝にかけて長時間の夜勤をシフトで組んでいる場合に活用されています。
ただし、残業に対する割増賃金が不要な場合でも、深夜勤務手当(午後10時から午前5時の勤務に対して支払う通常賃金の1.25倍以上の割増賃金)は支払わなければなりません。
また、完全週休2日を確保するのが難しい飲食店などで、休日を減らす代わりに労働日の1日の所定労働時間を短くして週40時間以内に収める手法もあります。これも1カ月単位の変形労働時間制です。
③ 1カ月単位の変形労働制の注意点(誤解しやすい点)
1カ月単位の変形労働時間制では、労働日や各労働日の労働時間を事前に設定し、従業員に通知する必要があります。あらかじめ設定した労働日や労働時間は原則として変更できません。その日その日の忙しさに合わせて自由に所定労働時間を変更し、残業代を削減できる制度ではありません。
④ 1カ月単位の変形労働制の導入手続き
導入するには、労使協定または就業規則に次のような事柄を盛り込まなければなりません。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象となる期間(変形期間=1カ月以内)と起算日
- 変形期間内で平均した場合に1週当たりの労働時間が法定労働時間を超えないという定め
- 変形期間内の労働日ごとの労働時間
- 有効期間(労使協定の場合)
1年単位の変形労働時間制

① 1年単位の変形労働時間制とは
「1年単位の変形労働時間制」とは、1カ月を超え1年以内の一定期間において、その期間内で平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないように所定労働時間を柔軟に割り振る制度です。以下の条件があります。
- 1年間の労働日数の上限は280日
- 労働時間は1日10時間まで、週52時間まで
- 連続勤務は最長6日(特定の期間は最長12日)
- 週1回以上の休み
※1カ月単位の変形労働時間制では、特定業種の小規模事業所で法定時間を週44時間以内とする特例が適用されますが、1年単位の変形労働時間制にはこの特例は適用されません。
② 1年単位の変形労働時間制が活用されている職場の例
「1年単位の変形労働時間制」は、1年以内の期間に繁忙期や閑散期がある場合に適した制度です。
例えば、夏休みと春休みの時期が忙しい旅館で、7月・8月・3月の所定労働時間を週50時間に設定し、その分、閑散期の6月・11月・2月の所定労働時間を週30時間、他の月は40時間に設定することで、1年間全体の平均では1週間の所定労働時間を40時間以内とすることができます。
1年間の変形労働制は、季節によって業務量に大きな差がある職場、例えばスキー場や観光地のホテル・商店・飲食店、季節商品を製造する工場、セール時期が忙しい商店、農業などで活用されています。
③ 1年単位の変形労働時間制の導入手続き
1年単位の変形労働時間制を導入する場合には、その内容について就業規則に定めるとともに、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出なければなりません。労使協定には次の内容を盛り込みます。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象期間(変形期間)と起算日
- 変形期間における労働日と労働日ごとの労働時間
- 特定期間(連続12日まで働ける期間)
- 労使協定の有効期間
農業における変形労働時間制の活用

① 農業の所定労働時間
労働基準法は「1週40時間以内・1日8時間以内の労働時間(法定労働時間)」と「1週間に最低1日の休日」を原則としています。しかし、農業には労働基準法の労働時間関係に関する規定が適用されないため、法定労働時間を超えて所定労働時間を設定することができます(労基法第41条)。
しかし、最近では、農業事業者でも労働力確保等の観点から、所定労働時間を法定労働時間の週40時間を基本に設定するケースも増えています。他産業を大きく下回るような労働条件で良質な労働力を安定的に確保することは困難だからです。
② 農業における変形労働時間制の活用
そのような中、変形労働時間制を活用する農業事業者もあります。例えば、農繁期には所定労働時間を長く(休日は少なく)設定し、農閑期には所定労働時間を短く(休日は多く)設定するというやり方があります。こうして年間を通じた所定労働時間や休日数の平均を他産業並みに設定し、労働者の確保等につなげています。
農業における変形労働時間制の導入方法として、例えば、次のようなやり方があります。
5月~10月の6カ月間が農繁期の場合、この期間の所定労働時間を9時間(休憩時間を除く、週5日勤務)に設定し、11月~4月は所定労働時間を7時間に設定すると、通年平均では1日あたりの所定労働時間は8時間、1週間あたりの所定労働時間は40時間となります。
また、月ごとの総労働時間を個別に設定することもできます。通年平均で1週間あたりの所定労働時間を法定労働時間の枠内の40時間となるように設定すると、年間の総労働時間は40÷7×365=2085.7時間となります。この総労働時間を各月の仕事量に応じて配分し、各月の所定労働時間を決める方法もあります。
いずれの場合でも所定労働時間を超えて働いた場合は、農業といえども残業代を支払わなければなりません。その際、農業では、残業代は割増賃金ではなく通常賃金でもよいのですが、労働力確保の観点から他産業並みに25%割増した残業代を支払うケースも増えています。
また、労働者に午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間の労働については、農業でも通常賃金の25%増以上の割増賃金(深夜勤務手当)を支払わなければなりません。
③ 変形労働時間制で働いた農業技能実習生の体験

ベトナム人女性のタオさんは仲間3人と一緒に北海道東部のJA(農協)に技能実習生として赴任しました。仕事内容は季節ごとに違いました。2~7月はJAの育苗センターや組合員の畑での仕事(苗植えなど)が中心で、7~10月は畑での収穫作業や選果場でのニンジンの選別、11~4月はタマネギの選別などが中心でした。
これに応じて所定労働時間も季節によって変わりました。5、6月は毎日8.5時間、11~2月は7時間、それ以外の月は7.5時間でした。
これは、閑散期にも選果場等での仕事を盛り込んで最低限の労働時間(給料)を確保し、逆に繁忙期には少し労働時間を長くするものの過密労働にはならないようにする、という手法でした。このような農業実習の方式は「北海道方式」とも呼ばれ、技能実習生から好評を得ています。
まとめ

このページのまとめ
◎変形労働時間制とは、一定期間内で所定労働時間の平均が法定労働時間を超えていなければ、その期間内で所定労働時間が法定労働時間を超える日があっても、超過分を割増賃金の対象として扱わないとする制度です。
◎変形労働時間制には「1カ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」があります。
◎「1カ月単位の変形労働時間制」とは、1カ月以内の一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないように所定労働時間を定める制度をいいます。活用例としては、シフト勤務で1回の労働時間が長くなる職場(医療、介護、工場、倉庫、タクシー、警備など)や完全週休2日が難しい飲食店などがあります。
◎「1カ月単位の変形労働時間制」では労働日や各労働日の労働時間を事前に設定し、従業員に通知しなければなりません。あらかじめ設定した労働日や労働時間は原則として変更できません。
◎「1年単位の変形労働時間制」とは、1カ月を超え1年以内の一定期間において、その期間内で平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないように所定労働時間を割り振る制度です。以下の条件があります。
- 1年あたりの労働日数の上限は280日
- 労働時間は1日10時間まで、1週間52時間まで
- 連続勤務は6日まで(繁忙期は最長12日)
- 1週間に1回の休み
◎「1年単位の変形労働時間制」は季節によって業務量に大きな差がある職場(スキー場や観光地のホテル・商店・飲食店、季節商品を製造する工場、セールの時期が忙しい商店、農業など)で主に活用されています。
