
日本の少子高齢化等を背景に、2008年に約49万人だった日本の外国人労働者数は2024年には約240万人になりました。日本は国内の社会・経済機能を維持していくために、今後ますます多くの外国人材の就労を想定しています。しかし、人材送出諸国と日本との賃金格差が急激に縮小したことと円安によって、今や日本で働く際の賃金面での魅力は激減しました。一方で諸外国との人材獲得競争は激化しています。今後、日本が必要な外国人材を確保していくためには、賃金引き上げや生活・教育環境の改善などさまざまな努力が求められます。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
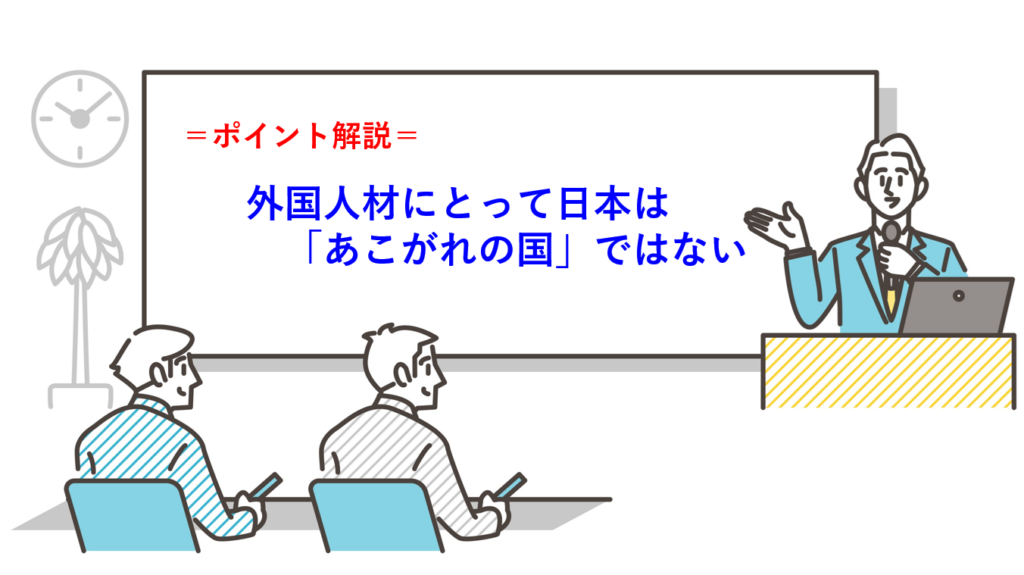
・急速に増える外国人材と今後の人口予測:
- 日本の少子高齢化・人口減少を背景に、2008年に約49万人だった日本の外国人労働者数は2024年には約240万人になりました。
- 特定技能の新たな5年間の受け入れ枠も最初の5年間の2.4倍にあたる82万人に設定されました。
- 2070年には在留外国人が総人口の10.8%(939万人)になると予測されています。
・外国人材が順調に増え続けるとは限らない:今や就労先としての日本の魅力は薄れ、受け入れ見込み数や目標を設定すれば、自動的に必要な数の外国人材が集まるという状況ではなくなってきています。外国人材を確保していくためのさまざまな努力が国・自治体・受け入れ事業者等に求められます。
・日本はもはや「あこがれの国」ではない:人材送出諸国と日本との賃金格差が大幅に縮小したことと円安によって、今や日本で働く際の賃金面での魅力は激減しました。
・人材獲得を巡る国際競争と日本離れの兆し:
- アジア・東南アジア諸国の人材にとっては、中東や欧州、近隣諸国、台湾・韓国など海外就労先はほかにもあり、その中で日本は決して特別な存在ではありません。
- 東アジアでは海外就労先として台湾・韓国の優位性が増し、日本の優位性が低下しています。
・外国人から選ばれる国や企業へ:日本が必要な労働力を確保していくためには、賃金の引き上げや外国人から見た生活・教育環境の改善などが求められます。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 急速に増える外国人材と今後の人口予測
- 外国人材が順調に増え続けるとは限らない
- 日本はもはや「あこがれの国」ではない
- 人材獲得を巡る国際競争と日本離れの心配
- 外国人から選ばれる国や企業へ
- まとめ
急速に増える外国人材と今後の人口予測

急速に増える外国人材
日本の生産年齢人口の減少に伴って外国人労働者の数が増え続けています。日本で働く外国人は2008年に48万6398人だったのが、2016年に100万人を突破。その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を脱すると再び増加に転じ、2023年には204万8675人、2024年には230万2587人になりました(いずれも10月末現在)。
また、2020年の国勢調査で日本に住む外国人は274 万7000人(総人口の2.2%)でしたが、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の人口推計(2023年)では、2070年に939万人(総人口の10.8%)になります。
特定技能外国人の受け入れ枠も拡大
2019年に始まった特定技能制度は、人手不足が深刻な産業で即戦力となる外国人労働者を受け入れる制度です。飲食料品製造業や介護、製造などに加え、2024年には自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の追加が決まり、2025年3月現在、計16分野で受け入れが可能となっています。
特定技能外国人の受け入れが過大になり、日本人の雇用に悪影響を及ぼすことがないよう、分野別の受け入れ見込み数(受け入れ可能枠)を5年単位で設定しています。特定技能外国人の売れ入れ見込み数は2019年度からの5年間では34万5150人に設定されましたが、2024年度から5年間では倍以上の82万人に設定されました。
毎日新聞の報道によると、各省庁が業界の要望を集約したところ、新たな5年間の受け入れ見込み数は計100万人前後にふくらみましたが、日本人の雇用を守る必要もあり、政府が最終的に82万人まで絞ったとのことです。人口減少が急速に進む中、特定技能制度の導入時に根強かった、外国人労働者が増えることへの警戒感や「移民反対」の声は小さくなっていきました。
外国人材が順調に増え続けるとは限らない

本格的な人材不足はこれから
日本は近年、このように外国人労働者への依存を急速に深めています。そして、特定技能外国人を今後大幅に増やそうとし、将来の人口推計にも外国人の増加を見込んでいます。
少子高齢化による日本の人材不足が本格的に深刻化するのはこれからで、日本のさまざまな社会・経済機能を維持するために外国人材の活用が今後ますます不可欠になっていきます。
外国人材が自然に集まる時代は終わった
ただ、そのことへの危機意識がまだ国全体で十分に共有できているとは言えません。例えば、2025年1月の自民党「外国人材等に関する特別委員会」で次のような趣旨の発言がありました。
「特定技能2号に関しては、対象分野を安易に増やさないでほしい。2号になったら、5年経てば永住許可が取れるので、実質移民と同じような扱いだ」
この意見は日本が外国人材から「選ばれる」ことが前提になっているように思われますが、日本の賃金が約30年間すえ置かれた結果、外国人材を引きつける日本の就労先としての魅力は急速に減少し、今や日本は外国人材にとって決して「あこがれの国」ではありません。
外国人材を確保していく努力が必要
そのような状況の中、2号特定技能を拡充・活用して外国人材の来日モチベーションを引き上げることも視野に入れないと、日本が社会・経済機能の維持に必要な外国人材を今後十分に集めていくことは難しいかも知れません。
外国人材が諸手を挙げて日本を目指す時代は終わり、受け入れ見込み数や目標を設定すれば自動的に外国人材が集まるという状況ではなくなってきています。外国人材を確保していくためのさまざまな努力が国・自治体・受け入れ事業者等に求められています。
日本はもはや「あこがれの国」ではない

日本で働く外国人が急増し、将来の社会・経済機能の維持のためにも外国人材の活用が不可欠となっています。ただ、注意しなければならないのは、日本がもはや「外国人のあこがれの国」や「外国人から選ばれる国」ではなくなっているということです。
賃金格差の縮小
日本で働く外国人にはさまざまな動機があり、日本の生活環境や文化なども魅力になっています。しかし、かつて日本に外国人材を引き寄せる最大の魅力だった賃金の魅力は大幅に低下しています。外国人材の受け入れ事業者も含め、日本全体がこのことをもっと自覚する必要があります。
まず、人材送出諸国と日本との賃金格差が年々縮小しています。
例えば、日本の外国人労働者の中で一番多いのはベトナム人で、全体の約4分の1を占めていますが、ベトナムでの最低賃金は、新型コロナの影響があった2021年を除き、2017年以降毎年5.3~7.3%伸びています。一方、日本では2020年までの30年間で名目賃金については1.11倍(米国2.79倍、英国2.66倍)しか上昇せず、物価を考慮した実質賃金も1.03倍(米国1.47倍、英国1.44倍)しか増えていません。
円安
さらに、円安が賃金格差縮小の問題に拍車をかけています。
例えば、2024年にベトナムの両替商で日本円を両替した際に得られるベトナムドンは約5年前より2割以上減りました。両国の賃金格差が縮小したうえ、円安も進んだため、数年前と今とでは日本円で同じ給料をもらってもベトナムに送金できる現地通貨の額が激減しているのです。
その影響もあって、複数の送出機関によると、技能実習生が最も多いベトナムで、日本の求人に対する応募者が激減しています。
日本との賃金格差の縮小はベトナムに限ったことではなく、ほかの人材輩出諸国においても同じです。このため、他の国々でも早晩ベトナムと同じようなことが起こってくる可能性があります。
人材獲得を巡る国際競争と日本離れの兆し

日本離れが始まった国も
国際的な外国人材獲得競争が激化し、外国人材の日本離れが始まっている国もあります。
例えば、日本の外国人労働者の中で最も多いのはベトナム人ですが、出入国在留管理庁の資料によると、ベトナムでは、海外就労先として2018年には日本が1位(48.1%)で台湾が2位(42.3%)だったのが、2022年には台湾が1位(41.5%)で日本は2位(39.3%)になりました。
また、中国人の海外就労先として日本は2018年にはマカオに次いで2位(8%)だったのが、2022年には6位以下(2.9%)に後退しました。
送出国別の状況
◆日本の外国人労働者の国籍別人数(2023年、厚労省資料より)
ベトナム以外では、日本の外国人労働者の中で近年特に増えたのがフィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマーです。これらの国々について、三菱UFJリサーチ&コンサリティングがさまざまな公的データをもとに海外就労の状況をまとめています。
◆各国の海外就労先
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位以下 | ||
| フィリピン (2022年) | サウジアラビア 23% | UAE 14% | 欧州 14% | クウェート 8% | 北米・南米 6% | 日本 3% | |
| ネパール (2021年) | サウジアラビア 30% | カタール 29% | UAE 19% | マレーシア 6% | クウェート 6% | 日本 1% | |
| インドネシア (2023年) | 台湾 30% | マレーシア 26% | 香港 24% | 韓国 5% | 日本 4% | ||
| ミャンマー (2022年) | タイ 57% | マレーシア 20% | シンガポール 10% | 日本 8% | 韓国 4% |
フィリピン
フィリピンは世界有数の移民送出国です。国連の推計によると、フィリピンから海外への移民は 600 万人を超え、そのうち直近 5 年以内に出国して海外で働くOFW(Overseas Filipino Worker)と呼ばれる就労者だけでも約200万人います。
しかし、OFWの就労先上位はサウジアラビア(23%)やアラブ首長国連邦(UAE、14%)などの中東の国々が並び、日本での就労は3%に過ぎません。ちなみに台湾での就労は4%で、台湾にとってはフィリピン人が外国人労働者の20%を占めています。
フィリピンでは、政府が海外就労を促進してきたものの、近年は国内経済の発展もあり、OFW の数が 2018 年をピークに減少傾向にあります。国際協力機構(JICA)の試算では、日本で働くフィリピン人は2030年ごろをピークに減少する見通しとなっています。
ネパール
ネパールの人口は約 3,000 万人ですが、約100万人がインド(ネパール人にとってはビザ不要)で就労しています。2021年にインド以外の国での就労許可(新規+更新)を受けたネパール人は約63万人で、就労先はサウジアラビア、カタール、UAEの3カ国で79%を占め、日本での就労はわずか1%に過ぎません。
※日本に滞在するネパール人には留学生が多く、資格外活動でアルバイトをしていますが、この1%には含まれていません。
インドネシア
インドネシア人の海外就労先で日本の比率はまだ4%ですが、送出人数は 2022 年以降に急増しています。また、日本で働くインドネシア人は外国人労働者全体の6%にとどまるものの、増加率は2018年からの5年間で2.9倍と国籍別で最大です。
しかし、インドネシア人の海外就労先は台湾、マレーシア、香港の3カ国で計80%を占めています。台湾の外国人労働者の35%がインドネシア人です。
ミャンマー
ミャンマーからの海外就労先は、隣国のタイが半数以上で、近隣のマレーシアやシンガポールが続きます。タイの外国人労働者の66%がミャンマー人です。
一方、海外就労先として日本に行く人は8%と少なく、日本のストック統計で見ても全体の4%しかありません。しかし、ここ数年、日本で働くミャンマー人は急増しています。ミャンマーでは、国内の情勢不安から国外就労を希望する人が増えています。
台湾・韓国の優位性が上昇
出入国在留管理庁の資料によると、東アジアでは台湾と韓国が海外就労先の上位になり、日本の相対順位は低下傾向にあります。背景には、韓国・台湾の経済が順調に成長したのに比べ、日本の経済が長期間低迷したことがあります。
その結果、今や東アジアで低・中熟練外国人労働者(日本の技能実習生や1号特定技能外国人など)の平均月給が最も高いのは日本ではなく韓国となっています。
◆日本・韓国・台湾の1人あたり名目GDP の推移
しかも、韓国や台湾の出生率は日本よりなお低く、外国人材への切実なニーズは日本と変わりません。このため、韓国・台湾でも近年、外国人材依存を急速に強めており、日本が外国人材獲得における優位を奪回するには、相当な努力が必要と言えます。
外国人から選ばれる国や企業へ

2024年の日本の外国人労働者は約230万人で、10年前の約2.9倍になりました。特にアジア・東南アジアからの労働者が増えており、今後、加速していく人手不足の中で、これらの国々からの労働者の受け入れに大きな期待が集まります。
しかし、アジア・東南アジア諸国からの海外就労先として日本は選択肢の一つに過ぎず、決して特別な存在ではありません。送出各国からは、中東やタイ・マレーシア・シンガポール・インドといった近隣諸国にもこれまで多数を送り出してきたほか、近年は欧州諸国に行く人も増えています。東アジアでは海外就労先として台湾・韓国の優位性が増し、日本の順位が低下傾向にあります。
このように、送出国から見ると海外就労先はたくさんあるのに、受け入れ側ではそろって少子高齢化が進んで人手不足が深刻化しており、外国人労働者の獲得競争は今後さらに本格化していくことが予想されます。
日本が必要な労働力を確保していくためには、賃金の引き上げや労働環境の改善、外国人から見た生活条件や教育環境の改善などが求められます。
まとめ

このページのまとめ
◎少子高齢化・人口減少を背景に、2008年に約49万人だった日本の外国人労働者は2024年には約240万人になりました。日本は今後も多くの外国人材の就労を想定しています。
◎しかし、就労先としての日本の魅力は薄れ、目標を設定すれば自動的に必要な数の外国人材が集まるという状況ではなくなっています。外国人材を確保していくためのさまざまな努力が行政にも企業にも求められます。
◎人材送出国と日本との賃金格差が大幅に縮小したことと円安によって、今や日本で働く金銭面でのインセンティブは昔に比べて激減しました。
◎アジア・東南アジア諸国の労働者にとって、中東や欧州、近隣諸国、台湾・韓国など海外就労先はほかにもあり、日本は決して特別な存在ではありません。東アジアでは海外就労先として台湾・韓国の優位性が増し、日本の優位性が低下しています。
◎日本が必要な外国人材を確保していくためには、賃金の引き上げや外国人から見た生活・教育環境の改善などが求められます。
