
日本の人口は2056年に1億人を割り、2070年に約8700万人になると予測されています。人口減少が続く中、既に人手不足倒産が急増していますが、人手不足が本格化・深刻化するのはこれからで、「2035年に384万人の労働力不足」や「2040年に約1,100万人の労働力不足」といった研究結果があります。人手不足を緩和するには外国人材の増加が有効です。日本の就労者全体に占める外国人労働者の割合はまだ3.4%で、先進国の間では低水準です。今後、待遇や外国人にとっての生活環境を改善するなどして一層の受け入れ拡大を図ることが望まれます。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
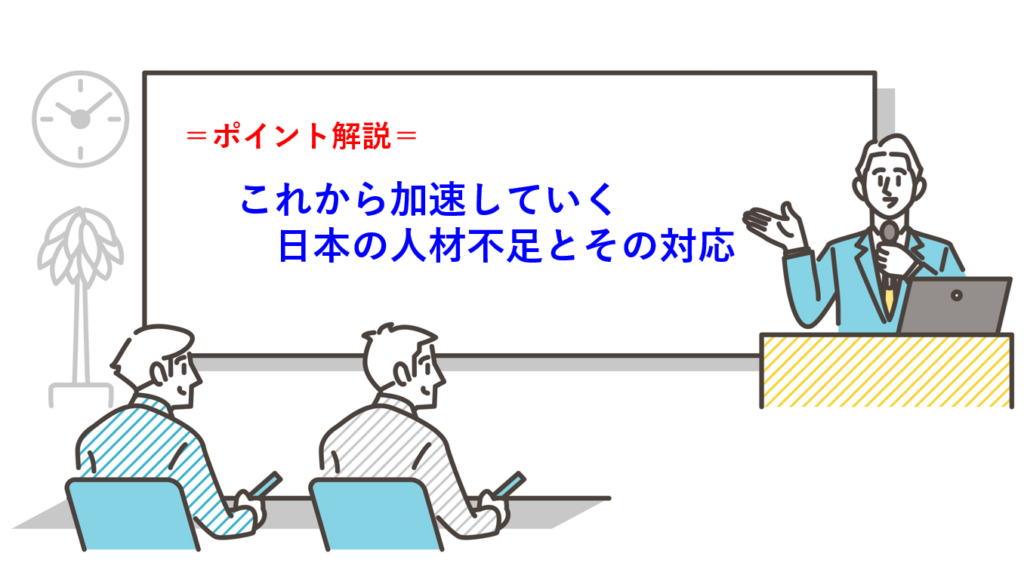
・日本の人口減少:日本の人口は2056年に1億人を割り、2070年には約8700万人、2100年には約6300万人に縮小すると予測されています。
・急増し始めた人手不足倒産:2024年に発生した人手不足倒産は計342件(前年比82件増)で、調査を始めた2013年以降で過去最多を2年連続で更新。
・予測① パーソル総合研究所と中央大学の予測:2035年に384万人の労働力不足が生じます。これは2023年の不足の1.85倍です。
・予測② リクルートワークス研究所の予測:2030年に約341万人、2040年には約1,100万人の労働供給不足が生じます。これは生活維持に必要な労働力を供給できないほどの不足水準です。
・外国人材の増加で衰退を緩和:外国人は2070年に939万人(総人口の10.8%)になると予測されています。外国人労働者の待遇や受け入れ環境の改善を進め、この数字を確保し、さらには上回る外国人を誘致できれば、社会・経済の衰退を緩和できる可能性があります。
・高まる外国人依存と今後に向けて:日本で働く外国人は2018年に約49万人だったのが2024年には約230万になりました。しかし、就労者全体に占める外国人労働者の割合は3.4%で先進国の間では低水準です。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 2056年に1億を割り、2100年に6300万人
- 急増し始めた人手不足倒産
- これから加速していく人手不足
- 外国人材の増加で衰退を緩和する
- 高まる外国人依存と今後に向けて
- まとめ
2056年に1億を割り、2100年に6300万人

国立社会保障・人口問題研究所(社人研)は2023年12月、日本の将来推計人口を公表しました。これは国勢調査結果などをもとに5年ごとに公表している将来の人口推計です。今後の出生や死亡に関して各3通りの仮定を設けていますが、それぞれ中間値の仮定を採用した場合の将来予測は次の通りでした。
◆日本の人口予測
| 年 | 人口 | |
| 2020 | 1億2615万人 | 実績 |
| 2045 | 1億880万人 | 予測 |
| 2056 | 9965万人 | |
| 2070 | 8700万人 | |
| 2100 | 6278万人 |
社人研の予測では、日本の人口は2056年に1億人を割り、2070年には約8700万人、2100年には約6300万人に縮小してしまいます。
しかも、若者の割合が減り続け、65 歳以上人口の割合(高齢化率)は2020 年の 28.6%(3603万人)から2070年には 38.7%(3367万人)に増加すると予想されています。
◆日本の人口予測(年代別)
| 2020年 | 2070年 | |
| 0~14歳 | 1,503万人 | 797万人 |
| 15~64歳 | 7,509万人 | 4,535万人 |
| 65歳以上 | 3,603万人 | 3,367万人 |
急増し始めた人手不足倒産

このような人口減少を背景に、人手不足によって事業継続を断念せざるを得ないケースが既に増え始めています。調査会社「帝国データバンク」によると、2024年に発生した、従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は計342件(前年比82件増)で、調査を始めた2013年以降で過去最多を2年連続で更新しました。業種別では労働集約型産業での人手不足倒産が中心でした。
◆人手不足倒産数の推移
◆ 業種別の人手不足倒産数
人手不足を感じている企業の割合は2024年12月時点で52・6%となり、新型コロナウイルスの感染拡大によって人手不足が一時的に緩和された2020年以降に急速に上昇し、高止まりが続いています。
これから加速していく人手不足
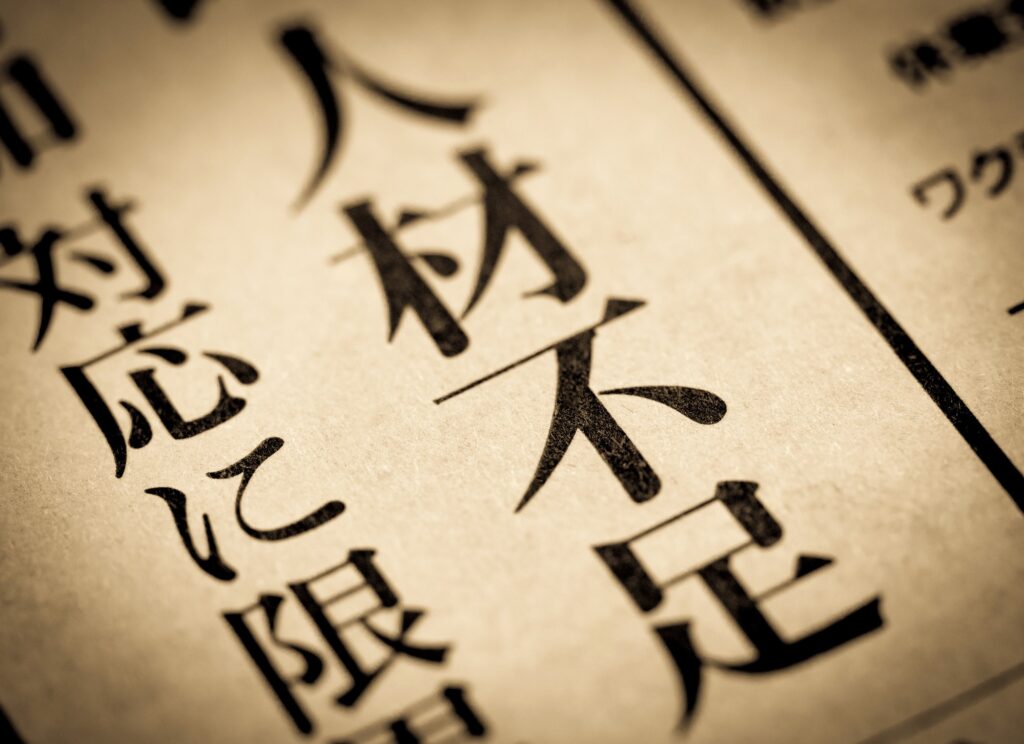
予測①:2035年の労働力不足384万人
日本の人手不足が本格化するのはこれからと予想されています。パーソル総合研究所と中央大学は2024年、2035年時点の日本の労働力不足が2023年の1.85倍の384万人に達するという推計を発表しました。
これは、将来推計人口や完全失業率、実質国内総生産(GDP)などのデータを基にした試算で、労働力には外国人を含みます。産業別ではサービス業の労働力不足が最も深刻で、115万人の不足。卸売・小売業(77万人)や医療・福祉(49万人)でも深刻な不足です。
高齢者や女性、外国人の労働者が増え、2035年の就労者は23年より6%多い7,122万人(うち外国人は84%増の377万人)と見込んでいます。しかし、働き方改革が進むほか、高齢者や女性には短時間だけ働く人も多いため、35年の就労者1人あたりの年間労働時間は23年と比べて9%減ると予想されています。
◆2035年の労働力不足予測
| 2023年 | 2035年 | |
| 労働力不足 | 189万人 | 384万人 |
| 就労者 | 6,747万人 | 7,122万人 |
| 1人当たり年間労働時間 | 1,850時間 | 1,687時間 |
| 外国人就労者 | 205万人 | 377万人 |
予測②:2030年341万人、40年1100万人の不足
リクルートワークス研究所は2023年に公表したレポート「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」でさらに深刻な労働力不足を予測しています。
65歳以上の高齢者人口が2044年まで増え続けるのに、15~64歳の現役世代は2040年まで急激に減少していくため、2030年に約341万人、2040年には約1,100万人の労働供給不足が生じると予測しています。
これは一時的な人不足ではなく、社会に必要なサービスの提供の継続を困難にする慢性的な労働供給不足です。レポートでは例えば次のような状況を予想しています。
◆2035年の労働力不足予測
| 輸送 |
| 必要なドライバーの76%しか確保できず、地方では、配送がまったくできない地域や配送が著しく遅れる地域が生まれる。 |
| 建設 |
| 必要な人材の78%しか確保できず、道路のメンテンナスや災害後の復旧にも手が行き届かず、放置状態が長期間続くこともある。 |
| 生産工程(工場等) |
| 必要な人材の87%しか確保できず、大規模工場を増やしても働く人が十分にいない。また、国内生産に頼っていた製品については品不足が顕在化。 |
| 商品販売 |
| 必要な人材の75%しか確保できず、地方の小売店は無人店が多くなる。 |
| 介護サービス |
| 必要な人材の75%しか確保できず、週4日提供していたデイサービスを週3日しか提供できなくなるなどの影響が出る。 |
| 接客給仕・飲食物調理 |
| 必要人材の85%しか確保できない。 |
| 医師・看護師・薬剤師など |
| 必要な人材の82%しか確保できず、救急車を受け入れられる病院が減るなど生活に大きな影響がある。 |
| 事務、技術者、専門職 |
| 必要な人材の93%を確保できる。 |
このような傾向は特に地方において顕著になっていくと予想されています。
外国人材の増加で衰退を緩和する

人口減少は予測よりさらに加速の可能性
この記事の冒頭で国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が2023年末に発表した人口予測として2070年に8700万人、2100年に6300万人という数字を紹介しました。そして、その半年後に厚生労働省が発表した2023年の出生数は前年比4万3482人減の72万7277人で、過去最少を更新しました。死亡数と差し引きした人口の自然増減も84万8659人の減少で、過去最大でした。
出生数は社人研の2023年推計よりも約10年早いペースでの減少となっており、このままでは「2070年に8700万人」とする予測よりもさらに速いペースで人口が減ってしまいます。
外国人の一層の誘致で衰退緩和を
社人研予測より速く人口減少が進むと、リクルートワークス研究所などが示した人手不足予想よりもさらに深刻な人手不足が待ち受けることになります。そこで、多角的で真剣な対策が必要です。
その対策の一つとして欠かせないのが外国人材の一層の確保です。
2020年の国勢調査で外国人は274 万7000人(総人口の2.2%)でしたが、社人研の人口推計(2023年)では2070年に939万人(総人口の10.8%)になります。まずはこの数字を確保できるように外国人労働者の待遇や受け入れ環境の改善を進め、さらにはこの予想を上回る外国人を誘致できれば、人口減少による社会・経済の衰退を緩和できる可能性があります。
もちろん、日本人の出生率を増やすための施策も必要です。人口そのものへの対策以外では、徹底的な機械化・自動化やシニアの社会参加の拡大なども欠かせません。その上で、人口減少への抜本対策として外国人の一層の誘致を進める必要があります。
高まる外国人依存と今後に向けて
急増する外国人労働者
日本で働く外国人は2018年に48万6398人だったのが、2016年に100万人を突破。その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を脱すると再び増加に転じ、2023年には204万8675人、2024年には230万2587人となりました(いずれも10月末現在)。
◆外国人労働者数の推移
出入国在留管理庁の統計によると、2023年の外国人労働者約205万人の内訳は次の通りです。
◆外国人労働者約205万人の内訳(2023年)
| 身分に基づき在留する者:約61.6万人 |
| 「定住者(主に日系人)」や「永住者」、「日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ外国人。仕事内容に制限がない。 |
| 就労目的で在留が認められる者:約59.6万人 |
| 「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格の外国人。在留許可時に仕事内容が規定される。 |
| 特定活動:約7.2万人 |
| 経済連携協定(EPA)に基づく看護師や介護福祉士の候補者やワーキングホリデーなど、その他全般の在留資格。在留許可の個々の内容によって報酬を受ける仕事ができる人とできない人に分かれる。ここでは仕事をすることができる人だけが計上されている。 |
| 技能実習:約41.3万人 |
| 技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的で、日本の在留外国人急増の原動力となってきた。2027年に労働力確保を目的とする育成就労制度に引き継がれる。 |
| 資格外活動:約35.3万人 |
| 主に留学生のアルバイト。在留資格の主目的の活動(留学生の場合は学業)を妨げない範囲で報酬を受ける活動が認められている。 |
外国人を雇う事業所数は2024年で前年同期比7.3%増の34万2087カ所でした。そのうち6割以上が従業員30人未満の事業所です。
日本の外国人労働者の割合は先進国では低水準
このように近年、日本の外国人労働者数が急速に伸びてきましたが、就労者全体に占める外国人労働者の割合は3.4%(2024年10月現在)にとどまっています。
この割合は米国(約17%)やシンガポール(約4割)、ドイツなどと比べて小さく、経済成長のためには外国人材をもっと取り込んで人口減少をできるだけ食い止めることが重要です。
まとめ

このページのまとめ
◎日本の人口は2070年に約8700万人、2100年に約6300万人に縮小してしまうと予測されています。
◎2024年に発生した人手不足倒産は342件(前年比82件増)で、調査を始めた2013年以降で過去最多を2年連続で更新しました。
◎パーソル総合研究所と中央大学は2035年に384万人の労働力不足が生じると予測しています。これは2023年の不足の1.85倍です。
◎リクルートワークス研究所は2030年に約341万人、2040年には約1,100万人の労働供給不足が生じると予測しています。これは生活維持に必要な労働力を供給できないほどの不足水準です。
◎外国人は2070年に939万人(総人口の10.8%)になると予測されています。外国人労働者の待遇や受け入れ環境の改善を進めてこの数字を確保し、さらにはこれを上回る外国人を誘致できれば、社会機能の衰退を緩和できる可能性があります。
◎日本で働く外国人は2018年に約49万人だったのが2024年には約230万になりましたが、就労者全体に占める割合は3.4%で、先進国の間では低水準です。
