
外国人材を配置する際に、事前に受け入れ職場の理解・納得を得ず、指導やサポートをいきなり丸投げした場合、現場の指導担当者たちは「相談なしに自分たちの仕事を増やされた」と感じます。外国人材への指導には言葉や仕事文化の違いもあり、指導担当者にも相当な労力やストレスがかかります。その場合、職場の雰囲気や外国人材の居心地も悪くなります。事前に現場の理解・納得を得るにはどうしたらよいでしょうか?
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
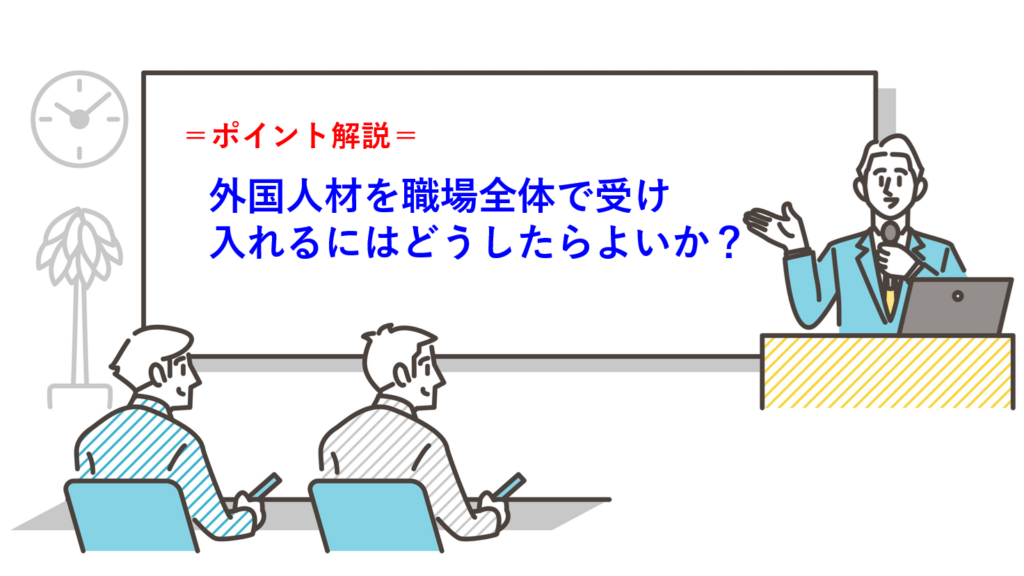
・受け入れ現場への事前説明や研修:外国人材の指導やサポートには相当な労力が伴います。受け入れ現場に外国人材導入の理由や効果を事前に十分に説明しましょう。また、指導担当者たちには外国人雇用に関する研修を実施するのも効果的です。
- 日本人の人材がいかに集まりにくく、コストがかかるか。
- 仮に日本人を雇用できたとしても、いかに定着が難しいか。
- 外国の若い人材が入ることでどのような利点があるか。
・外国人材への研修も望ましい:職場に配置する前に外国人材側にも研修を行うことが効果的です。仕事の内容とやり方、役割分担、職場のルール、就業規則などについて、しっかり教えます。
・来日前の日本語教育がいかに大切か:外国人材の日本語力が低すぎると、指導担当者には大きな困難・ストレスが伴います。外国人材の日本語力は外国の人材会社によって大きく異なります。特定技能の場合でも、必要な日本語試験に合格したからといって会話もできるとは限りません。
・海外の人材会社(送出機関など):比較的日本語力の高い外国人材を獲得するには、例えば次のような方法があります。
- 日本語教育力の高い海外人材会社を探す。
- そのような海外人材会社を選ぶノウハウを持っている監理団体や登録支援機関を選ぶ。
- 現在の海外人材会社に費用を支払って来日前の日本語教育期間を延長する。
・外国人材を巡るトラブルの大半はコミュニケーションの困難から生じます。日本語力の高い外国人材は貴重です。また、ある程度の日本語力を身に付けて来日する外国人材には、課題に取り組む力や努力する力も期待できます。
・社内イベント:職場全体で外国人材と共生する機運を高めるために、食事会や社員旅行などの社内イベントも有効です。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 現場の理解・納得を得てから配属する
- 受け入れ現場への事前説明や研修
- 外国人材への研修も望ましい
- 来日前の日本語教育がいかに大切か
- 現場の反感による受け入れ失敗例
- 社内イベントで交流促進
- まとめ
現場の理解・納得を得てから配属する

職場の親切で仕事も勉強も成功
「日本で働いて良かった」という感想を持つ外国人たちに話を聞くと、職場の雰囲気が良いとか、一緒に働く日本人が親切にしてくれるなどのケースが非常に多いです。
例えば、食品工場で働いた技能実習生たち(女性)は一緒に働く日本人の年配の女性たちから子や孫のようにやさしくしてもらいました。仕事を親切に教えてくれるのはもちろん、家でとれた野菜やお菓子を持ってきてくれたり、休みの日に一緒に食事に行ってくれたり。
こうした交流の中で彼女たちは居心地が良いと感じ、交流をさらに深めるために日本語の勉強も頑張って会話も上達しました。
筆者はスーパーのバックヤードで働いた留学生からも、縫製工場で働いた技能実習生たちからも、そのほかさまざまな外国人からも同じような話を聞きました。
事前の理解・納得がない場合……
逆に、職場に受容されない状況で外国人材を働かせるのは非常に酷です。異国に働きに来て、ただでさえ孤独や不安を感じやすいのに、職場の人たちから歓迎されていないとなると、そのストレスは並大抵ではありません。
経営者としては、「人手不足解消のために外国人材を導入した。感謝されて当然」と思って外国人材を配置したのかも知れません。しかし、事前に職場の理解・納得を得ず、外国人材の指導や世話をいきなり丸投げした場合、指導担当者らは「事前相談なしに自分たちの仕事を増やされた」と感じます。
また、外国人材への指導には言葉の問題や仕事文化の違い、感覚の違いが伴い、指導する側にも相当な労力やストレスがかかります。
受け入れ現場への事前説明や研修

受け入れ現場への事前説明と納得
外国人材に仕事や生活の指導・サポートをするにはそれなりの労力や気配りが必要です。また、外国人材が加わることで職場での調整が大変な場合もあります。このため、事業者は事前に管理職やリーダーを中心に受け入れ現場に外国人材導入の理由や効果を十分に説明しましょう。
外国人材を配置しようとする職場に例えば次のようなことを説明し、納得を得ます。
- (その職場に)日本人の人材がいかに集まりにくく、コストがかかるか。
- 日本全体の人材難の現況と将来の見通し。
- 仮に日本人を雇用できたとしても、いかに定着が難しいか。
- 外国の若い人材が入ることでどのような利点があるか(安定した労働力、若者の作業効率、職場の活力アップなど)。
管理職やリーダーへの研修
管理職やリーダーなど外国人材の指導を担当するスタッフに対しては、外国人雇用に関する研修を実施するのも効果的です。
指導担当者らに外国人材を受け入れる理由や外国人材の特性、文化の違いなどについて研修を行うことで、配置当初の指導にまつわる労力・ストレスを大きく軽減できますし、外国人材への指導力や知識を高めることができます。
外国人材への研修も望ましい

外国人材の受け入れを円滑にするには、受け入れる日本人の指導担当者への研修に加え、職場に配置する前に外国人材側にも研修を実施することが効果的です。日本人の新入社員が入ると新人研修を行う企業も多いですが、同じ考え方で外国人にも研修を実施します。
仕事の内容とやり方、各自の役割、職場のさまざまなルール、就業規則などについて、現場の指導担当者らに丸投げするのではなく、研修で最初にしっかり教えると、外国人本人も働きやすいですし、指導担当者たちの労力やストレスも大きく軽減できます。
西日本のあるスーパーマーケットではバックヤードの仕事などに技能実習生をたくさん雇用していますが、実習生が入国した後、法定の1カ月間の入国後講習に加え、配属前にさらに4週間、実務に関する自社研修を通訳を付けて行っています。
その際、外国人材には、日本人と比べて残業代の計上の仕方(対象となる時間、各種割増賃金)や有給休暇の取得方法など労働条件について細かく知りたい人も多いので、そのような疑問に答える機会も設けてはいかがでしょうか。
来日前の日本語教育がいかに大切か

外国人材の日本語力に大きな違い
受け入れ現場と外国人材の双方に研修を行うことで、外国人材の配置当初の指導・サポートにまつわる担当者の労力・ストレスを大きく軽減できます。しかし、外国人材の日本語力が低すぎると、やはり指導にあたっての大きな困難・ストレスが伴います。
技能実習生や育成就労外国人は外国の送出機関で多くの場合4~6カ月間の日本語教育を受けてから来日し、法律で決められた1カ月間の入国後講習の中でさらに日本語を勉強します。送出機関によっては、来日前にもっと長く教える場合もあります。
特定技能外国人でも技能実習未経験者は実習生と同じ教室で日本語教育を受け、所定の日本語試験に合格してから来日します。彼らには入国後講習はありません。
このような日本語教育を経て現場に配置される外国人材ですが、外国の人材会社(送出機関など)によって日本語教育の期間や質は異なります。このため、日本に配置される外国人材の日本語力も外国の人材会社によって大きく異なります。
特定技能外国人の場合、技能実習を経験した外国人の中には日本語がある程度できる人も多いですが、未経験者の場合、所定の日本語試験に合格しても会話がほとんどできない人がたくさんいます。
日本語教育力の高い人材会社を選ぶ
比較的日本語力の高い外国人材を獲得するには、例えば次のような方法があります。
- 日本語教育力の高い海外人材会社(送出機関など)を探す。
- 日本語教育力の高い海外人材会社を選ぶノウハウを持っている監理団体や登録支援機関を選ぶ。
- 現在取り引きしている海外人材会社に追加費用を払って来日前の日本語教育期間を延長する(それでも効果が薄い場合は、人材会社を変える)。
特定技能外国人や技能実習生など現場労働に携わる外国人材を巡るトラブルの大半はコミュニケーションの困難から生じます。ある程度日本語力のある人材を獲得できれば、この問題をクリアできます。また、一定の日本語力を身に付けて来日する外国人材には、語学力以外に、課題に取り組む力や努力する力も期待できます。
海外の良い人材会社を見つけ、そのような人材を送り出してもらうことで、外国人材を受け入れる職場の労力も大きく軽減できます。
「日本に来たら日本語力も上がるだろう」は間違い
外国人材の中にはあわよくば訪日前の教育期間を短縮して少しでも早く仕事を始めたという人も多いです。教育期間は無収入なので、給料をもらう生活に早く移りたいからです。
また、受け入れる日本企業の経営者にも、1カ月でも早い来日を要求する人もいます。その場合、「日本語力は日本に来てから何とかなるだろう」と考えるか、外国人材の日本での仕事・生活の充実や将来のキャリア・可能性を広げることに関心が薄いかということになります。
筆者の取材経験によると、日本での仕事や生活に必要な最低限の日本語力を身に付けていない外国人材を配置した場合、その人材が日本滞在・勤務を通じて日本語力を伸ばすケースは大変まれです。
働き始めると夜は疲れて勉強に身が入りませんし、来日前に学習努力を十分にしなかった人材が日本に来たからといって急に努力を始めるケースは残念ながら少ないようです。逆に、来日前にある程度の日本語力を身に付けてきた人は、その日本語力や努力体験を基盤に、仕事や生活の中で語彙を増やし会話力も向上させ、夜や休日にも学習を続ける傾向があります。
現場の反感による受け入れ失敗例

外国人材受け入れに対する現場のリーダーによる反感がもとで受け入れがうまくいかなかったケースについて参考に紹介します。
西日本のある工場では、技能実習生を最初に3人(1期生)、2期生は2人雇用しましたが、2期生のうち1人が3年の実習期間をまっとうできず途中帰国しました。
午後の始業前に午前の仕事の結果と午後の仕事の予定を報告するのですが、報告時に求められる日本語レベルが高すぎるということでした。しかし、監理団体によると、この実習生の日本語力は来日1年目の実習生にしては平均以上でした。
監理団体がさらに調べると、リーダーは実習生受け入れ当初から「事前の調整なく実習生の指導を押しつけられた」と感じ、社長のやり方に不満を感じていたことが分かりました。そして、労働組合に「実習生への指導で大きなストレスを感じている」と漏らし、必要最小限なこと以外は実習生との接触も避けていたそうです。
社長は実習生受け入れに積極的で、彼女たちを食事に連れて行ったりもしましたが、現場の指導担当者に事前説明や調整ができていなかったのです。また、監理団体の調査でリーダーのパワハラ体質も浮かんできました。
その後、監理団体が会社と調整したうえで3期生1人、4期生2人を入れましたが、4期生のうち1人も約1年でこの会社を辞めました。彼女の場合は、特に日本語力が高かったので特定技能の必要試験に合格して他社に移りました。このときも、実習生は「上司(別の指導担当者)から怒鳴られる」と監理団体に相談し、心療内科に通っていました。
社内イベントで交流促進

外国人材が職場に定着する要素として、職場で孤立感を感じずに一緒に楽しく働ける仲間がいるかどうかが大事になります。
この記事では、外国人材の受け入れを円滑にするために、受け入れ現場と外国人材の双方への研修や、日本語力の高い外国人材を得る努力をすることを紹介しました。それらは主として職場の指導担当者と外国人材とのあつれきや相互ストレスを解消・軽減するための方策です。
それ以外に、職場全体で外国人材と共生する機運を高めるために、食事会や社員旅行などの社内イベントを設けて外国人材が日本人従業員と広く交流する機会を設けることも望ましいです。
これは特定技能外国人や技能実習生に限ったことではなく、事務職の外国人材にも言えることで、パーソル総合研究所の調査では、正社員の外国人のうち約33%が「(自分は)孤立しているように思う」と回答しました。孤独感が強いと仕事のパフォーマンスや会社への満足度は下がり、早期離職につながります。
この調査で、孤独感をやわらげる効果が確認できた対策として各社が回答したものには、「歓迎会の開催」や「外国人材向けの相談窓口の設置」、「同僚とのコミュニケーション機会の付与」、「定期的な面談」、「母国語対応の指導者の配置」がありました。
社内イベントを喜ぶ外国人材も多いので、下記の記事も参考にしてください。
まとめ

このページのまとめ
◎事前に受け入れ現場(特に指導担当者)の理解・納得を得ず、外国人材の指導やサポートを丸投げした場合、指導担当者らは「相談なしに自分たちの仕事を増やされた」と感じます。外国人材への指導には言葉や仕事文化の違い、感覚の違いが伴い、指導する側にも相当な労力やストレスがかかります。
◎外国人材を配置する職場に、▽日本人の人材がいかに集まりにくく、コストがかかるか▽日本人を雇用できたとしても、いかに定着が難しいか▽外国の若い人材が入ることでどのような利点があるか(安定した労働力、若者の作業効率、職場の活力アップなど)――などを説明し納得を得ます。
◎外国人材の指導やサポートを担当する日本人への事前研修も重要です。
◎外国人材側への研修も大切です。仕事の内容とやり方、各自の役割、職場のさまざまなルール、就業規則などについて、しっかり教えると、本人たちも働きやすく、指導担当者たちの労力やストレスも大きく軽減できます。
◎外国人材の日本語力が低すぎると、指導担当者には大きな困難・ストレスが伴います。外国人材の日本語力は外国の人材会社(送出機関など)によって大きく変わります。特定技能外国人の場合も、所定の日本語試験に合格しただけではほとんど会話できない場合が多いです。
◎「日本に来たら日本語力も上がるだろう」は間違いです。
◎共生の機運を職場全体で高めるため、食事会や社員旅行などの社内イベントも有効です。
