
外国人材が地域社会に受け入れられて気持ちよく生活することができれば、仕事にも安定した気持ちで取り組めますし、地域に愛着がわき、長期定着にもつながります。また、特定技能外国人の場合は、受け入れ事業者か登録支援機関に外国人材と日本人との交流をサポートする義務が課せられています。外国人材が地域社会と交流・共生するために受け入れ事業者側は何をしたらよいでしょうか?
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
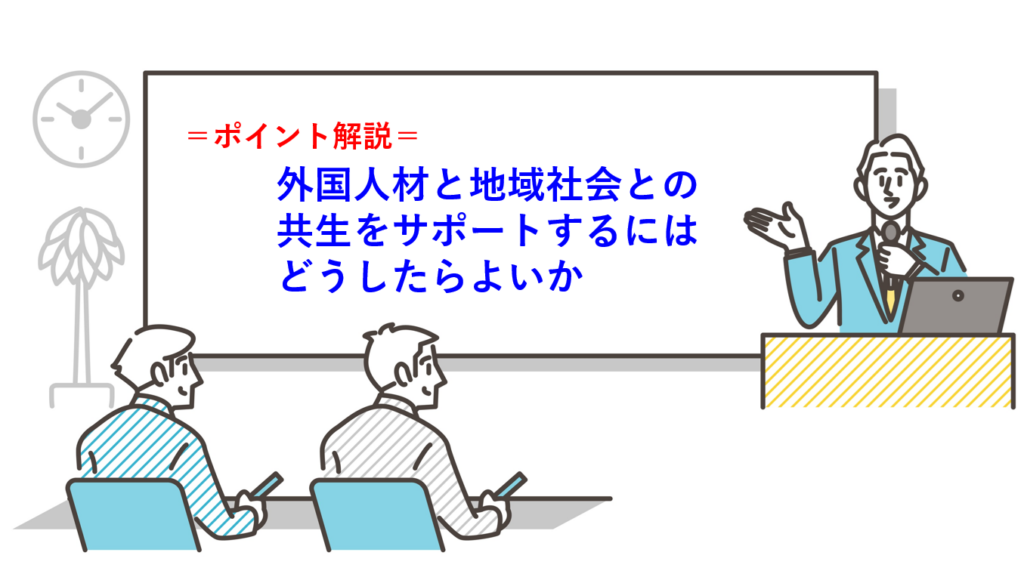
・地域の生活ルールを守る:外国人が地域住民と良い関係を築くには、まず地域社会のルールを守ることが大切です。外国人と地域社会との間で特に多いトラブルはゴミ出しや騒音です。外国人側も粗大ゴミの出し方などを調べるのが難しく、困っているので、サポートが必要です。
・家主と良好な関係を保つ:住宅の使用や退去に関するトラブルが多いので、受け入れ事業者や登録支援機関による指導・サポートが必要です。次のような点に特に注意してください。
- 十分な期間をあけて家主に退去通告をする。
- 退去の際は部屋に何も残さない。
- 部屋の使い方が不適切な場合、多額の退去跡補修費が必要になる場合がある。
- 退去前にライフラインをきちんと解約する。
- 受け入れ事業者か登録支援機関が退去跡チェックにも立ち会う。
・あいさつ:あいさつは地域社会にとけ込む第一歩です。外国人材が日本でのあいさつに慣れるため、あいさつの場面ややり方についても指導してください。
・地域行事への参加をサポート:外国人材の地域交流支援は特定技能の受け入れ事業者や登録支援機関の義務です。交流支援の実例には次のようなものがあります。
- 受け入れ会社のサポートで地域行事に参加
- ボランティア団体のサポートで地域のお年寄りと交流
- 日本人社員と一緒に文化イベントに参加
- 監理団体と受け入れ事業者のサポートで祭りに屋台を出店
・社内交流が地域交流の足がかりに:外国人材が社内交流を深めることで日本人とのコミュニケーションに慣れ、地域とも交流できるようになります。
◆このページの内容
地域の生活ルールを守る

外国人材が地域住民と良い関係を築くには、まず地域社会でのルールを守ることが大切です。日本在住外国人からの電話相談を受けている事業者によると、外国人と地域社会や家主との間で特に多いトラブルはゴミ出しや騒音についてです。
特定技能外国人の場合、受け入れ事業者の義務的な支援の中に「生活オリエンテーション」が盛り込まれています。受け入れ事業者や登録支援機関はオリエンテーションの際に近隣とのトラブル防止についても母国語で指導してください。
また、オリエンテーションを行ったとしても、特定技能外国人が住居をめぐるトラブルを起こすと、受け入れ事業者側がサポートしなければならない状況になることもあります。そのような対応を登録支援機関に依頼したい場合は、適切な対応力のある支援機関を選んでください。
技能実習生や育成就労外国人の場合、通常、監理団体や監理支援機関が生活指導や苦情対応をサポートします。指導力や対応力は機関によって差がありますので、良い監理団体を選んでください。
また、技人国の人材の場合も生活サポートの担当者を社内に置くか、外部の相談窓口を紹介するなどの対応が望ましいと言えます。
ゴミ出しのトラブルの例
日本では、ゴミの回収日や曜日ごとに回収してもらえるゴミの種類、ゴミを置く場所や時間帯など、さまざまなゴミ出しのルールがあります。多くの外国人はこうしたルールになじみがなく、ルールに違反して地域住民や家主とトラブルになるケースが多発しています。
- 決められた場所にゴミを置かず、道路等に放置する。
- 決められた回収日以外の日にゴミを出す。
- ゴミの分別をしない。
また、外国人の相談窓口を運営している会社によると、外国人からゴミに関する相談の中で一番多いのは粗大ゴミの捨て方についてです。「ふとんを捨てたい」、「スーツケースを捨てたい」、「ベッドを捨てたい」といった相談です。
大型ゴミを捨てる場合、例えば東京都では次のような手順が必要です。
- 電話かインターネットで「粗大ゴミ受付センター」に事前に申し込む。
- そのゴミを回収してもらうために必要な「ごみ処理券」をコンビニなどで購入する。
- ゴミ処理券をゴミにはり、指定された収集日に決められた場所に出す。
しかし、外国人にとっては、どこに電話したらよいか、いくらの処理券を買ったらよいかなどを自分で調べるのが困難な場合もあります。
その場合、受け入れ事業者や登録支援機関、監理団体によるサポートが求められます。その地域のゴミ出しのルールを調べ、必要に応じて通訳も交えて外国人材に粗大ゴミの出し方を教えたり、手続きを手伝ったりします。
騒音トラブル
外国人が騒音で近所に迷惑をかけるケースが多く、受け入れ事業者側にも対応が必要です。騒音で迷惑をかける事例としては次のようなものがあります。
- 室内で大音量で音楽をかける。
- 多数の外国人が部屋に集まって飲食をし、大声で騒ぐ。
- 携帯電話による通話をバルコニーで大声で長時間行う。
受け入れ事業者か登録支援機関、監理団体が、日本では夜遅くまで騒ぐことや長時間騒ぐことが周囲の迷惑になるということを外国人材にしっかり指導しなければなりません。
家主と良好な関係を保つ

ゴミ出しや騒音などのトラブルがあると、家主が近所から苦情を受けることもあります。また、外国人入居者については住宅の使用や退去をめぐるトラブルも比較的多く、家主に迷惑をかけることがあります。
受け入れ事業者などは外国人材に住宅をきちんと掃除しながら適切に使うよう、また退去時にトラブルを起こさないよう、サポートしてください。
退去時のトラブル防止
外国人入居者が賃貸住宅を退去する際によく起こすトラブルとして次のようなものがあります。
- 部屋に私物やゴミを大量に残して退去する。
※本人とは連絡が取れず、処分費用も請求できない。 - 家主に事前に知らせずに退去する。
- 電気・ガス・水道を解約せずに退去する。
こうしたことは家主の負担を増やし、ほかの外国人が日本で家を借りる際に警戒される要因にもなります。外国人材が転勤や退職などに伴って住宅を退去する際、こうした事柄を守るよう、受け入れ事業者や登録支援機関は確認や指導をしてください。
部屋に何も残さない
退去時は部屋に何も残さないように確認・指導してください。特に大型家具や洗濯機、冷蔵庫などの処分には高い費用がかかりますので、家主が困らないようにしてください。
家主に退去通告または延長相談
住宅の賃貸借契約は多くの場合24カ月間です。それより長く住みたい場合や、逆にそれより早く退去したい場合は、事前に管理会社か家主に相談するようにサポートしてください。できれば契約満了の2、3カ月前に相談すると、円滑に進みます。
契約通り24カ月で退去する場合でも、退去の1カ月以上前に管理会社か家主に連絡しましょう。連絡が遅れると、余分に1カ月分の家賃を請求される場合もあります。
ライフラインの解約
退去前に電気・ガス・水道やWi-Fiなどの契約を解除し、最終月の費用を支払うよう、サポートしてください。
管理会社のチェック
管理会社に退去日を事前に連絡し、退去前の部屋をチェックしてもらいます。年月の経過や通常の生活に伴う壁・床・畳・ふすまなどの変色・劣化への対応は家主に負担義務がありますが、入居者の不適切な使い方による破損や汚れについては入居者が原状回復費を負担しなければなりません。
通常は、入居時にあずけた敷金からその費用を支払い、残額を返してもらいますが、逆に追加で支払わなければならない場合もあります。できれば、受け入れ事業者か登録支援機関も管理会社によるチェックに立ち会いましょう。
あいさつ

近所同士で「おはようございます」「こんばんは」といったひと言があれば、お互いの感情が大きく変わり、あいさつ一つで周囲から好意的に受け止められるようになります。あいさつは近所と良い人間関係をつくるための第一歩であることを外国人材に指導してください。どのような場面でどのような挨拶をしたらよいかも教えてあげてください。
指導者からあいさつする
九州地方のあるリサイクル会社では10人前後の技能実習生が働いていますが、当初は、職場になじめないのか、皆、元気がありませんでした。そこで、会長が毎朝現場に出向いて実習生たちに自分から「おはよう」と声をかけ、彼らの体調や気分を簡単な日本語で聞くようにしました。
すると、実習生たちは次第に元気になりました。また、会長や職場の人と勤務前後や休憩時間に話す機会が増えたため、夜間や休日に日本語の勉強もするようになりました。このため、買い物でスーパーに出かけたときなどに人から声をかけられると、あいさつしたり受け答えしたりすることができるようになりました。
地域行事への参加をサポートする

特定技能の支援業務
入管法が定める特定技能外国人に対する受け入れ事業者や登録支援機関の支援義務の中には、日本人との交流サポートが含まれています。
具体的には、特定技能外国人に職場や住居の地域住民と交流する機会を提供することが義務付けられています。地域の行事について情報を提供するほか、参加の手続きなどをサポートすることも必要です。
交流サポートについては、技能実習受け入れ事業者や監理団体、民間団体による好例がたくさんありますので、参考に紹介します。
受け入れ会社のサポートで地域行事に参加
岩手県の縫製会社の地元では、春祭りで約2,000人が踊りながら市内をパレードするイベントがあります。同社は十数年前から技能実習生を受け入れ、社長らが実習生たちを春祭りに連れて行き、日本の文化を楽しませていました。そして、数年前からは実習生全員(フィリピン人とベトナム人の女性計10人)がパレードに参加するようになりました(=上の写真)。
地元で働く若い外国人たちが地域行事に参加すると、地域の人たちから大歓迎されます。周りから喜ばれ、声もたくさんかけてもらえるので、実習生たちは喜んでいます。
また、社長らは実習生一人一人に浴衣を買い与え、地域の夏祭りにも連れて行きます。このような交流も手伝い、彼女たちは近所でも買い物先でも、住民から笑顔で接してもらえ、地域から歓迎されているという実感を持って生活しているそうです。
外国人材と地域との共生は受け入れ事業者にとってもプラスになります。この会社は給料が飛び抜けて高いわけではなく、立地も人口の少ない地域ですが、実習生たちが職場でも地域でも気分良く過ごせるため、「この会社に残って特定技能をしたい」という実習生が多いとのことです。
ボランティア団体による交流サポート

静岡県の工場でプレス加工の技能実習をしたベトナム人男性は毎週末、地元の国際交流団体が行う日本語教室に参加し、日本人教師や他社の実習生と交流しました。日本語教室に参加した外国人たちはこの団体のサポートで地域の祭りで神輿をかついだ(=上の写真)ほか、敬老会の集まりに参加してお年寄りとも交流しました。そのことによって地域から歓迎されましたし、自分たちも地域が好きになりました。
さまざまなサポート事例
外国人技能実習機構(OTIT)は「課外活動」として受け入れ事業者や監理団体のサポートによる交流例をいくつか紹介しています。
日本人社員と一緒に文化イベントに参加
秋田県の受け入れ会社では、ベトナム人実習生3人と日本人社員2、3人が地元の文化紹介施設で「なまはげ変身」体験をしたり、祭りに参加したり、町内会主催の寿司作り体験に参加したりしました。実習生たちは地域社会から歓迎されたほか、日本人社員たちとも仲良くなりました。
祭りに屋台を出店
富山県滑川市の夏祭りではベトナムの民族音楽のコンサートや民族衣装の試着体験なども行われています。監理団体と受け入れ会社が手伝ってベトナム人技能実習生10人がこの祭りで屋台を出しました。実習生と地域住民との良い交流機会になり、実習生には地元への愛着が生まれ、地域住民も実習生たちへの理解を深め好意を持つようになりました。
社内交流が地域交流の足がかりに

特定技能外国人や技能実習生の多くは母国で日本語を半年から1年間学んだだけで来日するため、最初は日本語を聞き取ることも簡単な日本語を口に出すことも難しく、言葉の壁から地域との交流に対しても及び腰になりがちです。
そこで、勤務の前後や休み時間などに外国人材と日本人が交流できる機会をなるべくたくさん設けることが望ましいと言えます。
「日本に来て良かった」と話す外国人材の多くが、職場での交流を足がかりに日本社会にとけ込んでいます。
- 一緒に働く日本人社員たちが休憩時間などに話し相手になってくれる。
- 社長や世話役の日本人がよく話しかけてくれる。
- 世話役の日本人が休みの日に買い物に連れて行ってくれる。
このほか、受け入れ事業者がオンラインや対面の日本語教師による授業を提供する事例もあります。日本人と話すことに慣れ、交流の機会を広げていく動機になります。
まとめ

このページのまとめ
◎ 外国人が地域住民と良い関係を築くには、まず地域社会のルールを守ることが大切です。特にゴミ出しや騒音に関するトラブルが多いので指導・サポートをしてください。粗大ゴミの出し方が分からずに困る外国人も多いので、これもサポートしてください。
◎ 家主との関係では、住宅の使用や退去に関するトラブルが多いので、受け入れ事業者や登録支援機関による指導・サポートが必要です。
- 十分な期間をあけて家主に退去通告をする。
- 退去の際は部屋に何も残さない。
- 部屋の使い方が不適切な場合、多額の退去跡補修費が必要になる場合がある。
- 退去前にライフラインをきちんと解約する。
- 受け入れ事業者か登録支援機関が退去跡チェックにも立ち会う。
◎ あいさつは地域社会にとけ込む第一歩です。あいさつの場面ややり方についても指導してください。
◎ 外国人材の地域交流支援は特定技能の受け入れ事業者や登録支援機関の義務です。地域行事への参加、敬老会での交流、社員と一緒にイベント参加、祭りへの参加などのサポート事例があります。
◎ 外国人材が社内交流を深めることで日本人とのコミュニケーションに慣れ、地域とも交流できるようになります。
