
「送出機関など海外の人材会社の選び方」で、特定技能や技能実習で海外の人材会社を選ぶ際の4つのポイント「日本語教育力」「募集・選考力」「生徒から取る費用」「日本入国後のフォロー」について紹介しました。この記事では、「入国後フォロー」についてさらに説明するとともに、「日本に駐在員がいる方が良いか」「政府認定機関かどうか」「過剰接待やキックバック」「日本人教師がいる方が良いか」といった観点についても説明します。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
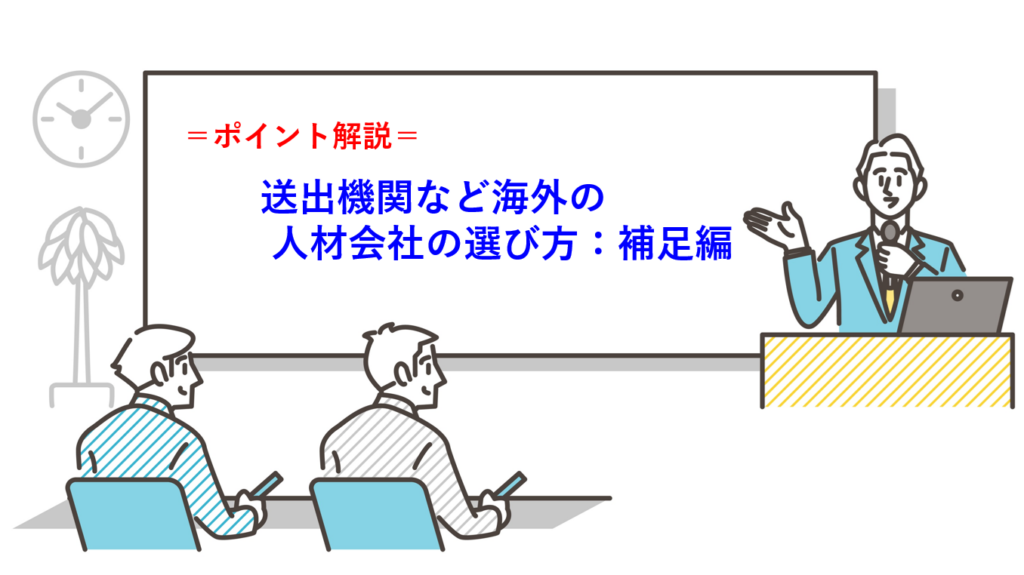
・入国後のメンター役ができるか?:外国人材を日本に送り出した後も、教師や担当職員がSNSなどで彼らとコミュニケーションを取り続ける送出機関もあります。教師や職員は外国人材の不満・悩みが小さなうちから助言・指導を行うことができ、トラブルの早期防止・解決につながります。これによって早期離職や失踪等を防止することができます。
・日本に駐在員がいる方が良い?:
- 駐在員を置くのは外国人材サポート目的以外に営業目的があり、後者の方が優先です。
- 外国人材サポートは母国からでも代替が可能です。
- 無償で常駐通訳を提供させるなど、登録支援機関や監理団体が取引上の立場に乗じて海外の人材会社に過度の便宜供与を求めることがあります。
・政府認定の送り出し機関か?:二国間取り決めや日本の規則にそって送出業務をしているとして各国政府が認定した送出機関であれば、技能実習、特定技能、技人国のどの外国人の紹介をお願いするにも比較的安心です。
・過剰接待やキックバックをしていないか?:監理団体幹部が海外の人材会社から過剰接待や巨額のキックバックを受けている例が多数あります。そのおカネは外国人材が負担します。
・ビジネスコミュニケーション力:事務・連絡能力が低い送出機関もあり、避けた方が無難です。
・現地を訪問したら、ここをチェック:教師や生徒と話して日本語力を確認し、教室内の生徒数もチェックしましょう。
・日本人教師はいた方が良い?:日本語教師の質によります。現地国籍の熱心で教え上手な教師がいるかどうかの方がより重要です。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 入国後のフォロー(メンター役)ができるか?
- 日本に駐在員がいる方が良い?
- 政府認定の送り出し機関か?
- 過剰接待やキックバックをしていないか?
- ビジネスコミュニケーション力
- 現地を訪問したら、ここをチェック
- 日本人教師はいた方が良い?
- まとめ
入国後のフォロー(メンター役)ができるか?

送り出し管理費
技能実習生を受け入れる場合、送出機関に「送り出し管理費」という費用を毎月支払います(監理団体が監理費と一緒に徴収)。送り出し管理費の趣旨は「実習生の選抜・選考」「日本語教育等の事前研修」「実習生に対する相談・支援」などに要する費用で、実習生1人あたり月5,000円(介護の場合は5,000~10,000円)が相場です。
送出機関によるメンター機能
送り出し管理費を受け取りながら、サポートがほとんどない送出機関もあります。しかし、技能実習生を日本に送り出した後も、教師や担当職員が受け入れ事業者ごとに実習生とSNSグループを作るなどし、メンター(相談役)として実習生と日ごろからコミュニケーションを取り続けてくれる送出機関もあります。
SNSのグループチャットや個人チャットで実習生の仕事や生活の状況を日ごろから聞き取り、必要な場合はSNS電話やビデオ通話も使って助言・指導を行います。
これは技能実習生だけに限らず、その人材会社で一定期間の日本語教育を受けた「教え子」であれば、特定技能や技人国の外国人も同じようにフォローします。
送り出す前に信頼関係が構築されているのと教師や職員が連絡を取り続けることで、外国人材がいつでも頼れる状態をつくり、登録支援機関・監理団体や受け入れ事業者に明かさないような本音(特に不満や悩み)も把握します。
教師や職員は外国人材の不満・悩みが小さなうちから助言等を行うことができ、必要に応じて登録支援機関や監理団体にも情報を共有してトラブルを早期に防止・解決します。これによって早期離職や失踪等を防止することができます。
メンター役は日本駐在の方が良いか?
海外人材会社のこのような役割(メンター)をその会社の日本駐在が担当するケースもあります。ただし、母国の教師や職員の方が入国前に長期間一緒に過ごし信頼関係を築けているのでメンターに適している場合もあれば、日本駐在が外国人材によく会いに行くなどして信頼を得る場合もあり、どちらが良いとは一概には言えません。
日本に駐在員がいる方が良い?

駐在員等を置くさまざまな目的
送出機関など海外の人材会社が日本に事業所(支社、駐在事務所等)を置くのは、外国人材のフォローという目的もありますが、より大きな目的は営業です。例えば次のような狙いがあります。
営業目的
① 取引先の登録支援機関や監理団体の利便のため、日本駐在が連絡窓口となります。
② 日本人向けのホームページやパンフレットに日本事業所や駐在員の連絡先を記載すると、外部から信頼されやすく、連絡も受けやすくなります。
③ 駐在員が既存の取引先との関係維持や新規取引先の開拓を行います。歩合制の営業マンに駐在員の名刺を持たせているだけの場合もあります。
④ トラブル時に駐在員が外国人材の受け入れ先に行ければ、登録支援機関や監理団体は通訳担当者を行かせるだけですむ場合もあります。
サポート目的
⑤ 駐在員が外国人材と信頼関係を築ければ、外国人材の悩み・不満を早期に把握できます。
※これについては前章でくわしく説明しています。
⑥ トラブルが起きた場合、登録支援機関や監理団体を補助してヒアリングや外国人材への説得・サポートを分担できます。
⑦ 外国人材のけがや病気、事故、あるいは災害の場合に、実習生の家族に連絡を行います。駐在員がいない場合は、登録支援機関や監理団体と海外の人材会社が連携して行います。
受け入れ事業者にとっての駐在員の必要性
送出機関の駐在員等の人数が少ないと、営業目的が優先され、外国人材サポートがおろそかになる場合もあります。日本に事業所があるかどうかだけではなく、どのようなスタッフがいて、どのような役割を果たしているかを調べる必要があります。
日本に駐在員がいても、多くの場合、問題が起きたとき以外は外国人材に頻繁に会いに行くわけではありません。一方、良い送出機関の教師や担当者は、日本に送り出した人材と日ごろからSNS等で連絡を取り合っているので、⑤の「外国人材と信頼関係を築く」役割は本国でも代替できます。
その場合、⑥のトラブルについても、事前に防止したり登録支援機関や監理団体を遠隔でサポートしたりすることが可能です。
登録支援機関や監理団体の業務肩代わりは不適切
入国後のトラブルへの備えとして、日本に駐在事務所等を置いている海外人材会社を勧める情報もあります。例えば、監理団体の元スタッフがネット上で下記のような趣旨の記事を書いています。
「入国後のトラブル対応について、多くの送出機関は遠隔通訳のみにとどまるが、日本に駐在事務所がある少数の送出機関は一緒に企業に行ってくれることもある。送出機関が実習生と同じ母国語の駐在員を日本に置いていると、トラブル発生時に連携してスピーディーに対応できる」
つまり、送出機関の駐在員を通訳代わりに使い、トラブル対応に同行させるという趣旨です。筆者が取材で現認したもっと不適切な事例では、 送出機関に所属する外国人(駐在員等)に、監理団体が日常的に通訳をさせているケースもありました。
しかし、多くの登録支援機関や監理団体は通訳・翻訳の担当者を自分で雇用し、訪問指導や「外国人材の相談対応・助言・指導」なども担当させています。受け持つ人材が少ない国については、外部の通訳を使う場合もありますが、その場合も費用は自前です。
また、技能実習生のトラブル対応は一義的には監理団体の責務です。監理団体が責任を持って受け入れ事業者や実習生からヒアリングを行って対処し、送出機関は必要に応じて補助的に実習生へのヒアリングや指導・説得をサポートします。
監理団体や登録支援機関が、本来は自前で行うべき業務を取引上の優位に乗じて外国の人材会社(送出機関等)に肩代わりさせている場合、受け入れ事業者はその機関・団体との取り引きを再考すべきかも知れません。
政府認定の送り出し機関か?

送出機関の認定要件
技能実習の送出機関とは、実習生を日本の監理団体に取りつぐ企業や団体(実習生の派遣元)です。技能実習生の送り出し業務をするには認定が必要です。「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の第25条(規則第25条)によって定められた12項目の要件を要約して紹介します。
- 技能実習の申し込みを日本の監理団体に適切に取りつぐことができるとして、所在する国の公的機関から推薦を受けている。
- 技能実習制度の趣旨を理解して志望する人だけを選んで送り出す。
- 技能実習生等から徴収する手数料その他について算出基準を明確に定めて公表する。その費用を実習生に明示し十分に理解させる。
- 技能実習を修了して帰国した人が技能を活用できるよう、就職先あっせん等を行う。
- フォローアップ調査への協力等、日本政府や外国人技能実習機構からの要請に応じる。
- 当該機関や役員が日本や所在国で禁錮以上の刑等に処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない者ではない。
- 所在する国・地域の法令に従って事業を行う。
- 技能実習生や家族から保証金の徴収等を行っていない。
- 技能実習の契約不履行について違約金等の取り決めを行っていない。
- ⑧⑨の行為が行われていないことを技能実習生に確認する。
- 過去5年以内に偽造文書の使用等を行っていない。
- その他、技能実習の申し込みを監理団体に適切に取りつぐ能力がある。
外国人技能実習機構が監理団体向けに公表している「外国の送出機関を選ぶ際のポイント」では、主に上記12項目に沿って送出機関選びの着眼点を紹介しています。
二国間取り決め
技能実習制度について日本は14カ国と二国間取り決めを締結しています。内容は国ごとに異なりますが、違法な行為を行わないことや手数料算出基準を明確にすることなど共通部分も多いです。
二国間取り決めを締結した国では、その国の政府が、各企業・団体が二国間取り決めと日本の規則第25条(12要件)を満たしているかどうかを審査し、送出機関として認定します。
政府認定の送出機関かどうか
二国間取り決めがある国の場合、政府認定の送出機関かどうかは大事です。特定技能や技人国の人材紹介を依頼する場合も、技能実習の送出機関の認定を受けている人材会社の方が安心です。
政府認定送出機関は、外国人技能実習機構のウェブサイトで国別に公開されています。技能実習候補者から高額費用を徴収するなど不適切な行為を起こすと、送出機関の認定を取り消されますので、リスト更新時に企業・団体名が削除されます。
※ただし、日本は中国やネパールとは二国間取り決めを締結していません。
過剰接待やキックバックをしていないか?

過剰接待やキックバックの横行
技能実習制度では、送出機関が監理団体から多くの求人を発注してもらおうと、監理団体の幹部等に過剰な接待を行うケースがあります。また、本来は禁止されているキックバック(謝礼)を監理団体側に提供することもよくあります。
技能実習の送出機関が特定技能外国人の送り出しも行っていますので、このような接待・キックバック攻勢は技能実習に限らず特定技能制度でも起こり得ます。
複数の監理団体関係者によると、例えばベトナムでのキックバックの相場は実習生1人あたり1,000ドル以上です。監理団体から求人が1人寄せられ実際に入国するたびに1,000ドルが積算されます。その監理団体からの発注で年間200人を送り込んだとすれば、年20万ドルの大金が謝礼(キックバック)として監理団体幹部(理事長など)に非公式に環流されます。
キックバックは政府から禁止されていますので、このようなカネは正規手続きでは振り込めません。そこで、技能実習生が日本に行く際に、多額の現金を一人一人に渡して飛行機で運ばせ、空港で回収するというケースもあります。
過剰接待やキックバックは以前と比べればましになったとも言われますが、複数の監理団体幹部によると、「最近でも、海外の人材会社から特定技能や技能実習に関する営業を受ける際、先方からキックバックの提案を受けることが頻繁にある」とのことです。
過剰接待やキックバックの原資はだれが負担するのか?

節度ある監理団体や受け入れ事業者が海外の人材会社を訪問したときに受ける便宜としては、現地での送迎や1、2回の食事ぐらいがせいぜいです。これに対し、複数の監理団体関係者によると、現地での飲食・宿泊の一切に加えて風俗接待すら人材会社に負担させ、さらに巨額のキックバックも受け取ってきた監理団体幹部がたくさんいます。
問題は過剰接待や多額のキックバックの原資が最終的に外国人材たちの負担になることです。そのような人材会社(送出機関等)は生徒・候補者に高額の費用を請求し、生徒たちは多額の借金を抱えて来日することになります。
借金が多い外国人材は給料だけに関心が集中し、早期離職・転職をするケースが多くなります。
負担額を本人たちに確認
外国人材が負担した額については、本人たちに聞けば分かります。ただし、海外の人材会社から言い含められて本当のことを言わないことがありますので、信頼関係ができてから広くまんべんなくヒアリングしてください。
特定技能や技能実習の生徒・候補者から相場を超える高額費用を徴収している場合、その人材会社が過剰接待やキックバックを行っている可能性があります。また、仮にそうではなくても、生徒たちの負担が大きいことに変わりはないので、取引を再検討する余地があります。
ビジネスコミュニケーション力

海外の人材会社の事務能力やビジネスコミュニケーション力も大切です。いくら人材募集力や教育力があっても、次のような人材会社は避けた方がよいでしょう。
- 電子メールや電話で仕事のやり取りをする際、担当者の日本語力が著しく低い。
- 事務連絡担当者の電子メールへの返信が著しく遅い。
- 日本語で難しい内容の会話をできるスタッフが常駐していない。
- 必要な事務手続きや書類作成の期限を守らない。
これらは直接には登録支援機関や監理団体が影響を受ける事柄ですが、受け入れスケジュールに影響が及ぶなどの恐れもありますので、避けた方が無難です。日本の機関・団体に確認しましょう。
現地を訪問したら、ここをチェック

受け入れ事業者が採用面接のため現地に出向く場合があります。その際、海外の人材会社を訪問しますが、現地で説明を聞き授業を見学しても、十分な知識・経験がないと、実際の「募集力」や「教育力」を判別できません。
そこで、「募集力」のチェックは登録支援機関や監理団体に任せ、日本語教育力をチェックする手法を3点だけ紹介します。
① 教師と話す:海外の人材会社の教師には元技能実習生で日本語能力試験N3やN4程度の人も多いうえ、普段は日本人と話す機会がないので、話しかけてもまともに会話できないことが多いです。そこで、主任格の複数の教師に話しかけて会話力をチェックします。
② 生徒と話す:最も大事なことは、日本語を5カ月以上勉強した生徒たちと会話をさせてもらうことです。あいさつ程度の会話ではなく、ある程度時間をかけて話す必要があります。また、わかりやすい日本語を使うなどの配慮も必要です。このチェックを適切に行うと、送出機関によって生徒の日本語会話力に大きな違いがあることが分かります。
③ 教室の人数:一つの教室の生徒数が20人以内の方が、教育効果が高いです。
日本人教師はいた方が良い?

日本人教師の質による
日本語を数カ月勉強した生徒なら、日本人教師による会話練習を受けている生徒たちの方が、会話力があります。ただし、教育の質に左右されます。
海外の日本語教室の日本人教師は2年以内に離職するケースが非常に多く、一つの職場になかなか定着しません。また、日本国内の日本語学校と違って、日本語を教育するための教育を受けた人や資格を持っている人ばかりではありません。
インドネシアやベトナムの日本語教室を多数訪問した経験では、日本人教師がいるのに生徒の会話力がもうひとつの教室もあれば、日本人教師がいないのに平均的な会話力が飛び抜けている教室もあります。また、最近は、日本人教師によるオンラインの会話授業を活用する教室も増えています。
そこで、日本人教師の有無よりも、生徒の実際の会話力で判断する方が良いと言えます。具体的には、現地訪問の際に5カ月以上教育した生徒と会話するか、その人材会社から訪日してすでに他社で働いている外国人材に会って判断します。
より大切なのは現地国籍の優秀な教師
生徒・候補者は大人なので、幼児のように外国語を頭の中で母国語に変換せずに理解する学習はできません。そこで、会話以外の初心者向け授業(文法、読解、漢字など)は母国語で教える方が適していると言われています。
しかし、現地国籍で日本語力が高く、熱心で教え方も上手な教師が絶対的に不足しています。日本人教師の有無よりも、そのような教師がいるかどうかの方が重要です。この点も、教室を見学するだけでは十分に分からないので、やはり、生徒や卒業生(すでに日本で働いている人材)の会話力で判断するのが確実です。
まとめ

このページのまとめ
◎ 外国人材を日本に送り出した後も、教師や担当職員がSNSなどで彼らとコミュニケーションを取り続ける送出機関もあります。教師や職員は外国人材の不満・悩みが小さなうちから助言等を行うことができ、トラブルの早期防止・解決につなげられます。
◎ 海外人材会社が日本に駐在員を置くのは外国人材サポートの目的もありますが、どちらかというと営業目的が優先です。外国人材サポートは母国からでも代替可能です。
◎ 無償で常駐の通訳を提供させるなど、登録支援機関や監理団体が取引上の立場に乗じて海外の人材会社に行き過ぎた便宜供与を求めることがあります。
◎ 二国間取り決めや日本の規則にそって送出業務をしているとして各国政府が認定した送出機関であれば、どの在留資格の人材紹介をお願いするにも比較的安心です。
◎ 監理団体などの幹部が海外の人材会社から過剰接待や巨額のキックバックを受けている例が多数あります。その原資は外国人材が負担しています。
◎ 日本人教師の効果はその教師の質によります。それよりも、現地国籍の熱心で教え上手な教師がいるかどうかの方が重要です。
