
外国人が海外就労先として日本を選ぶと、在留資格等を取得するための長い手続きを経てようやく日本に入国します。しかし、日本で生活していくには、入国後もさまざまな行政手続きが必要です。その中には、外国人にとって分かりにくいものも少なくありません。「選ばれる国」や「選ばれる事業者」になるためには、行政手続きなどの利便性向上に加え、受け入れ側によるサポートが望まれます。外国人へのサポートが求められる各種手続きについて紹介します。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
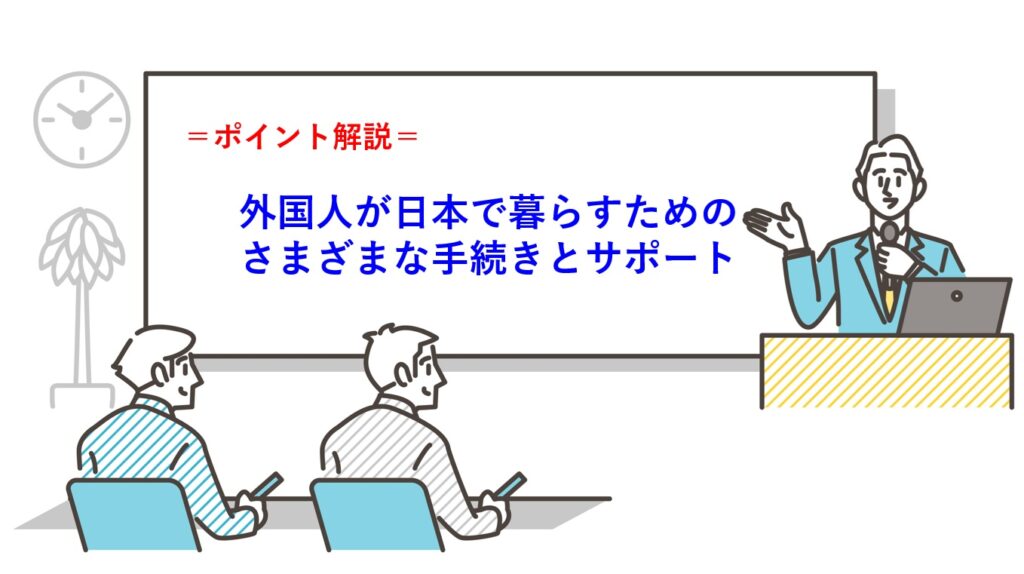
新規入国や引越にともなう手続き、国民年金、妊娠・出産・育児に対する行政サービス、保育園入園の手続きなど、外国人材が日本で生活するためにはさまざまな手続きがあります。受け入れ事業者がそれらをサポートすることで外国人材は非常に助かります。
・入国後や引越時の行政手続き:日本に初めて入国したときや引っ越したときは、役所への届け出が必要です。届出関係は役所の窓口に行く必要があり、難しい日本語のやり取りも想定されます。外国人材の受け入れ側が入国直後以外でも必要に応じて付き添いなどのサポートをすることが望まれます。
- 新規入国時の転入届(住民票、マイナンバー通知書)
- 引越にともなう届出
・マイナンバーカード:在留資格の期限を更新する場合、マイナンバーカードの有効期限も変更(延長)しなければなりません。
・国民年金制度の落とし穴:学生が卒業まで保険料を納めなくてもよい「学生納付特例制度」には申請が必要です。申請なしで保険料を納めないと「滞納」になり、そのままでは在留資格変更が許可されません。外国人留学生の年金加入について情報サポートが必要です。
・妊娠・出産・育児に対する公的サポート:外国人が日本で出産・育児をする場合も行政サービスを多数受けられますが、外国人が独力でサービスの全容を把握するのは難しく、受け入れ側からのサポートが求められます。
- 母子健康手帳交付
- 妊婦健康診査への助成
- 出産育児一時金、出産手当金
- 育児休業給付金
- 児童手当、児童扶養手当
- 乳幼児医療費助成制度
・保育園に入るための複雑なプロセス:子どもを保育園に入れるには、給付金(補助金)の申請や就労証明書、課税証明書などさまざまな提出物が必要です。「保活ポイント」という制度もあります。行政のホームページだけでこれらの全容を正確に把握するのは困難で、サポートが望まれます。
◆このページの内容
入国後や引越時の行政手続き

入国後や引越時に市区町村役場で行う手続き
外国人が日本に初めて入国したときや、入国後しばらくして引っ越したときは、地元の役所への届け出が必要です。
新規入国時の転入届(住民票、マイナンバー通知書)
在留カードを持っている外国人は地元の市区町村に住所を届け出なければなりません。
- 新規入国の場合、住所を決めた日から 14 日以内に市区町村の役所に転入の届出
- 申請時には在留カード(交付待ちの場合はパスポート)が必要
- 家族と一緒に暮らす場合は、婚姻証明書や出生証明書なども必要
転入届を出せば、住民票が作成され、住民票の写しを申請することができるようになります。住民票の写しはさまざまな行政手続きや契約などで使います。また、転入届を出すと、後日、役所から自宅にマイナンバー通知書が届きます。
引越にともなう届出
引越するときは次のような届け出が必要です。
① 日本で別の市区町村へ引っ越す場合
- これまで住んでいた市区町村に「転出」の届出
- 引越後は、新しく住むことになった市区町村に「転入」の届出
② 同じ市区町村内で引っ越す場合
- 地元の役所に「転居」の届出
③ 海外へ引っ越す場合
- 地元の役所に「転出」の届出
受け入れ側のサポートの重要性
日本に初めて来たときは、受け入れ側(受け入れ事業者や監理団体、登録支援機関、留学先の学校の担当者など)が役所に付いて行って行政手続きを手伝うことも多いですが、入国後しばらく経ってからの新たな手続きは、外国人材や家族が独力で行うケースも多いです。
住民票の写しや印鑑証明を取得するだけなら、マイナンバーカードがあればコンビニでも可能ですが、届出関係は役所の窓口に行く必要がある場合がほとんどです。その場合、次のような不便があります。
- 役所は平日しか開いていないので、外国人材や留学生が役所で何か手続きをしようと思ったら、学校や仕事を休む必要がある。
- 役所の窓口を何カ所も回って手続きを行う場合がある。複数の役所を訪ねて手続きを行うこともある。
- 窓口手続きが基本的には日本語で行われているため、外国人にとっては、日本語会話に習熟していない限り、手続きをとても困難に感じることがある。
役所窓口でのコミュニケーションについては、役所に常駐する通訳者やオンライン通訳サービスが増えてきたとはいえ、多くの役所で対応言語の種類や通訳者の数がまだ限られています。また、通訳アプリで対応する場合、その使い方に習熟していない(アプリが正確に翻訳できるような分かりやすく簡潔な日本語を使えない)窓口担当者もたくさんいます。
行政にはこのような不便を解消していく努力が必要です。そして、外国人材の受け入れ側(受け入れ事業者や登録支援機関など)にも、状況に応じて継続的なサポートを提供することが重要です。
マイナンバーカード

入国後、役所に転入の届出をする際にマイナンバーカードの交付申請も同時に行なうことができ、後日、カードができてから受け取ります。そのときに交付申請をしない場合も、後日、オンラインや郵送で申請することができます。
来日して一定期間が経ち、在留資格の期限を更新(延長)する場合、マイナンバーカードの有効期限も更新しなければなりません。しかし、そのことを知らない外国人も多く、更新を忘れた場合、マイナンバーカードを有料で新規発行してもらわなければなりません。
これについても、役所の広報の改善に加え、受け入れ側が手続きについて熟知し、外国人材にそれを教えたり役所に付き添ったりするサポートがあると、親切です。
国民年金制度の落とし穴
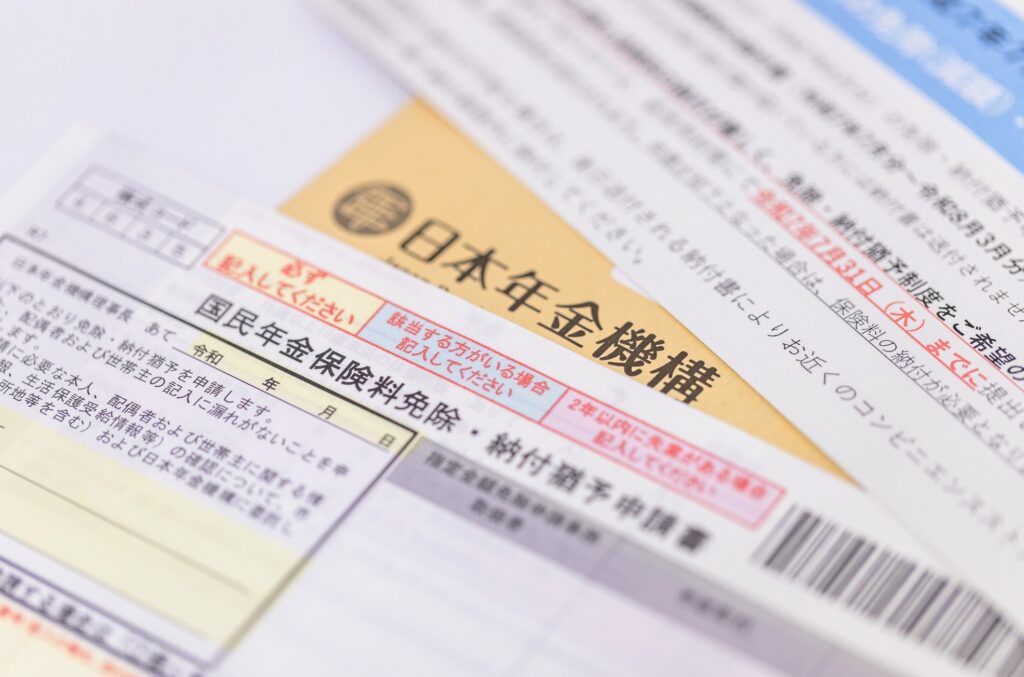
20歳以上の外国人はすべて年金加入が必要
日本で暮らす場合、外国人も20歳以上なら年金への加入義務があり、留学生も例外ではありません。サラリーマンが加入する「厚生年金」については、受け入れ事業者が加入手続きを行い、保険料も納付しますが、留学生や個人事業者などは自分で「国民年金」に加入し、自分で保険料を納めなければなりません。
「老後に日本の年金をもらうことはないから関係ない」と考える外国人も多いかも知れませんが、滞納を続けると、在留資格変更の審査で不利益を受ける可能性があるほか、もしものときに障害基礎年金を受給することもできません。国民年金に加入していれば、不慮の事故などで身体に重い障害を負った場合などに生涯(障害が続く限り)、障害基礎年金を受給できます。しかし、それまで年金保険料を納付していなかった人は受給できません。
学生納付特例を使うには手続きが必要
国民年金に加入するには、市区町村の役所か年金事務所で手続きをします。
学生の場合、卒業まで保険料を納めなくてもよい「学生納付特例制度」がありますが、適用を受けるには申請が必要です。申請せずに保険料を納めないと「滞納」になり、日本で就職が決まって在留資格を変更するときに、滞納額を全納するなどの対処をしないと在留資格変更が許可されません。
「留学生は年金保険料を支払わなくてもよい」という情報が在留外国人向けのSNSなどに投稿されていることがあり、その文言だけを信じて学生納付特例制度の手続きをせずに未納を続けると、後で大変なことになります。
東京都つながり創生財団が運営する外国人相談窓口によると、「国民年金の納付書が届いたが、納めるべきかどうか、納めないとどうなるのか」といった相談が多いそうです。私の友人の元留学生たちも、このような年金制度の重要ポイントについて、年金事務所からの郵便物や日本年金機構のホームページだけでは十分に把握できなかったとのことです。
外国人留学生の年金加入については、受け入れ教育機関による情報サポートが不可欠です。また、留学生が介護事業者等から奨学金を受給して日本語学校や介護専門学校に通っている場合は、事業者による目配りも求められます。
妊娠・出産・育児に対する多様な行政サービス

日本で暮らす外国人が妊娠・出産・育児をする場合、日本人と同じような公的サポート(行政サービス)を多数受けられます。これは日本が外国人材から選ばれるポイントの一つになります。妊産婦や乳幼児の育児に対する行政サービスには次のようなものがあります。
- 母子健康手帳交付
- 妊婦健康診査への助成
- 出産に関する手当:出産育児一時金、出産手当金
- 育児休業時の生活支援:育児休業給付金
- 産前・産後のサポート:相談事業、母親交流支援
- 育児に関するサポート:児童手当、児童扶養手当
- 子どもの医療費助成:乳幼児医療費助成制度
外国人材や家族が独力でこうした行政サービスの全容を把握しもれなく申請するのは、決して簡単なことではありません。受け入れ側によるきめ細かい情報提供や申請書作成補助、役所同行などのサポートがあれば、外国人材は非常に助かります。
保育園に入るための複雑なプロセス

日本で働く外国人材が保育園に子どもをあずけたい場合、日本人と同じように保育園を探さなければなりません。保育園見学などを経て行かせたい保育園が決まると、入園の申し込みには例えば次のような書類が必要です。
- 入園申込書
- 給付金(補助金)の申請書
- 重要事項確認書・同意書
- 子どもの健康状況に関する申告書
- 夫婦の勤務証明書(就労証明書)
- 夫婦の直近1年の課税証明書
問題は提出書類が多いことや、期限に遅れると選考対象に入れてもらえないことですが、外国人は日本人と比べて期限に関する認識が甘い場合も多々あります。そのうえ、保育園によっては競争率が高く、そういう保育園に行きたい場合は「保活」に関する自分のポイントを知ることも必要です。
行政のホームページだけでこのような手続きの全容やポイントシステムについて正確に把握するのは日本人でも困難です。そこで、在留外国人の多くは外国人向けに作られた民間のウェブサイトやSNSで情報を集めています。しかし、その場合、情報が不十分・不正確な場合があります。
そこで、受入れ側がその地域の保育園事情や入園手続きを調べて情報提供を行なうなどサポートをすると、外国人材の苦労が大きく軽減されます。
まとめ

このページのまとめ
外国人材が日本で生活するためにはさまざまな手続きがあり、受け入れ事業者がそれらをサポートすることで外国人材から選ばれる事業者へと近づけます。
- 外国人が日本に初めて入国したときや、引っ越したときは、地元の役所への届け出が必要です。それには役所に行く必要があり、入国後しばらく経っても必要に応じて同行などのサポートが望まれます。
- 在留資格の期限を更新(延長)する場合、マイナンバーカードの有効期限も変更しなければなりません。
- 学生が卒業まで国民年金の保険料を納めなくてもよい「学生納付特例制度」には申請が必要です。外国人留学生の年金加入について情報サポートが必要です。
- 外国人が日本で出産・育児をする場合、行政サービスを多数受けられますが、外国人が独力でこうしたサービスの全容を把握するのは難しく、受け入れ側によるサポートが求められます。
- 子どもを保育園に入れるには、就労・収入に関する証明書を含むさまざまな提出物があります。高い「保活ポイント」が必要な場合もあります。行政のホームページだけで全容を把握するのは困難で、受け入れ側のサポートが望まれます。
