
外国人材を初めて受け入れる際、「わが社こそは外国人材と上手に共生し、良い受け入れを実現するぞ」と意気込む経営者や担当者も多いことでしょう。しかし、実際に雇ってみると、予想に反して大きなすれ違いやまさつが生じる場合もあります。「失敗例から学ぶ」シリーズでは、外国人雇用の失敗例をいくつか取り上げ、その原因を探ります。
外国人材を現場で指導する担当者と十分な話し合いをせずに外国人雇用を進めると、うまくいかないケースが多々あります。この記事では、技能実習や特定技能をサポートするA協同組合への取材に基づき、ある企業の失敗例を紹介します。その失敗から外国人材受け入れの際に見落としがちなポイントを見ていきましょう。
※記事中の画像はすべてイメージ画像です。
実習生の1人が途中帰国

その工場では、機械検査のためにベトナム人の技能実習生(女性)を3人雇いました。1期生3人は日本語力も高く、働きぶりも良かったので、彼女たちの採用から2年後にさらに2期生2人を雇用しました。ところが、そのうち1人は3年間の技能実習期間満了を待たず、途中で帰国することになります。その理由は、彼女が「会社の指示を守れない」ということでした。
同社の技能実習を指導・監督し技能実習生のサポートをしていたA監理団体(組合)は事態をゆゆしきことと受け止めました。再発防止のため、原因を解明しなければなりません。組合は日ごろの実習生サポートで得ていた情報に加え、途中帰国することになった実習生や周辺からくわしくヒアリングを行いました。すると、次のようなことがわかってきました。それはひと言で言うと、現場の日本人管理職が技能実習生たちに求めるレベルが高すぎるということでした。
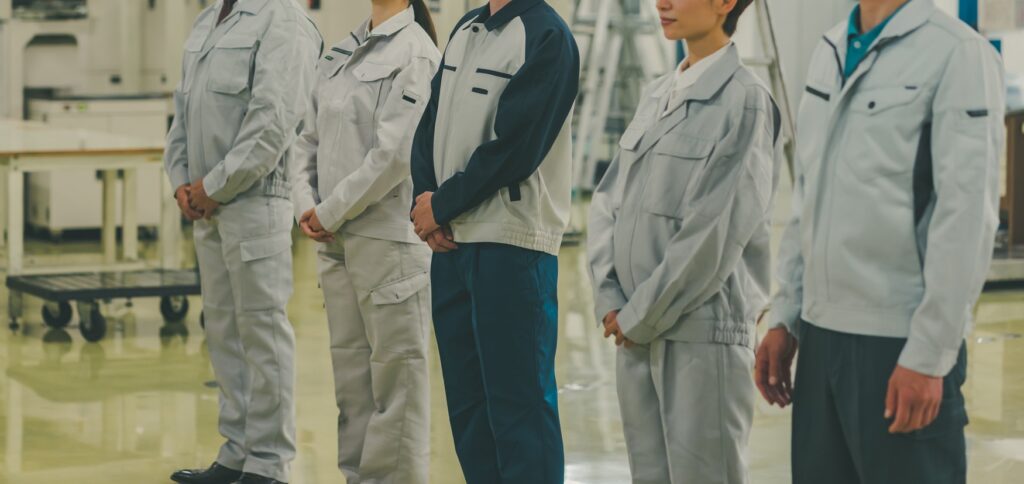
この会社では、朝礼ならぬ「昼礼」があります。それは午後の始業時に行い、午前の仕事の結果と午後の予定を話し合います。その際、報告書の提出が必要で、報告書に求められる日本語レベルが外国人には高すぎたようです。
機械検査の仕事には難しい専門用語もあります。それらの用語を報告書の中で日本人と同じレベルで使うように求められ、2期生のベトナム人たちは十分に対応できなかったということです。
では、1期生の3人がそれを完璧にできたのかというと、彼女たちも管理職が求めるレベルには達していなかったようです。それでも、この3人は技能実習生としては日本語力が高かったのと、仕事ぶりも気に入られていたので、そこまでとがめられることはありませんでした。しかし、2期生たちは日本語力が1期生に比べて劣るのと、何か管理職の気に入らない点があったようで、管理職から注意を受ける日が続きました。
現場の管理職の指導方法
この管理職の男性は、指導する際に言い方がきついという側面がありました。また、指導の仕方もねちっこいと言う評判です。実は、この職場では、日本人の正社員や日本人の派遣社員の離職も相次いでいました。組合は、管理職の指導方法と職場の高い離職率は無関係ではないと考えました。
外国人の職業文化はもともと日本人とは違ううえ、若い人材が母国を離れて外国に出稼ぎに来て不安の中で働いています。職場の管理職や先輩たちがどのような心持ちで外国人材を受け入れるか、指導担当者がどのように指導するかで、外国人材にとって職場の居心地は大きく違ってきます。
中間管理職の孤独と不満

一方、この管理職の側にも大きな不満がありました。問題がこじれてきた段階で、組合は管理職とも面談を繰り返していました。そのときに彼がこうもらしたのです。
「私もベトナム人従業員とは話をしたくない。ストレスが大きい」
実際のところ、外国人材を指導するには、指導担当者(主に中間管理職)に大きな負荷がかかる場合があります。しかし、同社ではこの管理職に対し、外国人材への理解や指導方法を身に付けるための研修やていねいな事前相談はありませんでした。また、実習生たちが実際に配属されてからも、この管理職に経営陣から状況ヒアリングやねぎらいなどのサポートはなかったようです。
彼が、実習生への指導に困難を感じる日々の中で会社からの気遣いを感じることなく孤独を感じ、ともすれば「やっていられない」という気持ちになったとしても無理はありません。
ちなみに、この会社は技能実習生の採用開始と同じころ、ベトナムに現地法人を設立しました。この管理職も出張で現地法人を訪れ、ベトナムという国には好印象を持っていました。
しかし、外国人と利害関係なしで付き合うのと仕事を一緒にする場合とでは人間関係の苦労は格段に違います。この管理職はベトナム人を部下に持つようになって、彼女たちが指示通りにできないことがあるほか、言葉も十分に通じないという状況にストレスを感じ、精神的負担が積もっていったようです。加えて経営陣との意思疎通がないことから孤独や不満を感じ、ネガティブな精神状態の中で実習生への指導が悪化していった可能性があります。
8人のうち2人が途中離脱

2期生1名の途中帰国を機に、組合は社長や現場の管理職と話し合いを重ねて改善を促し、3期生と4期生計3人採用しました。ところが、4期生2人のうち1人が在籍約1年でまたもこの会社を去ることになりました。
事情はこうです。上述の現場管理職の直属の部下で同じく実習生の指導を担当している男性が、実習生が失敗をすると長々とどなるので、実習生はどうしていいかわからなくなりました。また、東南アジア諸国の人々の多くは職場でどなられること自体に大きな違和感とストレスを覚えます。この実習生は上司の指導に耐えられなくなり、心療内科に通うようになりました。そして、とうとう仕事を続けられなくなって、組合が新しい職場を探し、他県の畜産業に転職させたのです。
技能実習では他の業種には転籍(転職)できないので、この実習生は勉強をして特定技能(農業)の技能試験に合格し、特定技能外国人として畜産業に転職しました。もともと日本語力の高い実習生で、特定技能1号に必要な日本語能力試験N4の資格も持っていました。
この実習生は転職先では居心地よく働くことができました。一方、もとの会社は4期・8人のうち2人が技能実習を途中で辞めるという状況で、組合が指導してもなかなか改善に至りませんでした。
考察と学び

現場への丸投げは禁物
中小企業で外国人材を受け入れる際には、経営陣や人事サイドと現場の指導担当者たちとの十分な話し合いが不可欠です。また、外国人材の文化的背景や生活背景を理解し、職場での共生や適切な指導を実現するための研修や教育も本当は必要です。
このような環境整備やサポートをせず、指導の一切を現場任せ(丸投げ)にすると、指導担当者にとっては大きな負担となり、不満が生じます。その場合、その担当者から指導を受ける外国人材が居心地良く感じながら仕事をすることは難しいと言えるでしょう。
指導担当者への気配りや意思疎通
社長は実習生たちを食事に連れていって励ますということはしていましたが、現場での指導は現場の中間管理職に丸投げでした。社長としては、人手不足解消のために外国人材を導入し、彼女たちをときどき食事にも連れていっており、大いに会社の助けになっていると思っていたようです。
しかし、現場で外国人材を指導する中間管理職やリーダーの苦労には思いが行き届かなかったようです。指導担当者たちに対するていねいな事前相談や研修機会の提供もなければ、苦労が増えることに伴う特別な手当の支給もありません。外国人材が実際に配属されてからも状況を聞いたりねぎらったりすることもありませんでした。
このため、担当管理職は、組合からヒアリングを受けるたび、「社長は外国人雇用についてどのような考えを持っているのですか」と組合に聞いてきました。社長と現場との意思疎通が決定的に欠けていたことを示すエピソードと言えます。
ノウハウを学び準備をしてから受け入れる
今回のケースでは、社長の調整不足を背景に指導担当者たちの指導態様の問題(パワハラ、モラハラ)が生じて外国人材が相次ぎ離脱しました。短期間で8人のうち2人がドロップアウトした事実は重く受け止めなければなりません。
外国人材を受け入れる前に、経営者も現場責任者も外国人雇用のノウハウをよく学び、相応の準備をしてから受け入れなければなりません。
そして、外国人材が実際に働き始めてからも、経営者と指導担当者たちがしっかり情報交換をし、指導担当者の負担が大きすぎないか、組織としてサポートすべき点はないかを確認しながら雇用を進めていく必要があります。
