
技能実習に代わる新制度「育成就労」の最大の目玉は転籍要件の緩和です。技能実習では原則3年間は職場変更(転籍)ができないため、使用者と技能実習生との間に過度の支配従属関係が生まれ、人権侵害や労働法令違反を助長する背景になっていると指摘されています。実は技能実習制度でも「やむを得ない事情がある場合」の転籍はできるのですが、制度が十分に周知されていないうえ、行政に転籍を認めてもらうことが難しいケースもたくさんありました。育成就労制度では「本人の意向による転籍」を新たに導入するとともに、従来からある「やむを得ない事情がある場合の転籍」の運用も大幅に改善することになりました。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
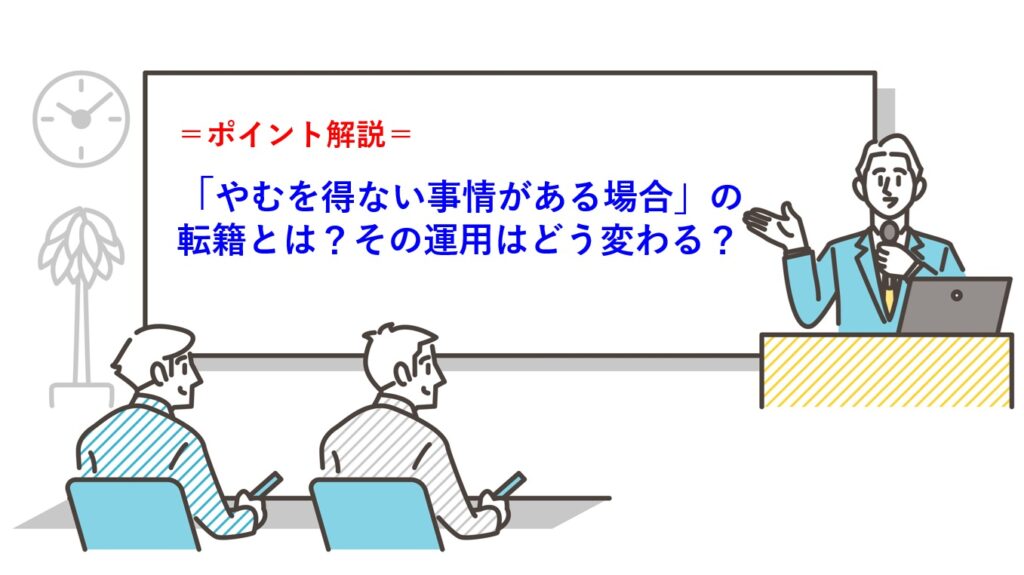
◎技能実習制度でも「やむを得ない事情がある場合」の転籍はできます。その手続きは本来、監理団体が外国人技能実習機構と連携しながら進めます。
◎しかし、人権侵害や労働法令違反等について監理団体に相談しても、責任ある対応をせず、技能実習生があきらめて失踪したり、民間の支援団体に助けを求めたりするケースが後を絶ちません。
◎今後は、労働条件の相違(事前説明と実態の不一致)を含め、「やむを得ない事情」に該当するケースの範囲を広げて明示していくことになったので、「やむを得ない事情」による転籍の運用は大きく改善されることが期待されます。
◎これまでは、外国人技能実習機構に転籍を認めてもらおうと思えば、人権侵害や法令違反等を実習生側が細かく証明する必要がありました。しかし、今後は、特に暴力やハラスメントなどの事案では、個別事情に応じて立証手段を簡素化するなど柔軟な対応が行われます。
◎今後は、「やむを得ない事情がある場合」の転籍がもっと周知されるので、監理団体が不適切事例に目をつぶることが難しくなります。このため、事業者が人権侵害や法令違反等を起こした場合、実習生や育成就労外国人がこの制度によって転籍するケースが増えそうです。
◎人件侵害や労働法令違反等によって「やむを得ない転籍者」を出した事業者は新規の外国人材募集が困難になる恐れがあります。その事業者の悪評がSNS等を通じて先輩外国人から後輩たちに伝えられるためです。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 不正や法令違反の背景となっている「転籍禁止」
- 技能実習制度でも転籍はできる-「やむを得ない転籍」
- 「やむを得ない事情がある場合」への対応はどうなっているか
- 新制度:「やむを得ない転籍」の対象を拡大・明確化
- 新制度:「やむを得ない事情」の立証を簡素化
- 転籍制度の周知徹底
- 人権侵害や法令違反で転籍者を出した事業者の不利益とは?
- まとめ
不正や法令違反の背景となっている「転籍禁止」

技能実習制度の目的は、技能・技術・知識を開発途上国等に移転するために、その国々の経済発展を担う「人づくり」に協力することです。この目的を達成するためには、技能を計画的・継続的に学ぶ必要があるという理由で、技能実習では、職場を変える「転籍」を原則3年間認めていません。
しかし、転籍の原則禁止によって使用者と技能実習生との間に過度の支配従属関係が生まれ、暴力・暴言・いじめといった人権侵害や労働法令違反を助長する背景・原因になっていると指摘されています。
その結果、実習生の失踪が多発したり、実習生の苦境がメディアによって周知されたりし、外国から「日本の技能実習は奴隷制度」と酷評されるに至りました。2022年11月に技能実習制度等の改革に向けた有識者会議が設置された際、政府には、このような国際批判への対処の必要や「このままでは日本に外国人労働者が来てくれなくなる」という危機感もありました。有識者会議は新制度「育成就労」で働く外国人の転籍要件を緩和する最終報告をまとめ、2024年に閣議決定を経て関連法案が成立しました。
技能実習制度でも転籍はできる-「やむを得ない転籍」

実は、技能実習制度でも「やむを得ない事情がある場合」の転籍はできます。人権侵害や労働法令違反等によってその職場で適切な技能実習を継続することが困難になった場合や、職場での人間関係の問題等で実習を継続できない場合は、別の職場に移ることができるのです。この手続きは本来、監理団体が外国人技能実習機構と連携しながら進めます。
しかし、そのような責任を果たさない監理団体も多いため、実習生が失踪せざるを得なくなったり、代わりに民間の支援団体が転籍をサポートしたりするケースも多数あります。
監理団体には監査業務があります。受け入れ事業者が機構に提出した「技能実習計画」の通りに実習が行われているか、技能実習法や労働基準法への違反はないかなどを、3カ月ごとに定期監査し、問題を見つけたら指導するとともに、大きな問題があれば臨時監査を行うこともあります。また、来日1年目の実習生(1号技能実習生)がいる事業者には毎月1回訪問し、実習生の様子や実習の実施状況を確認します。
監理団体は本来、このような監査・訪問を通じ、事業者を日常的に指導したり機構に報告したりしなければなりません。そして、「やむを得ない事情」につながりそうなトラブルや違反を察知した場合は、事業者を指導し、事業者と実習生の関係も調整し、それでも解決できない場合は、外国人技能実習機構と相談しながら転籍手続きを進めなければならないこともあります。しかし、その機能を果たせていない監理団体が多いのです。
「やむを得ない事情がある場合」への対応はどうなっているか

監理団体は本来、監査や訪問指導などで「やむを得ない事情」に該当する問題を察知した場合、事業者への指導や調整を行い、それでも問題が解決しなければ、転籍手続きを主導的に進めなければなりません。
しかし、知識・体制の不足から十分な監査や訪問指導を行っていない監理団体も多数あります。そのような監理団体は、仮に「やむを得ない事情」があっても把握できませんし、たとえ実習生から人権侵害や法令違反の疑いについて相談されても、十分な事実確認や指導・調整をしないことが多々あります。
これは「受け入れ事業者から今後も引き続き技能実習生の求人や監理業務を受注したい」とか「面倒を避けたい」といった思惑によるものですが、ひどい場合は、事業者への指導や転籍サポートをするどころか、逆に実習生を強制的に帰国させてしまうことさえあります。その場合、実習生は転籍制度や強制帰国禁止について知らされていないので、泣く泣く従ってしまいます。
このような目にあった技能実習生たちがSNSなどで被害について広く発信してきたことから、「職場で起きた問題を監理団体に相談しても解決しない」と最初からあきらめている実習生も多くいます。また、実習生がせっかく監理団体に相談したのに誠実に対応してもらえず、失望するケースもあります。こうして、「やむを得ない事情」を抱えた実習生がやむなく失踪するか、民間の支援団体に駆け込んで転籍をサポートしてもらう事例が後を絶ちません。
2023年6月現在、実習生は35万8159人いますが、前年の失踪者は9,006人に上りました。
新制度:「やむを得ない転籍」の対象を拡大・明確化

このような実態を踏まえ、育成就労制度では、本人の意向による転籍を新たに可能とするほか、「やむを得ない事情がある場合」の転籍の運用も改善されることになりました。
育成就労における「やむを得ない事情がある場合」の転籍について、2024年2月の閣議は「例えば労働条件について契約時の内容と実態の間で一定の相違がある場合を対象とすることを明示するなど、その範囲を拡大・明確化する」「例えば職場における暴力やハラスメント事案の確認等の手続を柔軟化する」と決定し、「やむを得ない転籍」の範囲が拡大・明確化され、手続きも柔軟化されることになりました。
監理団体関係者らによると、技能実習で最も多いトラブルは「来日前に聞いていた労働条件と実際の条件が違う」という事案(労働条件の相違)です。それは手取り給料や仕事内容に関するものが目立って多く、例えば「ビニルハウス内での仕事が大半だと聞いていたが、実際には屋外での農作業が中心だった」といったような事柄です。
しかし、これまでは何が「やむを得ない事情」なのか明確にされていなかったので、そのことが理由で転籍が認められるかどうかは外国人技能実習機構の採用にゆだねられてきました。今後は、労働条件の相違を含め「やむを得ない事情」に該当する事柄の範囲を広げ、明示していくことになったので、「やむを得ない事情」による転籍の運用は大きく改善されることが期待されます。
新制度:「やむを得ない事情」の立証を簡素化

これまでは、外国人技能実習機構に「やむを得ない事情がある場合」の転籍を認めてもらおうと思っても、人権侵害や法令違反等を技能実習生側が細かく証明する必要があり、なかなか認めてもらえないケースがありました。このため、有識者会議でも「外国人から労働条件の相違や法令違反などの申告があった場合、外国人側が過度の立証責任を負わされている」との意見がありました。今後は、特に職場での暴力やハラスメントなどの事案では、個別事情に応じて立証手段を簡素化するなど柔軟な対応が行われることになりました。
そして、この運用改善については、育成就労制度の導入を待たず、技能実習制度のもとでもできるだけ早期に実施することになりました。
立証手続きの改善に伴い、受け入れ事業者側が人権侵害や法令違反がなかったことについて説明を求められることも予想されます。例えば、外国人から労働条件の不一致に関する申告があった場合、もし、事業者が労働条件について外国人材の母国語で説明し本人署名を得た書類などを示すことができれば、不一致ではないことの証明になります。逆に、このような客観的な証拠がないと、今後は、外国人側の主張が従来よりも認められやすくなる可能性があります。

求人票に明記されていない残業代の平均額や仕事の細かい内容(労働条件)について、送出機関やブローカーが口頭でしか説明しないことや、受け入れ事業者が採用面接の際に口頭で説明するだけのことがあります。その際、送出機関やブローカーが応募者に正しく説明しない場合や、面接時に通訳者が十分に通訳しない場合も多く、外国人が来日してから「事前に聞いていた労働条件と違う」と感じるケースが後を絶ちません。
そこで、事業者が外国人に労働条件を書面(現地語併記)でも説明し、確認のために本人の署名ももらっておけば、労働条件について正しく理解させたことの証拠になります。逆に、このような客観的な証拠がないと、今後の運用では、外国人側の主張が認められやすくなる可能性があります。最近では、仕事内容に関する誤解をなくすため、仕事内容を動画で説明する事業者も増えています。
転籍制度の周知徹底

これまでは、技能実習生たちに転籍制度の存在や内容があまり知られていなかったため、有識者会議の最終報告では「転籍が認められる範囲やそのための手続きについて、関係者に対する周知を徹底する」と述べられています。
制度に関する知識が広まれば、転籍を検討すべき案件に対して監理団体が意図的に目をつぶることも難しくなります。このため、受け入れ事業者が人権侵害や法令違反等を起こすと、実習生や育成就労外国人が「やむを得ない事情がある場合」の転籍を求めるケースが増えていくことでしょう。
人権侵害や法令違反で転籍者を出した事業者の不利益とは?

人権侵害や労働法令違反によって「やむを得ない」転籍者を出した受け入れ事業者は、不正の内容がひどい場合、技能実習計画の認定取り消し処分等を受けてほかの実習生や育成就労外国人も失い、その後も一定期間、新たな実習生等の受け入れができなくなる事態も覚悟しなければなりません。
また、問題の多い事業者は、特定技能や技能実習・育成就労の求人を新たに出しても、外国人がだんだん応募しなくなるというリスクもあります。
受け入れ事業者が外国の人材会社(送出機関等)に新たな求人を依頼すると、求人票を見た技能実習候補者たちが先輩実習生たちにその事業者の評判をSNSなどで尋ねる場合があります。人権侵害や労働法令違反で転籍者を出した事業者の場合、先輩たちが事業者に関する否定的なコメントを多数紹介する可能性があり、その場合、求人への応募者が集まりにくくなってしまいます。
このため、事業者が現在雇用している技能実習生を大事にすることは、今後の応募者を確保する上でも大切です。
外国に人材を頼る動きは欧州や中東、台湾、韓国など日本以外の国々でも強まっており、国際的な人材獲得競争が激化している上、日本の賃金安や円安の問題もあり、日本が外国人材を今と同じように確保し続けることができるとは限りません。そのような中、先輩実習生たちから悪い評価を付けられた事業者が人材を安定的に確保し続けることは相当困難になっていくと予想されます。
まとめ

このページのまとめ
- 技能実習制度でも「やむを得ない事情がある場合」の転籍はできますが、監理団体が責任ある対応をせず、実習生があきらめて失踪したり民間の支援団体に助けを求めたりするケースが後を絶ちません。
- 今後は、「やむを得ない事情」に該当するケースの範囲を広げ、明示していくので、「やむを得ない事情」による転籍の運用は大きく改善されることが期待されます。
- これまで、「やむを得ない事情がある場合」の転籍を認めてもらうには、人権侵害や法令違反等を実習生側が細かく証明する必要がありましたが、今後は、立証手段が簡素化されます。
- 「やむを得ない事情」の立証の簡素化によって、事業者側にも違反等がないことの証明を求められる可能性があります。
- 人権侵害や労働法令違反によって「やむを得ない転籍者」を出した事業者は新規の外国人材募集が困難になる恐れがあります。その事業者の悪評がSNS等を通じて先輩外国人から後輩たちに伝えられるためです。
