
技能実習生になるためには日本語能力の要件(条件)はありませんが、育成就労制度では、就労開始までに日本語能力試験N5等に合格するか、育成開始後に日本語教育を受けなければならないことになりました。また、育成就労から特定技能1号になる際には、すべての場合でN4等への合格が求められ、特定技能2号になるにはN3等への合格が必要になります。育成就労や特定技能への日本語要件の導入・強化は受け入れ事業者にどのような影響をもたらすのでしょうか?事業者はどのような対策をすればよいのでしょうか?
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
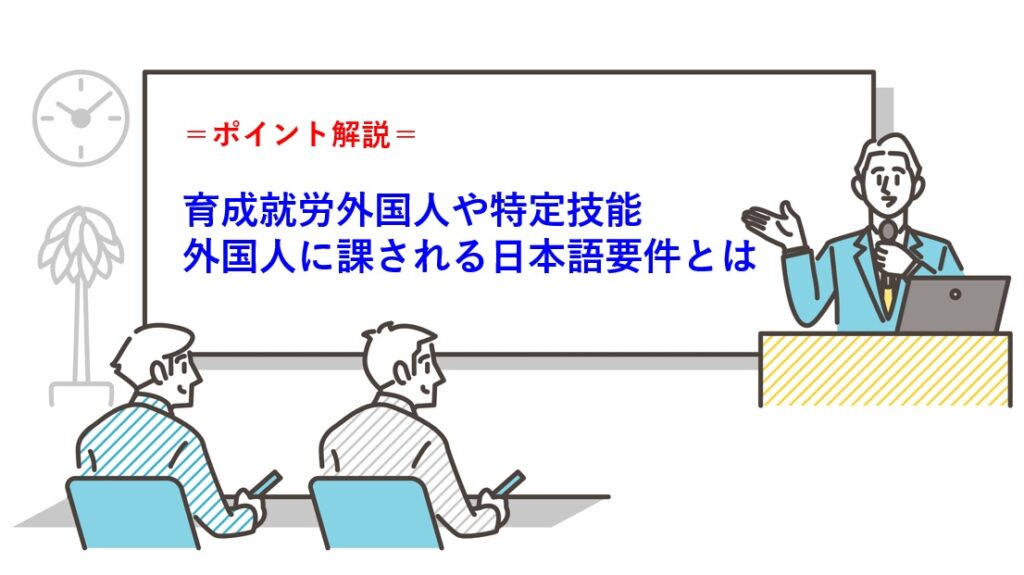
◎育成就労制度では、就労開始前に原則として日本語能力試験N5等への合格が求められるようになりますが、応募者が減る恐れもありますし、N5合格者を十分に送り出せない送出機関も多数あります。
◎そこで、当面は、試験合格の代わりに来日後に「相当講習」を受講させることで代替できます。ただし、それには費用や時間、学習管理などのコストがかかります。
◎N5等に合格してから来日した育成就労外国人を受け入れる方が、来日後に相当講習や日本語試験を受けさせるより楽です。日本語力の高い人材を安定的に送り込んでもらうには、日本語教育力の高い送出機関を見つけ、付き合いを深めることが大事です。
◎外国人材に十分な日本語力を確実に身につけてから来日してもらうには、来日前に追加の教育をしてもらうことも有効です。追加費用が必要ですが、基礎的な日本語会話ができる状態で来日した外国人材は自習・仕事・生活を通じて日本語力を上積みし、仕事でのやり取りも生活も楽になっていくケースが多いです。
◎外国人の日本語レベルを引き上げるには、来日前に引き上げるコスト(費用・時間・手間)の方が来日後に引き上げるコストより小さいです。
◎育成就労を修了した外国人が特定技能1号に移行するには、N4等への合格が必要になります。そのための学習サポートコストを軽減する意味でも、来日前に高い日本語力を身につけてもらう方が得策です。
◎特定技能外国人を海外から受け入れる場合、入国時にN4相当の試験合格が必要になりますが、来日前に追加教育を受けさせて会話力も併せ持つ人材を確保すると、大きな戦力になります。
◎育成就労制度で優良受け入れ機関に認定されるためには、外国人への日本語教育への取り組みが考慮されるようになります。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 新制度:就労開始前に日本語能力N5等
- 送出機関はN5の人材を十分に送り出せるのか
- 対策①:教育力の高い送出機関を確保する
- 対策②:来日前の追加教育が有効
- 新制度:特定技能1号移行時にN4が必要
- 日本語学習サポートが優良団体の認定要件に
- まとめ
新制度:就労開始前に日本語能力N5等

育成就労制度では、外国人が就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、来日後に相当する日本語講習を認定日本語教育機関等において受講することが要件となります。
また、育成就労外国人の技能修得状況等を評価するため、受け入れ機関は受け入れ後1年以内に技能検定試験基礎級等や日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)を外国人に受験させなければなりません。ただし、外国人がすでに試験に合格している場合は除きます。
① 育成就労開始時にN5相当
現行の技能実習制度では、日本語能力に関する要件はありません。技能実習生が来日してから1カ月間受ける入国後講習の中で日本語科目の講習を含めることが求められているのみです。
※ただし、介護職種については、最初に入国する時点で日本語能力試験N4等以上に合格していること 、技能実習2号(来日2~3年目)移行時には、N3等以上に合格しているか日本語学習プランを提出して継続的に日本語を学ぶ旨を誓約していることが要件となっています。
育成就労制度では、育成開始前に原則として日本語能力試験N5等以上への合格が求められるようになります。これは、日本語能力が技能修得にとって重要で、本人の権利保護や入国後の地域社会との共生のためにも必要という考え方から導入されました。
技能実習制度でのトラブルの原因として、使用者側の問題に加え、実習生の日本語能力不足も指摘されています。日本語をある程度理解できる状態で来日した技能実習生は、仕事に必要な意思疎通や生活に必要なコミュニケーションが成立するための日本語会話力を比較的早期に身に付けることができ、職場でのトラブルが少ない傾向があります。
② N5に達しない場合は来日後に相当講習
ただし、日本語能力について入国前に高いハードルを設けた場合、受け入れ分野によっては応募者が減ってしまう恐れがあります。
それに、諸外国の送出機関で日本語を教える教員の多くは元技能実習生で、N1合格者は非情に少なく、N2合格者も決して多くありません。筆者がベトナム、インドネシアの送出機関・数十社を調査したところ、送出機関の教員全体の6~7割がN3以下で、N4の教師もいました。このように外国における日本語教師の不足もあり、訪日までに生徒をN5に合格させる教育条件が広範に整っているわけではありません。
さらに、日本語能力試験が年に2回しか実施されないなど公的な日本語試験を受験できる機会が制限されていることも問題点として指摘されています。
そこで、当面は来日後に「相当講習」を受講することで代替できることになりました。日本語試験合格に代わり、相当レベル・時間の日本語教育を認定日本語教育機関等で受講することが要件となります。
※「認定日本語教育機関」は2025年度から設置される日本語学校で、設置者にさまざまな要件が求められます。そして、留学生相手の授業を担当できるのは新たな「日本語教員試験」に合格した「登録日本語教員」だけになります。
送出機関はN5の人材を十分に送り出せるのか

送出機関など外国の人材会社は「大半の生徒に来日までにN4相当の日本語力を身に付けさせる」といった説明をすることがよくあります。ところが、実際にその人材会社を訪問し、学習を始めて半年前後の生徒たちと会話をしてみると、初歩的な日本語会話も成立しない事例が多々あります。
これは、その送出機関等の規模とは関係ありません。規模が大きく日本の大手企業との取引も多い送出機関等であっても、生徒たちの日本語力が低い場合はよくあります。
送出機関等が「大半の生徒をN4相当で送り込む」と触れ込む場合、N4レベルの日本語教材を使った授業を受けさせるというだけで、必ずしもN4等の試験に合格させるわけではありません。
また、送出機関の教室で日本語試験を行う場合、生徒に類似問題を事前に解かせたり、カンニングを黙認したりなど、さまざまな不正が行われるケースもあります。さらに、カンニングや替え玉受験など不正な手段で合格証を入手する事例もあります。

それでも、N5(初歩的な日本語力)であれば合格は簡単だろうと考えがちですが、こうした試験には文法・読解・聴解・語彙などのカテゴリーがあり、「読解がどうしてもできない」とか「聴解(主にヒアリング)が苦手」といった生徒も多く、試験合格は結構難しいのです。特に、利潤だけを追求してこれまで十分な教育体制を整えてこなかった送出機関の場合、N5相当の合格者を多数育成するのは難しいようです。
こうした送出機関が多くの生徒をN5に合格させてから日本に送り込むには、教師の質を高めるとともに、意欲の高い生徒をたくさん確保するための一層の努力が求められます。しかし、その体制を整えるのは決して簡単なことではありません。
生徒の多くをN5まで育成してから日本に送り出せる送出機関を確保できない場合、外国人が来日してから「相当講習」を受けさせ、1年以内に日本語試験を受けさせなければなりません。これには費用や時間、学習進捗管理、受験に伴うコストが必要となります。
対策①:教育力の高い送出機関を確保する

来日後の外国人に認定日本語教育機関による相当講習を受けさせたり、1年以内に日本語試験を受けさせたりするには、費用負担や学習管理の手間がかかります。
そもそも、ある程度日本語ができるようになってから来日した外国人を受け入れるのと、日本語がほとんどできない状態でやって来た外国人を雇うのとでは、外国人本人にとっても受け入れ事業者にとっても大きな違いがあります。
| 簡単な会話ができる状態で来日 |
| 【本人】 ・来日後も自習・仕事・生活を通じて日本語力を上積みし、仕事でのやり取りも日本での生活もどんどん楽になっていくケースが多い。 ・職場や生活でのトラブルも少ない。 【受入事業者】 ・日本語学習をサポートするための費用や手間が最小限で済む。 |
| あいさつと定型の自己紹介しかできない状態で来日 |
| 【本人】 ・3年働いても日本語をほとんど覚えずに帰国する傾向。 ・来日後、仕事をしながら疲れた体で慣れない日本語学習を続け、成果を出すのはかなり大変。 ・日本語ができないので、職場や地域でのトラブルも多い傾向がある。 【受入事業者】 ・学習サポートのコスト(時間・費用)が結構かかる。 ・来日前に学習の習慣があまりついていないので、本人の学習意欲を保つためのさまざまな努力(学習管理)も必要。 |
受け入れ事業者にとっては、育成就労外国人をN5に合格させてから送り出してもらう方が、受け入れてから初めて本格的に学習させるより、はるかに楽です。ただし、それができる送出機関ばかりではないため、今のうちに良い送出機関を見つけ、付き合いを深めておくことが大切です。そのような送出機関を自力で見つけることができない場合は、そのような送出機関と取引をしている監理団体(新制度では監理支援機関)を見つけることが大切です。
対策②:来日前の追加教育が有効

来日前にN5に合格した外国人を雇用する方が受け入れ事業者にとっては助かります。それができる送出機関を見つけて付き合いを深めることが大切ですが、そのような送出機関でも、求人が増え送出人数が増えた場合、良い人材をいつも安定的に送り出すことができなくなる場合もあります。これはどの送出機関にも言えます。
そのような中、自社が採用した外国人材に十分な日本語力を確実に身につけてから来日してもらうには、送出機関に追加の来日前教育をしてもらうことも有効です。
送出機関は生徒に6カ月前後の日本語教育を施してから日本に送り出すことが多いですが、例えば、受け入れ事業者から送出機関に依頼して2~3カ月追加で教育してもらい、N5等の試験合格に加えN4相当の会話力も身につけてから送り出してもらうと、その人材を受け入れてから大変助かります。

この場合、受け入れ事業者が追加教育費を負担します。また、「少しでも早く日本に行きたいと」いう生徒が多いので、生徒に承諾してもらわなければなりません。場合によっては、追加教育期間の生活費も支援する必要があります。
このように少しコストはかかりますが、必要な日本語力を来日前に身につけた外国人材を確実に雇うことができれば、受け入れ事業者にとって大きなメリットがあります。それに、外国人も日本でキャリアを築いていくための良いスタートを切ることができます。
また、外国人の日本語レベルを引き上げたいのであれば、来日前に引き上げるコスト(費用・時間・手間)の方が来日後に引き上げるコストよりも小さく済みます。教育費は人材輩出国の方が安いですし、本人も訪日前なら学習だけに専念できます。一方、来日後は、教育費も高いうえ、平日の仕事後や休日に学習しなければならないので、本人もかなり大変です。
新制度:特定技能1号移行時にN4が必要

制度改正に伴い特定技能外国人になるための日本語要件は次のようになります。
・育成就労制度から特定技能1号への移行時:日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)への合格が必要。事業者が育成就労外国人に試験を受けさせなければならない。
※特定技能1号への移行に必要な試験(技能試験も含む)に不合格となった者については、同一の受け入れ事業者での就労を継続する場合に限り、再受験に向けて最長1年の在留継続が認められる。
・特定技能1号から特定技能2号への移行時:日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)への合格が必要。
・受け入れ対象分野ごとにより高い水準の試験への合格を要件とすることもできる。
① 特定技能1号に移行する際はN4(免除はなくなる)
育成就労を修了した外国人が特定技能1号に移行する際には、技能検定試験等への合格に加え、日本語能力試験N4等への合格が条件となります。
現行の技能実習制度では、技能実習2号を良好に修了した実習生が同じ業種で特定技能1号に移行する「技能実習ルート」では、日本語試験が免除されていますが、育成就労制度では、このような免除がなくなります。
育成就労外国人を特定技能1号に移行させて継続雇用しようとする場合、その外国人に入国後3年以内(1年延長可能)にN4に合格してもらわなければなりません。特定技能に必要な日本語力を身に付けるための学習サポートのコストを軽減する意味でも、来日前になるべく高い日本語力を身につけてもらう方が得策です。
なお、特定技能外国人を海外から受け入れる場合、技能実習の経験者ではなく、初めて来日する生徒を受け入れるケースも増えています。新制度では入国時にN4相当の日本語力が必要とされますが、入国前に日本語試験合格だけでなく、ある程度の会話力(試験のレベルと実際の会話力は別)も身につけてもらった方が、受け入れ側にとっては助かります。その場合も、受け入れ事業者が費用を負担して来日前に追加教育をしてもらう手法が有効です。
② 特定技能2号に移行する際はN3
特定技能1号から2号に移行する際、現在は、日本語要件はありませんが、新制度では日本語能力試験N3等への合格が義務付けられることになりました。
日本語学習サポートが優良団体の認定要件に

受け入れ事業者による育成就労外国人の日本語学習サポートについては、以下のようなことが決められました。
・日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の仕組みを活用して日本語教育の質の向上を図るとともに、受け入れ機関が日本語教育支援に積極的に取り組むためのインセンティブとなる優良な受け入れ機関の認定要件等を設ける。
・育成就労において必要となる日本語能力を測る試験について、A1相当からA2相当までの範囲内で設定される水準の試験を含む新たな試験の導入や、外国人の十分な受験機会を確保する方策を検討するとともに、母国における日本語学習支援として、日本語教材の開発、現地日本語教師の育成のための日本語専門家等の各国への派遣、日本語教材購入助成等の支援の実施等の取組を進める。
外国人労働者の日本語能力向上は、日常生活だけではなく、技能習得や自分の権利保護にも役立つという認識のもと、育成就労制度では、受け入れ事業者が外国人の日本語学習を積極的にサポートするよう、優良受け入れ機関として認定してもらうための要件に日本語教育への取り組みが含められることになりました。
また、日本語能力試験が年に2回しか開催されておらず受験機会が少ないなどと指摘されているため、日本語試験に関する改善策を検討するとともに、送出国での日本語教育力を高めるために、日本が良質な日本語教材や現地の日本語教師の育成支援に乗り出すことになりました。
まとめ

このページのまとめ
- 育成就労制度では、就労開始前に日本語能力試験N5等への合格が求められます。しかし、そのことで応募者が減る恐れがありますし、十分に対応できない送出機関も多数あります。
- そこで、当面は、試験合格の代わりに訪日後に「相当講習」を受講することで代替できます。ただし、それには費用や時間などがかかります。
- N5等に合格した人材を安定的に送り込んでもらうには、日本語教育力の高い送出機関を見つけ、付き合いを深めておくことが大事です。
- 外国人材に十分な日本語力を確実に身につけてから来日してもらうには、送出機関等に来日前に追加の教育をしてもらうことも有効です。
- 外国人の日本語レベルを引き上げるには、来日前に引き上げるコスト(費用、日数)の方が来日後に引き上げるコストより小さく済みます。
- 育成就労を修了した外国人が特定技能1号に移行する際には、日本語能力試験N4等への合格が必要になります。そのための学習サポートのコストを軽減する意味でも、来日前に高い日本語力を身につけてもらう方が得策です。
- 特定技能2号に移行する場合、今は日本語要件がありませんが、新制度ではN3等への合格が必要となります。
- 育成就労制度で優良受け入れ機関に認定されるためには、外国人への日本語教育の取り組みが考慮されるようになります。
