
労働基準法は「週40時間以内・1日8時間以内の労働時間(法定労働時間)」と「週1日以上の休日」を規定しており、原則として法定労働時間を超えて所定労働時間を設定することはできません。しかし、農業はその例外で、これらの規定の適用を除外されています。ただし、それ以外の労働関係法令はすべて適用されますし、技能実習生には労働時間関係の規定も適用されます。また、最近では、人材確保の観点から、実習生だけでなく特定技能外国人や日本人に対しても他産業並みの労働条件を設定する農業事業者も増えています。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
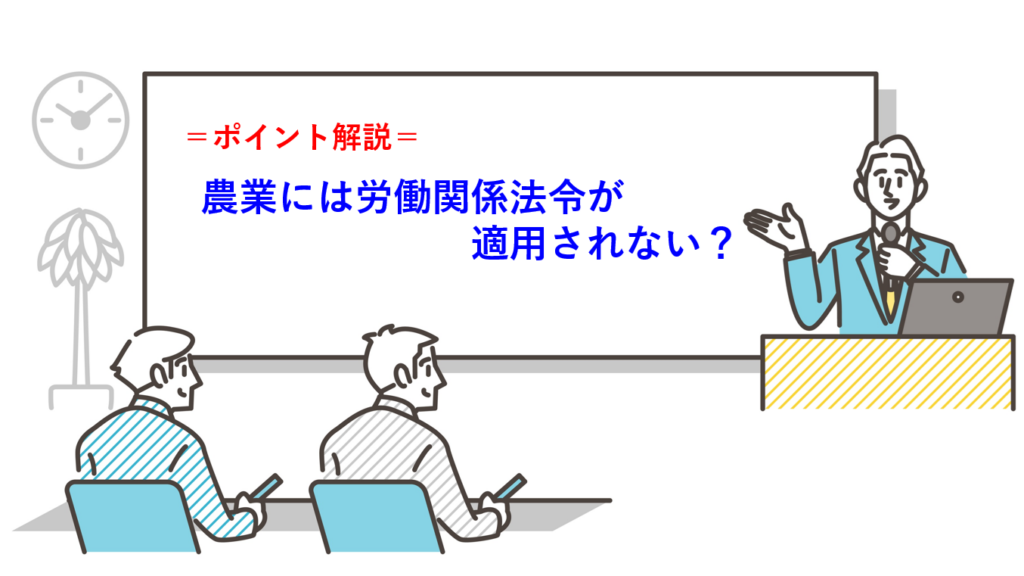
- 農業にも労働関係法令が適用される:農業にも労働関係の諸法令が適用されます。従業員を1人でも雇用すると、労働契約や最低賃金保証、年次有給休暇の付与、社会保険加入、健康診断などが必要になります。
- 労働時間関係の規定は適用除外:労働時間・休憩・休日に関する労働基本法上の規定は、農業に対しては適用されません。このため、農業では時間外労働や休日労働に対する割増賃金はありません。ただし、所定労働時間を超えて労働をさせた場合、超えた時間に対する(割増ではなく)通常の賃金は必要です。
- 深夜労働への割増賃金は必要:農業でも労働者に午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、割増賃金(深夜勤務手当)を支払わなければなりません。
- 技能実習生には労基法が全面適用:農業の技能実習生については、労働時間・休憩・休日も含めて労働基準法のすべての規定が適用されます。
- 農業労働者の保護:農業でも使用者が労働者の安全や健康に配慮する義務があります。
- 人材確保:人材確保の観点から、特定技能外国人や日本人についても所定労働時間や休憩・休日を他産業に近づけ、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金を支払う農業事業者も増えています。外国人材については獲得競争の一層の激化が予想され、労働条件の整備が不可欠です。
◆このページの内容
農業に適用されないのは労基法の一部だけ

農業にも労働関係法令が適用される
「農業には労働関係法令が適用されない」と勘違いされがちですが、農業であっても従業員を1人でも雇用すれば、労働に関するさまざまな法律が適用されます。例えば、下記のような法律がすべて適用されます。
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 労働契約法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 育児介護休業法
- 男女雇用機会均等法
これらは正社員にもアルバイト・パートにも適用され、事業形態が個人でも適用されます。このため、例えば、賃金は法定の最低賃金を下回ってはいけませんし、常時雇用する労働者については定期的に健康診断を受けさせなければなりません。
◆農業にも適用されるさまざまな労働法令の例
| 労働契約について 〈労基法15条〉 |
| 労働者を雇用する場合は、労働契約を結ぶことが必要。使用者は契約締結の際、労働者に賃金や労働時間等の労働条件を明示する。 |
| 最低賃金の保証等について 〈最低賃金法等〉 |
| 最低賃金制度は農業従事者にも適用される。 |
| 年次有給休暇について 〈労基法39条〉 |
| 6カ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(パート等も含む)には、年次有給休暇を与えなければならない。 |
| 社会保険について 〈労基法32条、34~37条〉 |
| ・労働者を雇用する場合は、原則として労働保険(労災保険、雇用保険)に入らなければならない。 法人事業者の場合、社会保険(医療保険、年金保険)も強制適用される。 |
労働時間関係の規定は適用除外
ただし、労働基準法41条で、農業や畜産業、養蚕業、水産業など特定の事業に従事する労働者については労働時間・休憩・休日に関する同法の規定を適用しないと定められています。
適用が除外されるのは例えば次の規定です。
- 労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)
- 休憩(労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上の休憩)
- 休日(週1日以上または4週間で4日以上)
農業は天候に大きく左右されるので、労働基準法の「1日8時間」「1週40時間」「週休1日以上」といった規定を適用しにくい時期があります。また、「閑散期や天気の悪い日に十分な休みを取れる」とか「特に休憩時間を設けなくても、いつでも自由に休憩を取れる」とも考えられています。これらが農業に労働時間関係の法令の適用が除外されている理由です。
ただし、適用が除外されているのは労働時間・休憩・休日に関する規定だけであり、労基法のほかの規定はすべて適用されます。例えば、従業員から年次有給休暇の申請があれば、応じなければなりません。
労働時間等に関する他産業との違いと注意点

それでは、労働時間等に関する規定について農業と他産業との違いをくわしく見ていきましょう。
労働時間
労働基準法32条で労働時間について次のような定めがあります。
- 休憩時間を除いて週40時間以内
- 休憩時間を除いて1日8時間以内
これらを「法定労働時間」と言います。他産業では原則として法定労働時間を超えて所定労働時間(1日の定時の労働時間)を設定することはできません。
しかし、農業では、法定労働時間を超えて所定労働時間を設定することができます。例えば、就業規則で「始業時刻6時、終業時刻17時、休憩2時間」と定め、1日の所定労働時間を9時間とすることは他産業ではできませんが、農業では可能です。
また、他産業では、労働者に法定労働時間を超えて働かせたり法定休日に労働をさせたりする場合、従業員の過半数の代表者と時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届けなければなりません。しかし、農業では36協定を締結する義務はありません。
休憩・休日
労働基準法34条と35条は休憩と休日に関し次のように定めています。
- 休憩:労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与える。
- 休日:週1日以上または(例外として)4週間に4日以上の休日を与える。
しかし、農業にはこれらの規定が適用されませんので、就業規則に固定の休憩時間を記載できない場合、休憩時間の決定方法を記載するだけでかまいません。「休日」についても就業規則に具体的な曜日を記載せず、「休日は1週間に1回以上与える。具体的には、シフト表によって個人ごとに定める」といった記載でもかまいません。
ただし、事業主には、従業員に対する「安全配慮義務」があります(労働契約法5条)。このため、休日や休憩時間が不十分で、過労死や過労疾患、けがなどの労働災害が生じた場合、事業主には損害賠償責任が生じることもあります。
農業法人等が加工や直売も行っている場合

同じ場所で農業生産以外に加工や直売等も行っている場合、何を「主たる業態」とするかについて、業態ごとの売上高や従事者数等をもとに決定します。
各部門で管理者と従事者が明確に区分されている場合は、生産、加工、販売をそれぞれ独立した事業場として取り扱います。その場合、農業生産現場では労働時間等の規定の適用が除外されますが、加工や販売を行っている事業場には労働基準法のすべての規定が適用されます。
休日や時間外の割増賃金は不要(通常賃金は必要)
他産業では、労働基準法37条によって、法定労働時間を超えて労働させた場合は通常の賃金の25%増以上の割増賃金、法定休日に労働させた場合は通常の賃金の35%増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、農業従事者には時間外労働や休日労働に対する割増賃金はありません。ただし、所定労働時間を超えて労働をさせた場合、超えた時間に対する(割増ではなく)通常賃金の支払いは必要です。
深夜労働への割増賃金は必要
一般に労働者に午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間の労働については、通常の賃金の25%増以上の割増賃金(深夜勤務手当)を支払わなければなりません(労働基準法37条)。農業についてもこの規定は適用され、深夜労働への割増賃金は支払わなければなりません。
技能実習には労基法のすべてが適用される

技能実習生には労基法が全面適用
労働基準法41条によって農業には労働時間等に関する規定の適用が除外されていますが、農業の技能実習生については、農林水産省の通達(2000年3月)で「他産業並みの労働環境等を確保するために、基本的に労働基準法の規定を準拠する」とされており、「労働時間、休憩、休日」に関する労働基準法の規定も適用されます。
農水省通達
技能実習生の労働条件に関して農林水産省が2020年に示した「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」という通達の概要を紹介します。この通達には労働時間関係の内容と社会保険、労働保険に関する記載がありますが、ここでは労働時間関係だけを取り上げます。
〈通達の要点〉
農業については、労働関係諸法令において様々な例外があることから、技能実習生の受け入れ機関である農家・農業法人・農協等(=農家等)を統一的に指導していくことが必要であり、当省の考え方を整理した。
1人でも労働者を使用していれば労働基準法の適用を受けるが、農業の場合、気候や天候に大きな影響を受けるため、労働基準法の労働時間・休憩・休日等に関する規定については適用除外とされている(ただし、深夜割増賃金や年次有給休暇に関する規定は適用される)。
しかし、農業の場合も労働生産性の向上等のために、適切な労働時間管理を行い、他産業並みの労働環境等を目指していくことが必要となっている。このため、技能実習制度では、労働時間関係についても基本的に労働基準法の規定に準拠するものとする。
農業の技能実習生に関する労働時間等の規定
この通達によって、農業の技能実習生に関する労働時間等の規定は一般の労働者と同じく下記のようになっています。
| 労働(技能実習)時間 〈労基法32条〉 |
| 所定労働時間を法定労働時間(1日8時間以内、週40時間以内)の枠内で設定 |
| 休憩・休日 〈労基法34・35条〉 |
| ・休憩は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上 ・休日は原則として週1日以上か4週間で4日以上 |
| 時間外・休日・深夜労働への割増賃金 〈労基法37条〉 |
| ・時間外労働:所定労働時間を超えて労働させた場合は通常の賃金の25%増以上の割増賃金 ・休日出勤:法定休日に労働させた場合は通常の賃金の35%増以上の割増賃金 |
労基署による監督指導
全国の労働基準監督機関が2021年、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習受け入れ事業者に対して9,036件の監督指導を行った結果、72.6%に当たる6,556件で法令違反が認められました(技能実習生以外の労働者に関する違反も含む)。
このうち農業では275事業者に監督指導が行われ、76%にあたる209事業者に法令違反がありました。内容は賃金不払い79事業者(29%)、安全基準違反39事業者(14%)、労働条件の明示違反34事業者(12%)などでした。
農業労働者の保護や人材確保に向けて

① 農業労働者の保護
農業では、労働時間関係は労働基準法の適用除外となっていますが、その場合でも使用者に安全配慮義務はあり、労働者の健康や安全に配慮する必要があります。
過労がもとで労働者が死亡したり病気になったりした場合、あるいは作業中にけがをした場合、使用者が彼らの健康や安全に対する配慮を欠いていたと認められれば、行政による労災保険の適用とは別に、事業主や管理者に損害賠償責任が発生することがあります。
そこで、日ごろから労働者の安全管理に配慮することが必要です。
また、農繁期に所定労働時間を長く設定し、農閑期に所定労働時間を短くすることで、労働時間や休暇のバランスを取ることも可能です(変形労働時間制)。
変形労働制の内容と活用例
② 労働者確保
農業従事者は減少傾向にあります。そこで、人材確保の観点から、法定労働時間を基準に所定労働時間を設定し、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金も支払う農業事業者も増えています。他産業を下回る労働条件で労働者を十分に確保することは難しいからです。
農業の特定技能外国人についても、法律的には技能実習生と違って労基法の労働時間等の規定を適用しなくてもよいのですが、人材確保のために他産業並みの条件を設定する事業者も多いです。同じ職場で技能実習から特定技能に移行させたい場合、労働条件を下げるわけにはいきませんし、外部から特定技能外国人を新たに雇う場合も、他社や他産業との獲得競争があるためです。
今後は外国人材の獲得を巡る競争がさらに激化していくことが予想され、外国人材を安定的に確保するためにも労働条件の整備は不可欠と言えます。
また、加工や直販を行う農業事業者が増えており、全社一律の労働条件を提供する必要があるとか、技能実習生を雇う事業者が増え、同じような労働条件を他の従業員にも提供する必要があるといった要因も、こうした傾向を加速させています。
まとめ

このページのまとめ
◎「農業には労働法令が適用されない」と勘違いされがちですが、農業であっても従業員を1人でも雇用すれば、労働に関するさまざまな法律が適用されます。このため、従業員を雇うと、労働契約や最低賃金保証、年次有給休暇、社会保険、健康診断などが必要となります。
◎農業では、労働時間・休憩・休日に関する労基法上の規定は適用が除外されます。したがって、農業では時間外労働や休日勤務に対する割増賃金はありません。ただし、所定労働時間を超えた労働時間に対する通常の賃金は必要です。
◎農業でも、従業員に午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の25%増以上の割増賃金(深夜勤務手当)を支払わなければなりません。
◎農業の技能実習生については、労働基準法のすべての規定が適用されます。
◎農業でも使用者が労働者の安全や健康に配慮する必要があります。
◎人材確保のため、特定技能外国人や日本人に対しても労働条件を他産業並みに設定して時間外労働や休日出勤に対する割増賃金を支払う農業事業者が増えています。
