
この記事では、求人の際の日本語条件に関するさまざまな実情を取り上げます。送出機関等を選べば、日本語を数カ月勉強した候補者を面接できる▽送出機関等が説明する「N4レベル」の人材と「N4合格者」とでは日本語力がまったく違う▽「N4合格者」の中でも会話力の差が激しい▽日本語試験のレベルと会話力は違う▽国籍を分散させることのメリット――などを紹介します。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
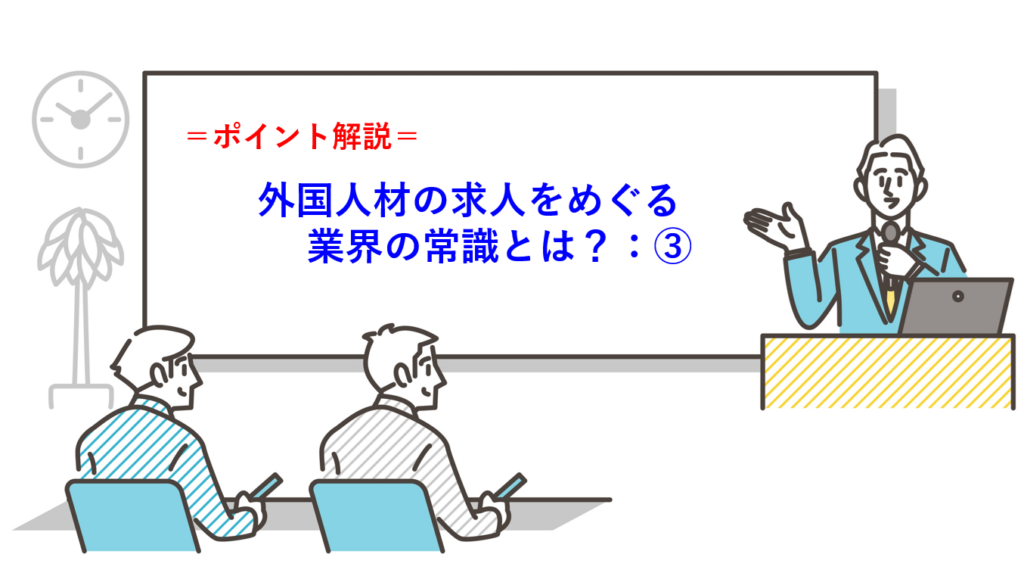
・日本語学習期間の長い候補者をリクエスト:日本語を4、5カ月以上学習した候補者を面接できれば、その時点での日本語力が分かり、課題に取り組む力や基礎能力、今後のポテンシャルを評価できます。そのような面接を設定してくれる送出機関等を探すのは難しいですが、監理団体や登録支援機関によってはそれが可能です。
・送出機関の「N4レベル」の意味:海外の人材会社(送出機関等)には、「数カ月で日本語能力試験N4相当のレベルにして送り出す」と説明する会社が多数あります。しかし、実際には、教材のN4レベルに該当する部分(の一部)を授業で1度教えるというだけで、「N4合格」のレベルにはほど遠いです。
・日本語力が高い外国人材のさまざまな価値:日本語力はさまざまな資質の指標として役立ちます。例えば、計画的・継続的に課題に取り組む力や基礎能力を持っていることの証明になります。
・日本語試験のレベルを高く設定しすぎない:日本語試験のレベルと会話力は違います。試験合格を優先すると、会話力やコミュニケーション力の高い人材を十分に採用できない場合があります。
・日本語力向上のために国籍を分散させる:外国人材の国籍を複数にすると、職場の共通言語が日本語となり、外国人材全体の日本語力アップにつながります。その際、国籍を変えながら採用するとさらに効果的です。
・外国人コミュニティのバランス:雇用する外国人材の国籍をバランス良く分散させれば、職場の一つの外国人コミュニティに問題が生じても、外国人材全体への指揮命令が難しくなるという事態は避けられますし、トラブルにも落ち着いて対応できます。
・国ごとの状況変化に備えたリスク分散:外国人材の供給を一つの国に頼ってしまうと、その国から日本への送り出し状況が変化したときに大きな打撃を受けます。リスクヘッジの観点からも国籍を分けて人材獲得を進めることが有効です。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 日本語学習期間の長い候補者をリクエスト
- 日本語力が高い外国人材のさまざまな価値
- 日本語試験のレベルを高く設定しすぎない
- 日本語力向上のために国籍を分散させる
- 外国人コミュニティのバランス
- 国ごとの状況変化に備えたリスク分散
- まとめ
[①の内容]
- 日本はもはや「夢の国」ではありません
- 相場を意識して給与などを設定する
- 送出機関等から優先順位を下げられないように
- 給与相場に関する業界情報の例
- 求人票に平均的な残業代を記載する
- 外国人材に残業を割り当てる配慮
- 外国人材への手当・寮費・ボーナス
- 「足がかり就職」とは?
[②の内容]
日本語学習期間の長い候補者をリクエスト

日本語学習期間の長い生徒をリクエスト
特定技能や技能実習の人材を海外から受け入れる場合、日本語をすでに4、5カ月以上学習した候補者を面接できれば、受け入れ事業者は大変助かります。その時点での候補者の日本語力が分かり、課題に取り組む力や基礎能力、今後のポテンシャルなどを評価できるからです。
ただし、日本語を数カ月間勉強した人を面接に出してくれる送出機関はどんどん減っています。2025年現在、インドネシアではそのような送出機関は以前よりずっと減りましたし、ベトナムではほとんどなくなりました。
日本語を4、5カ月以上学習した候補者に採用面接を行いたい場合、海外の人材会社を幅広く知っている情報通の登録支援機関や監理団体などを見つけて相談してください。
学習歴4、5カ月以上の応募者を集めてもらうことが難しい場合でも、学習歴2カ月前後の応募者であれば、比較的簡単に集められます。その方が、日本語学習経験ゼロの応募者よりはさまざまな資質を判定しやすいと言えます。
日本語試験と会話力は別
1号特定技能外国人を海外から採用する場合、在留資格の要件としてN4相当の日本語試験(JLPTかJFT-Basic)への合格が必要なので、海外の人材会社が教育して試験には合格させますが、日本語会話はほとんどできない状態で来日する人も多いです。
本来N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルとなっていますが、試験に特化した学習を行い、会話練習をあまりしないと、「聴く」「話す」が上達しないからです。
この場合、基礎学力はありますので、追加の教育費を支払うなどして会話練習を2、3カ月間集中的に行えば、簡単な日常会話ができる状態になってから来日することができます。
また、海外の人材会社(送出機関等)によっては、来日までに8カ月以上学習させるケースもあります。その場合、N4合格の有無にかかわらず、ある程度の会話ができる人材も多いです。
送出機関の「N4レベル」の意味
特定技能外国人や技能実習生を送り出す海外の人材会社(送出機関等)には、「数カ月で日本語能力試験(JLPT)N4相当のレベルにして日本に送り出します」と説明する会社がよくあります。
特定技能の場合は試験合格が必要なので、送出機関等は候補者が試験に合格できるまで教育します。しかし、試験合格の要件がない技能実習では、送出機関等はそこまでやりません。その場合、彼らが説明する「N4レベル」は「N4合格」のレベルとはまったく違います。
その場合の「N4レベル」とは、日本語学習教材のN4レベルに該当する部分(の一部)を授業で1度教えるというだけで、多くの場合、N4相当の日本語試験に合格する実力とはほど遠いです。
日本語力が高い外国人材のさまざまな価値

外国人材の資質は日本語力だけではありませんが、特定技能や技能実習の面接の場合、日本語力はさまざまな資質の指標として役立ちます。例えば、その日本語力を一定期間内に身に付けるために本人が計画的・継続的に努力を続けたことや、基礎能力を持っていることの証明になります。
また、技能実習生などのトラブルの多くはコミュニケーションの難しさによる相互のストレスに起因します。例えば、日本語での簡単な指示が伝わらず、日本人の上司・同僚が声を荒げたり暴力を振るったりするケースがよくあります。
日本語で簡単なやり取りすらできないと、指示する日本人も受ける外国人材も大きなストレスがかかるほか、互いにコミュニケーションがおっくうになります。コミュニケーションのないところに相互理解は生まれず、その職場での「共生」は困難です。
その場合、外国人材は孤立感を深め、他に条件の良い職場があれば、簡単に転職してしまいます。あるいは、予定より早く母国に帰る人もいます。
日本語試験のレベルを高く設定しすぎない

技人国(技術・人文知識・国際業務)や一部の特定技能の求人で、応募者にN2以上の日本語試験合格を求めるケースがよくあります。
しかし、日本語試験のレベルと会話力は違います。各種の日本語試験には漢字や読解などの試験問題が多いため、「会話のレベルは高いのに読み書きはだめ」という人は高得点が取れません。
もし、読み書きより会話力が求められる職種の人材採用で、日本語試験の合格レベルを優先しすぎると、会話力やコミュニケーション力の高い人材を十分に残せない可能性があります。
ある飲食チェーンは、各店で接客を担当する外国人材を多数募集する際に、以前はN2相当以上の合格を採用条件にしていたので、面接に進む応募者の中に会話力やコミュニケーション力の高い人材が十分に残っていませんでした。
そこで、日本語試験の要件をN4相当まで引き下げ、その代わり、採用過程でさまざまな方法で会話力やコミュニケーション力を確認するようにしたところ、現場で即戦力となる外国人材を十分に確保できるようになりました。
日本語力向上のために国籍を分散させる

特定技能外国人や技能実習生といった外国人材の雇用人数がある程度増えてくると、その国籍を分散させることも検討しなければなりません。
特定技能や技能実習で一つの国籍だけで外国人材を増やしていった場合、日本語ができるリーダー格の人材に他の外国人材が頼り過ぎてしまい、日本語の学習・練習をしなくなってしまいます。
その場合、もし、そのリーダーがいなくなったら、職場の業務効率が大きく下がります。また、リーダー以外は日本語が上達しないので、本人たちの将来のキャリアも制限されてしまいます。
そこで、外国人材の国籍を複数にすると、職場の外国人材の間で日本語が共通言語となり、外国人材全体の日本語力アップにつながります。
その際、例えば、今回ベトナム人を入れたら次はインドネシア人というように、国籍を変えながら採用していくと一層効果的です。
外国人コミュニティのバランス

外国人材は彼らのコミュニティを職場内で形成し、意見・情報を交換し合います。その中のリーダー格が会社に不満を持つと、それ以外の外国人も影響され、そのグループ全体が会社に不満を持つことがあります。
会社としては、自社の理念・方針と相性の合うリーダー外国人材を採用・育成することが大事です。しかし、それが上手くいかず、かつ職場に外国人コミュニティが一つしかない場合、リーダーが会社や上司に反発すると、コミュニティ全体がリーダーに同調して不満・反発が蔓延し、職場運営に支障が出る場合もあります。
その場合、リーダー格の人材が離職し、それにつられてほかの外国人材も何人か一緒に辞めるという事態も想定しなければなりません。特に特定技能外国人の場合は、転職あっせんブローカーが暗躍しており、ブローカーによる転職あっせんでまずリーダーが辞め、その後に元の職場仲間を引っ張ることはよくあります。それによって手数料ももらえるからです。
一つの国籍の人材だけを集中的に雇用するのではなく、国籍をバランス良く分散させれば、職場内の外国人コミュニティも複数になります。そうなれば、一つのコミュニティに問題が生じても、外国人材全体への指揮命令が難しくなるという事態や大量離職は避けられますし、トラブルにも落ちついて対応できます。
国ごとの状況変化に備えたリスク分散

以前、ベトナムで日本からの求人に応募者を集めることは簡単でした。しかし、ベトナムから日本に人材輩出を続けてきた複数の送出機関によると、2025年現在、日本に行きたい人材を集めることは以前と比べて非常に困難になっており、求人を受けても対応できないことがあるそうです。
一方で、台湾や韓国からの求人はベトナム人に人気が高く、応募者集めも好調です。また、欧州に送り出す留学生(後に現地で就職)への応募も増えており、「日本の求人だけが一人負けの状況」とのことです。
また、ミャンマーについては、同国政府が2025年3月、日本への送り出し条件を規制する発令を出し、今後の安定的な人材供給に暗雲が立ちこめています。
外国人材の供給を一つの国に頼ってしまうと、その国から日本への送り出し状況が変化したときに大きな打撃を受けてしまいます。リスクヘッジの観点からも、国籍を分けて人材獲得を進めることが有効です。
まとめ

このページのまとめ
◎日本語を4、5カ月以上学習した候補者を面接できれば、その時点での日本語力が分かり、課題に取り組む力や基礎能力、今後のポテンシャルなどを評価することができます。そのような面接を設定してくれる送出機関等を探すのは難しいですが、監理団体や登録支援機関によっては可能です。
◎海外の人材会社(送出機関等)には、「数カ月で日本語能力試験N4相当のレベルにして送り出す」と説明する会社が多数あります。しかし、実際は、教材のN4レベルに該当する部分(の一部)を授業で1度教えるというだけで、「N4合格レベル」にはほど遠いです。
◎日本語力はさまざまな資質の指標として役立ちます。例えば、計画的・継続的に課題に取り組む力や基礎能力を持っていることの証明になります。
◎日本語試験のレベルと会話力は違います。試験レベルを優先しすぎると、会話力やコミュニケーション力の高い人材を十分に採用できない場合があります。
◎外国人材の国籍を複数にすると、職場の共通言語が日本語となり、外国人材全体の日本語力アップにつながります。
◎外国人材の国籍をバランス良く分散させれば、職場の一つの外国人コミュニティに問題が生じても、外国人材全体への指揮命令が難しくなるという事態は避けられます。
◎外国人材の供給を一つの国に頼ってしまうと、その国から日本への送り出し状況が変化したときに大きな打撃を受けます。
