
東アジアの海外就労先として韓国、台湾の人気が上昇しています。韓国は日本よりも高い賃金、台湾は入国までの手続きの簡便さなどが魅力で、いずれも日本以上に少子化が進み、外国人材の受け入れに以前より力を入れています。一方、日本では、外国人材が入国・就労するまでの期間が長く、「選ばれる国」になることを妨げる要因の一つになっています。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
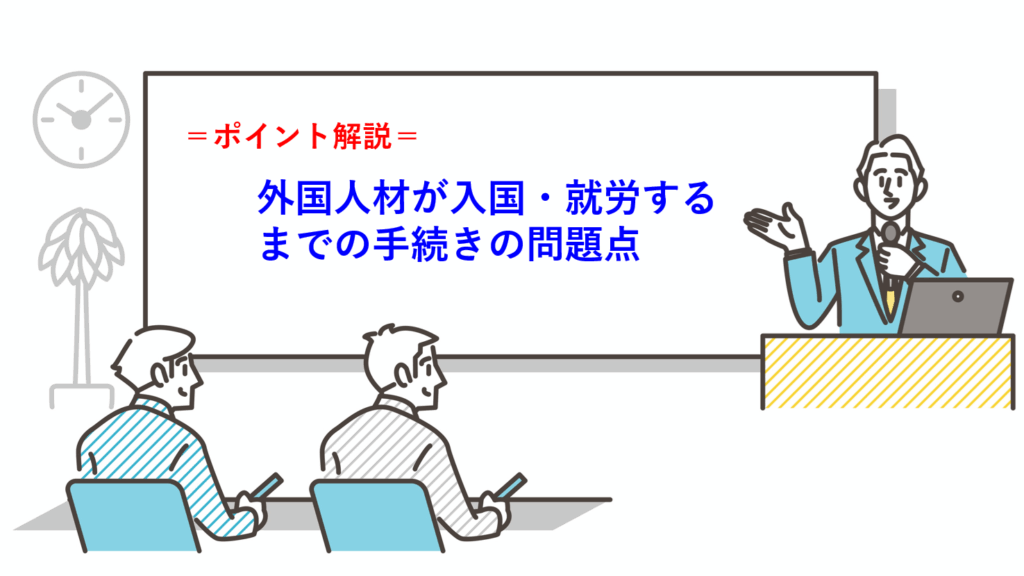
- 特定技能外国人の受け入れ枠拡大:特定技能外国人の受け入れ見込み数(上限数)は、2019年度からの5年間では34万5150人でしたが、2024年度からの5年間では82万人に増えました。ただし、受け入れ枠を拡大したからといって、無条件で外国人が日本に来てくれるわけではありません。
- 人材獲得競争におけるライバル国の優位:ベトナムで日本人気が下がり、2022年に海外就労先1位が日本(39・3%)から台湾(41・5%)に移りました。また、日本より賃金の高い韓国が外国人材の受け入れ枠を拡大し、韓国を選ぶベトナム人も増えています。ベトナム以外の国々にとっても、海外就労先として日本は選択肢の一つに過ぎず、特別な存在ではありません。
- 韓国の受け入れ枠拡大:2022年時点で日本の技能実習生の月給が平均21万2000円なのに対し韓国の低熟練労働者(製造業)は27万1000円です。その韓国で外国人の単純労働者の受け入れ枠を大幅に増やし、受け入れ産業分野も広げています。
- 台湾やシンガポールで働く際の手続き:台湾では、順調に進めば、外国人材は採用面接合格から1、2カ月後に働き始めることができます。シンガポールの就労ビザは、写真撮影と指紋採取以外はすべてオンラインででき、提出書類も比較的少なく、審査期間も短いのが特徴です。
- 外国人材が日本で働き始めるための手続きと期間:特定技能外国人を海外から新規に受け入れる場合、書類作成と入管審査で計3、4カ月かかることが多く、その後、ビザ発給までに2~4週間かかります。技能実習では、面接から入国まで約半年かかり、その後、約1カ月間の入国後講習を経て職場に配属します。技能実習計画の認定申請でOTITに出す書類も膨大です。
- 外国人材獲得の障壁になっている日本の受け入れ手続き:海外から新規で日本に就労する場合、特定技能では採用面接から約4カ月、技能実習では約半年かかります。その間、外国人材は収入がないうえ、送出機関などに手数料や教育費を払わなければなりません。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 特定技能外国人の受け入れ枠拡大
- 人材獲得競争におけるライバル国の優位
- 外国人材が日本のライバル諸国で働く際の制度や手続き
- 外国人材が日本で働き始めるための手続きと期間
- 外国人材獲得の障壁になっている日本の受け入れ手続き
- まとめ
特定技能外国人の受け入れ枠拡大

日本で少子高齢化が進む中、外国人材への依存が強まっています。2019年に特定技能制度が発足したときは「飲食料品製造業」や「製造」など12分野で受け入れが認められていましたが、2024年に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の追加が決まったうえ、「物流倉庫の管理」、「廃棄物処理」、「リネン製品の供給」の3分野の追加も検討されており、2025年末の閣議決定が見込まれています。
特定技能外国人が増えすぎて日本人の雇用に悪影響を及ぼすことがないよう、産業分野別の受け入れ見込み数(上限数)を5年単位で設定しており、2019年度からの5年間では34万5150人でしたが、2024年度から5年間では倍以上の82万人に設定されました。
ただし、受け入れ枠を拡大したからといって、無条件で特定技能外国人が日本に来てくれるわけではありません。移住労働者(外国に移り住んで働く人材)が海外就労先を選ぶ際、日本の人気は以前と比べて大幅に下がっています。ところが、移住労働者の国際的な獲得競争は激化しています。
このため、日本が今後、必要な外国人材を十分に確保していくには、国や地方自治体、産業界、受け入れ事業者の各レベルで外国人材の受け入れ体制を改善していかなければなりません。この記事では、その中で国の制度に関する問題点について考えます。
人材獲得競争におけるライバル国の優位

日本の賃金が長年横ばいで推移する間にアジア・東南アジアの人材送出諸国の賃金は年々上昇し、日本との賃金格差は大幅に縮小しました。さらに円安の進行もあり、昨今の日本の賃金では、外国人材を十分に引きつけることが難しくなりました。
このため、2010年代後半に日本への人材輩出が急増し、海外就労先の一番が日本だったベトナムでも日本人気が下がり、2022年に海外就労先1位が日本(39・3%)から台湾(41・5%)に移りました。また、日本より賃金の高い韓国が外国人労働者の受け入れを拡大したことによって、韓国を選ぶベトナム人も増えています。
ベトナム以外の国々でも海外就労先としての日本の受け入れシェアはもともと低いうえ、シェアを増やせる大きな要素が今のところありません。
※以下、三菱UFJリサーチ&コンサリティングまとめ
インドネシアからの海外就労先(2023年):台湾・マレーシア・香港で計80%。日本は4%。
ネパールからの海外就労先(2021年):サウジアラビア、カタール、UAE、マレーシア、クェートの順に多く、この6カ国で90%。日本は1%。
フィリピンからの海外就労先(2022年):中東諸国や欧米が多く、日本の受け入れシェアは3%。
ミャンマーからの海外就労先(2022年):タイ(57%)、マレーシア(20%)、シンガポール(10%)がトップ3。日本は4番目で8%。また、2025年になってミャンマー政府が日本への人材輩出に規制を設け、先行きが不透明。
このように、アジア・東南アジア諸国からの海外就労先として日本は選択肢の一つに過ぎず、決して特別な存在ではありません。そのうえ、東アジアでは海外就労先として台湾・韓国の優位性が増し、日本の地位が低下傾向にあります。
外国人材が日本のライバル諸国で働く際の制度や手続き

三菱UFJリサーチ&コンサルティングによると、2022年時点で日本の技能実習生の月給が平均21万2000円なのに対し韓国の低熟練労働者(製造業)は27万1000円です。その韓国で入管制度を改正して外国人材の受け入れを広げています。また、台湾は、採用面接で合格してから入国まで1カ月あまりという手軽さが魅力で、移住労働者の人気を集めています。
外国人材の受け入れ拡大に向けた韓国の制度改革
韓国が外国人の単純労働者を受け入れる制度は「雇用許可制」です。この制度での2021年の受け入れ数は約5万人でしたが、2023年に12万人、2024年には16万5000人に引き上げ、就労できる業種についても飲食や宿泊、養殖を新たに加えました。
2023年の韓国の人口は前年比0.2%増の5177万人で、3年ぶりに増加しましたが、そのうち外国人が前年比10.4%増の193万人となり、韓国人の減少を補っています。
また、韓国は林業分野でビザの要件を緩和し、2024年から森林の伐採・運搬などに従事する外国人材の受け入れも始めました。ほかに、「特定活動ビザ」の指針を2022年に改定し、造船に必要な溶接工や塗装工の人数制限も緩和しました。
台湾で働くための諸手続き
外国人材が台湾で働くには、採用が決まったら、受け入れ事業者が政府労働部か行政院労工委員会に「労働許可」の申請を行います。労働許可証が発行されたら、就労ビザの一種で3カ月以上の就労に必要な「居留ビザ」の発給を政府外交部(日本の外務省)申請し、最後に、内政移民局に「居留証」の発行を申請します。
台湾の労働許可証は通常10~12日の審査で取得でき、就労ビザも申請から1、2週間程度で発行されます。順調に進めば、採用面接合格から1、2カ月後に台湾で働き始めることができます。
シンガポールで働くための諸手続き

シンガポールは簡便な入管手続きと高賃金で外国人材を大量に獲得し、経済成長を成功させてきました。シンガポールでは全労働者の約3分の1が外国人材で、製造業では約5割、建設業では約7割、家事労働ではほぼ全員が外国人材です。そのシンガポールで単純労働に従事する外国人材の多くが「ワークパーミット(WP)」という就労ビザを取得します。
WPの申請は、政府が設けたインターネットの専用サイトから行います。受け入れ事業者がサイトに登録して申請しますが、必要なデータは本人のパスポート情報と最終学歴、雇用条件(給与、勤務時間、ポジションなど)ぐらいで、申請から1週間程度でIPAレターという仮承認の書類が発行されます。
レターが発行されると、WPの正式な申請手続きに進みます。まず、受け入れ事業者がセキュリティーボンドを金融機関で購入します。これは、外国人材が法律や労働許可条件に違反した場合に政府に支払われる金額で、いわゆる保証金のような位置付けです。さらに、事業者は事業者負担で外国人材を医療保険に加入させます。
その後、外国人材がシンガポールに入国して健康診断を受け、オンラインで住所を登録後、受け入れ事業者が再び専用サイトから正式な就労ビザ(WP)の発行を申請すると、まず仮の就労ビザが発行されます。その後、本人が政府機関を訪問して写真撮影と指紋採取を済ませると、5~7営業日後に正式な就労ビザカードが受け入れ事業者に届きます。
写真撮影と指紋採取以外はすべてオンラインででき、提出書類も比較的少なく、審査期間も短いのがWPの特徴です。
外国人材が日本で働き始めるための手続きと期間

特定技能の入管手続き
日本の入管制度の特徴は出入国在留管理局(入管)への提出書類が非常に多いことと審査期間が長いことです。
特定技能で海外から新規で特定技能外国人を受け入れる場合、採用が決まったら、まず入管に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。技能実習などすでに別の在留資格で日本に在留している外国人については、「在留資格変更許可」の申請を行います。
海外から新規で受け入れる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 書類の準備:1、2週間(※提出書類が多い)
- 入管での審査:1~3カ月間
国内人材の在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)
- 書類の準備:1、2週間
- 入管での審査:1、2カ月間
海外から新規に受け入れる場合、提出書類の準備と入管での審査期間を合わせて合計3~4カ月かかることが多いです。その後、現地の日本大使館や総領事館にビザの申請をします。ビザの審査には2~4週間かかります。審査期間は入管や大使館のそのときの業務量などによって左右されます。また、平均的な審査期間の長い入管もあれば短い入管もあります。
在留資格認定証明書(COE)の申請に必要な書類
〈外国人本人に関する書類の例〉
在留資格認定証明書交付申請書▽健康診断個人票(外国で受診した場合は日本語訳も必要)▽3カ月以内に撮影した写真▽技能試験及び日本語試験の合格証明書(または合格を証明する資料、技能実習2号を良好に修了した場合は不要)▽特定技能雇用契約書の写し(申請者が理解できる言語で記載)▽雇用条件書の写し(申請人が理解できる言語で記載)▽履歴書
〈受け入れ事業者に関する書類の例〉
特定技能所属機関概要書▽登録事項証明書▽業務執行に関与する役員の住民票の写し▽特定技能所属機関の役員に関する誓約書▽労働保険料等納付証明書(未納なしの証明)▽社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
技能実習開始前の諸手続き
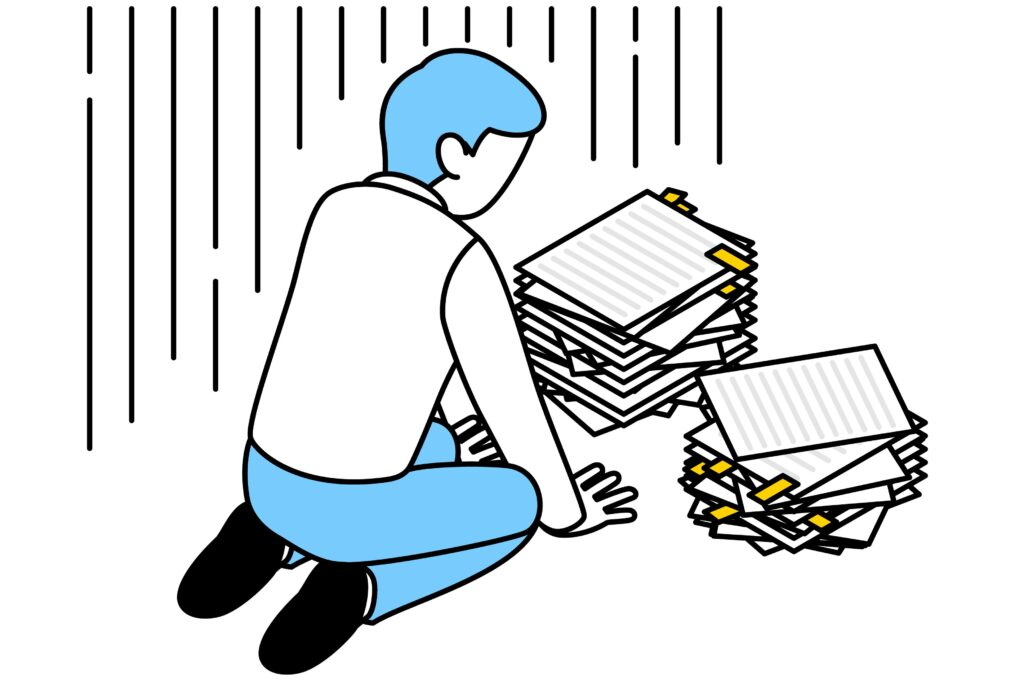
技能実習の面接で合格した場合、次のような手続きを経て入国・就労します。全体で半年以上かかります。
① 雇用契約を締結
② 監理団体が個々の内定者について技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に計画の認定を申請。
③ 技能実習計画が認定されたら、入管に在留資格認定証明書(COE)の交付を申請。
④ COE交付後、現地の日本大使館や総領事館にビザの発給を申請。
⑤ ビザが発給されたら訪日し、約1カ月間の入国後講習を受講。
⑥ 受け入れ事業者に配属。
〈技能実習の面接後の流れと期間〉
- 技能実習計画の書類準備:1~3週間(※提出書類が多い)
- 技能実習計画の審査(OTIT):1、2カ月間
- COEの審査(入管):約2週間
- ビザの審査(大使館等):1、2週間
- 入国後講習:約1カ月間
技能実習では面接から入国まで平均で約半年間かかり、その後、法律で決められた入国後講習(日本語や日本の生活習慣、ルール、マナーなど)を約1カ月間受けてから技能実習を開始します。2027年に導入される育成就労でも大きな流れは変わりません。
技能実習では、技能実習計画の認定申請でOTITに提出する書類が膨大で、書類作成に多大な時間・労力を要することも特徴です。
外国人材獲得の障壁になっている日本の受け入れ手続き

外国人材の負担
外国人材の海外就労先として、日本は給与水準がさほど高くないばかりでなく、入国・就労までのプロセスが大変です。海外から新規で日本に就労する場合、一般に、特定技能では採用面接から約4カ月、技能実習では約半年かかります。その間、外国人材は日本語や日本文化を学習しますが、正職につけないうえ、送出機関などに手数料や教育費を払わなければなりませんし、生活費も必要です。
受け入れ事業者の負担
受け入れ事業者側にとっても、OTITや入管に提出する膨大な書類の準備・作成が大きな負担です。手続きを代行する監理団体や登録支援機関に対する支払いが発生しますし、事業者自身が用意する書類も多数に上ります。
人材獲得のライバル諸国の制度・手続きにも関心を
入国までのプロセスが多いことが一概に悪いわけではありません。まじめな外国人材は日本入国・就労までの数カ月間に日本語や日本文化に関する知識をある程度習得し、訪日後の仕事や生活で役立ちます。
一方、入国までの期間が短い台湾についてベトナムのある送出機関関係者は「台湾で就労する場合、中国語をほとんど学習せずに渡航するケースが多い。手軽に行ける分、台湾に行くベトナム人材の中には素行不良の人物も多く、後輩ベトナム人たちが台湾での就労を検討する際の懸念材料になっている」と話しています。
ただし、入管手続きが簡単なこと自体は「選ばれる」ための大きな要素になっています。日本の人材不足や世界的な人材獲得競争が今後さらに激しくなっていくことが分かっている以上、人材受け入れに関するライバル諸国の制度に無関心ではいられません。
特定技能や技能実習の提出書類の多さや審査期間の長さについては、受け入れ事業者も外国人材も非常に不便を感じています。ライバル諸国の受け入れ制度にも学びながら、日本の制度や手続きも絶え間なく見直すことが求められます。
まとめ
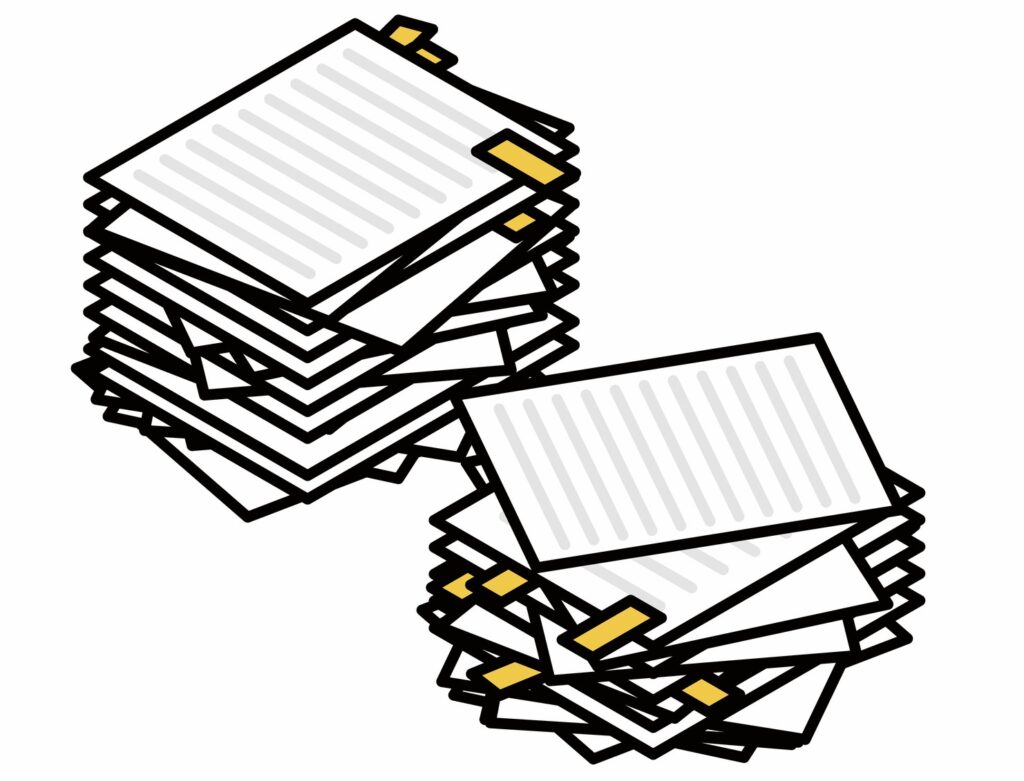
このページのまとめ
◎特定技能外国人を海外から新規に受け入れる場合、面接で採用を決めてから入国まで4カ月前後かかることが多いです。
◎技能実習の場合は入国まで平均で約半年かかり、入国後、法律で決められた入国後講習を約1カ月間受けてから技能実習を開始します。
◎特定技能も技能実習も入国までの期間が長いことや提出書類が多すぎることが問題です。
◎移住労働者の受け入れ国として日本と競合関係にある台湾の場合、審査期間が短く、面接合格から1、2カ月で働き始めることができます。
◎シンガポールの就労ビザ「ワークパーミット(WP)」も短い期間と比較的少ない提出書類で取得できます。
◎外国人材にとって、日本は給与があまり高くないうえ、採用面接合格から入国までの期間が長すぎます。その間、正職のない状態が続くため、日本の人気を下げる要因の一つになっています。
