
企業が技能実習や特定技能の外国人を受け入れる場合、日本の監理団体に送出機関選びを任せることが多いですが、どの送出機関を選ぶかによって、良い人材を面接できる確率が大きく変わってきます。送出機関を選ぶ際の大事なポイントとして人材の募集力や教育力があります。この記事では送出機関の人材募集力と、良い送出機関の探し方について紹介します。
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
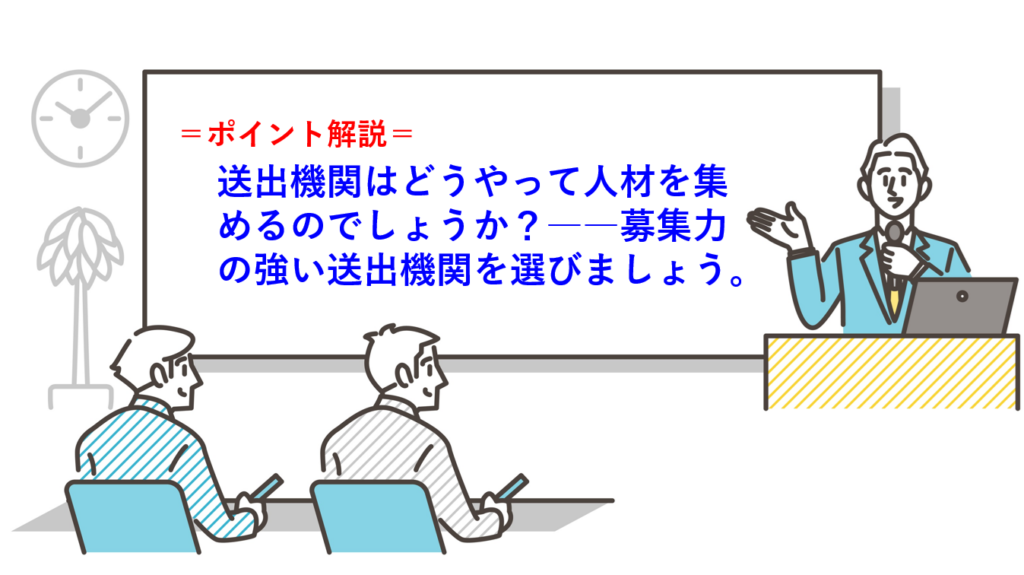
◎技能実習生を募集する際、送出機関選びを監理団体任せにせず、受入事業者が送出機関を指定することもできます。送出機関を選ぶ基準としては、人材募集力、教育力、生徒(人材)から集める費用などがあり、人材募集力がまずは必須です。
◎送出機関が技能実習候補者を集めるルートには、①個人事業者 ②日本語学校・教室 ③学校・大学等 ④地方説明会 ⑤在校生やOB・OG ⑥インターネット――などがあります。このうち①②をブローカーと呼ぶ場合もあります。
◎このような人材募集方法は特定技能外国人の候補者を集める場合も同じです。同じ人材会社が一括で候補者を集め、一部は特定技能外国人、一部は技能実習生として送り出しています。
◎ブローカーは技能実習制度に特有のものと誤解されがちですが、人材会社は特定技能外国人や一般の就労ビザで働く外国人の募集にもブローカーを使います。
◎さまざまな人材ルートを駆使して良い生徒(人材)をたくさん集めることのできる人材会社(送出機関を含む)は最初に生徒をある程度選び、企業面接を受けさせるまでにもハードルを設けます。このような人材会社に依頼する方が良い生徒を面接できる確率が上がります。
◎面接には偽の応募者(さくら)が入ることも多いので、面接に集まった人数だけで人材会社の募集力を判断することはできません。
◎「大きい送出機関は確かな人材を紹介してくれる」と考えがちですが、そうとは限りません。逆に規模は小さくても頼りがいのある送出機関もあります。
◎良い送出機関を探すには、複数の送出機関と直接話をするか、良さそうな監理団体に相談するといった方法があります。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 送出機関を指定するとは?
- 送出機関はどうやって人材を集めるのか
- 特定技能も技能実習と同じ方法で人を集める
- 送出機関の募集力と人材の質
- 面接に集まった人数だけでは募集力を判断できない
- 送出機関の大きさと人材の質は無関係
- 良い送出機関を探すにはどうしたらよいか
- まとめ
送出機関を指定するとは?

技能実習生を採用する際、一般には日本の監理団体(「組合」と呼ぶこともあります)に依頼します。その後、監理団体が外国の送出機関(=民間の人材会社)に求人を紹介すると、送出機関が人材を集め、日本語などを教育してから日本に送り出します。場合によっては、送出機関がもともとプールして教育を始めている人材の中から応募者を集めます。
人材募集の際、送出機関選びを監理団体任せにせず、受入事業者が送出機関を指定することもできます。これは、監理団体に依頼して、監理団体とその送出機関との間で契約を結んでもらうことで可能になります。
送出機関を選ぶ基準としては、人材募集力と教育力、生徒(人材)から集める費用、経営理念などがありますが、意欲のある人材をたくさん集める能力(人材募集力)がまずは必須です。それでは、送出機関はどのようにして人材を集めるのか、この記事で説明します。
送出機関はどうやって人材を集めるのか

「送出機関」と聞くと、いかめしい名前ですが、公的機関ではなく送出国の人材紹介会社です。海外に人材を送出できる人材紹介会社のうち技能実習生も紹介できる会社を「送出機関」と呼んでいます。
求人をもらった送出機関はその求人に対する応募者を探します。募集ルートには主に次のようなものがあり、どの送出機関も複数のルートを組み合わせて候補者を集めています。
① 個人事業者
送出機関は行政や教育の関係者、町の有力者、フリーランスの個人などに依頼して人材を集めます。このように謝礼と引き換えに人材を探して送出機関に紹介してくれる人のことを「ブローカー」と呼ぶ場合があります。元技能実習生にも送出機関に人材を紹介し、謝礼をもらっている人が多く、これもブローカーに含まれます。
② 日本語学校・教室
送出機関が自社経営の日本語学校や日本語教室(日本語センター)の生徒に求人への応募を呼びかけることもありますし、提携する他社の日本語学校・教室に応募者紹介をお願いすることもあります。そのような日本語学校・教室の経営者も「ブローカー」です。しかも、ブローカーの中でも中心的な存在です。
③ 学校・大学等
送出機関が高校や専門学校、短大、大学に人材の紹介をお願いすることもあります。学校・大学等が集めた応募者(学生)に企業面接や採用試験を受けてもらい、合格(採用内定)したら人材会社の日本語教室に入学し、教育してから日本に送り出します。
短大・大学から紹介を受ける人材の場合、技術・人文知識・国際業務(技人国)や特定技能の在留資格(通称・ビザ)で就労させることの方が多いです。
学校や大学で技能実習や特定技能に関する説明会を開いて希望者を入学させ、後から求人を紹介することもあります。
④ 地方説明会

地方行政が技能実習や特定技能に関する説明会を開き、人材会社(送出機関等)が説明を担当することがあります。参加者した若者たちが行政機関に登録し、人材会社が行政機関から応募者を紹介してもらうといったパターンがあります。
⑤ 在校生やOB・OG
日本に行くために送出機関で勉強している人や、そこから日本に行った人が、親せき・知人・友人にその送出機関を紹介する場合があります。在校生・卒業生やその家族からの紹介が多い送出機関は良い送出機関である確率が高く、良い人材も集まりやすいと言えます。
⑥ インターネット
最近は、インターネットで生徒(人材)を集めることに力を入れている送出機関もあります。ホームページやネット広告、SNSなどで募集します。サイト運営や広告の費用がかかりますが、ブローカーへの支払いを大幅に減らすことで、生徒の費用負担を減らし教育にも力を入れています。ただし、ネットによる生徒募集の効果を保つことは簡単ではありません。
特定技能も技能実習と同じ方法で人を集める

送出機関が技能実習候補者を集めるルートとして、①個人事業者 ②日本語学校・教室 ③学校・大学等 ④地方説明会 ⑤在校生やOB・OG ⑥インターネット――を紹介しました。どの送出機関も複数の手法を組み合わせて人材を募集しています。
このような人材募集方法は特定技能外国人の候補者を集める場合も同じです。同じ人材会社が一括で候補者を集め、一部は特定技能外国人、一部は技能実習生として送り出しています。同じ生徒が特定技能の面接に落ちたら、次は技能実習の面接に挑戦するといったケースもよくあります。
人材会社の中で技能実習制度に関与する許可を持っている会社を「送出機関」と呼びますが、送出機関は技能実習生だけを紹介するわけではありません。そこで、エンジニアなど一般の就労ビザ(技人国)で働く外国人を集める場合も、似たような集め方をします。ただし、紹介依頼先の重点が特定技能外国人や技能実習生の場合とは異なります。
また、ブローカーは技能実習制度に特有のものと誤解されがちですが、人材会社は特定技能外国人や一般の就労ビザで働く外国人の募集にもブローカーを使う場合があります。ブローカーの介在は技能実習制度に限ったことではありません。
送出機関の募集力と人材の質

送出機関には前述のようなさまざまな人材募集ルートがあり、どの機関も複数の手法を組み合わせて生徒(人材)を募集しています。ただし、送出国によって主力の募集ルートが異なります。
また、同じ国の中でも、送出機関ごとに、学校・大学等との提携力や地方行政とのパイプ、使っているブローカーの質の違いなどがあるため、集まってくる人材の質や人数にも大きな違いが生じます。
良い生徒(人材)をたくさん集めることのできる人材会社(送出機関を含む)は、最初に簡単な学力試験などを受けさせて生徒をある程度選びます。さらに、生徒を受け入れた後も、学習の進捗があまりに遅いとか欠席・遅刻が多い、規則を守らないといった問題がある場合は、企業面接を受けさせない場合があります。
外国人材を募集する場合、このようにある程度ふるいにかけられ生徒たちを面接するのと、そうではない生徒たちを面接するのとでは、人材選びのスタートが大きく違ってきます。
面接に集まった人数だけでは募集力を判断できない

ところで、不人気な求人に対して多数の応募者を集めることは困難です。求人の内容(給与、業種、地域など)によっては、候補者集めが困難を極め、受け入れ事業者からの応募倍率リクエストに表面的に応えるため面接に偽の候補者(さくら)を入れることがあります。また、応募者を選別せずに人数だけをそろえる場合もあります。ですから、面接に集まった候補者の数だけでその送出機関の人材募集力を判断することはできません。
逆に、求人を出したときに、「この求人内容では応募者が十分に集まらない。条件を改善した方がよい」などとアドバイスしてくれる送出機関の方が、紹介する人材に責任を持っている可能性が高いと考えられます。
送出機関の大きさと人材の質は無関係

「毎年多数の外国人材を送り出している人材会社(送出機関を含む)は人材募集力も強いはず」。そのように考える人も多いと思います。
しかし、大きな送出機関だから良い人材を紹介してくれる確率が高いとは言えません。大きな送出機関の場合、日本の大きな会社と大口取引をしていることも多いので、むしろ、「大きな送出機関が中小企業や零細企業の求人に対して良い人材を優先的に回してくれることはあまり期待できない」と考える人もいます。
また、ベトナムの超大手送出機関の元社員2人によると、同社は求人内容を偽って応募者を募集▽監理団体に接待やキックバックをふんだんに提供して求人を獲得▽生徒(人材)からさまざまな名目で高額の手数料を徴収――といった経営内容で、「働いていて良心が痛んだ」とのことです。このような会社からの人材は借金が多い、日本語力も低いといったケースが多く、むしろ受け入れを避けたい人材となってしまいます。
つまり、人材会社の大きさと送り出す人材の質は無関係です。規模が小さくても良い人材を十分に募集・教育できる良心的な送出機関なら、規模が大きくても人材の選別や教育が行き届かない送出機関より頼りになります。
良い送出機関を探すにはどうしたらよいか

人材募集力がある送出機関を選ぶ方が、良い人材を面接できる確率が高くなります。また、人材を送り出すまでの教育力も非常に大切です。
それでは、そのような送出機関を探すにはどうしたらよいのでしょうか?
一番良いのは、ネットや口コミで送出機関に関する情報を集めた上で、良さそうな送出機関を実際に訪問し、授業を見学したり、経営者と(日本語で)話をしたりすることです。実際に訪問できなくてもオンライン面談でもある程度のことが分かります。
しかし、個々の企業がそこまですることは、現実的には難しいかも知れませんね。
そこで、日本の良い監理団体等を探すという方法もあります。技能実習生を受け入れるには、外国の送出機関と日本の監理団体に仲介してもらわなければなりませんが、意識の高い監理団体は良い送出機関を選ぶ努力をしています。良さそうな監理団体の話を聞き比べてみると良いでしょう。
まとめ

このページのまとめ
この記事では、送出機関を含む外国の人材紹介会社がどうやって人材を集めているかを紹介しました。募集力や教育力の強い送出機関を選ぶことで、良い人材を面接できる確率が高まります。
そのような送出機関を選ぶには、周囲から情報を集め、良さそうな送出機関と面談してみることが一番です。それが難しい場合は、良さそうな日本の監理団体を探し、監理団体が紹介する送出機関の長所・短所について説明をしてもらいましょう。十分に説明ができない監理団体は、送出機関選びのノウハウがまだ十分ではないと考えても差し支えありません。
良い監理団体や送出機関を探して取引をし、良い人材を紹介してもらいましょう。
