
技能実習に代わる新制度「育成就労」の最大の目玉は転籍要件の緩和です。技能実習では原則3年間は職場変更(転籍)ができないため、使用者と技能実習生との間に過度の支配従属関係が生まれ、暴力・暴言などの人権侵害や労働法令違反を助長する背景になっていると指摘されています。技能実習制度でも「やむを得ない事情がある場合」は転籍できるのですが、その運用を改善するとともに、新制度では、特別な事情がなくても本人の希望だけで転籍ができることになります。では、本人の意向による転籍は育成開始後のいつから、どのような条件でできるのでしょうか?また、転籍外国人を受け入れることのできる事業者の条件とはどういうものでしょうか?
1分で読める記事の要点〈時間のない方はこちらだけ!〉
ポイント解説
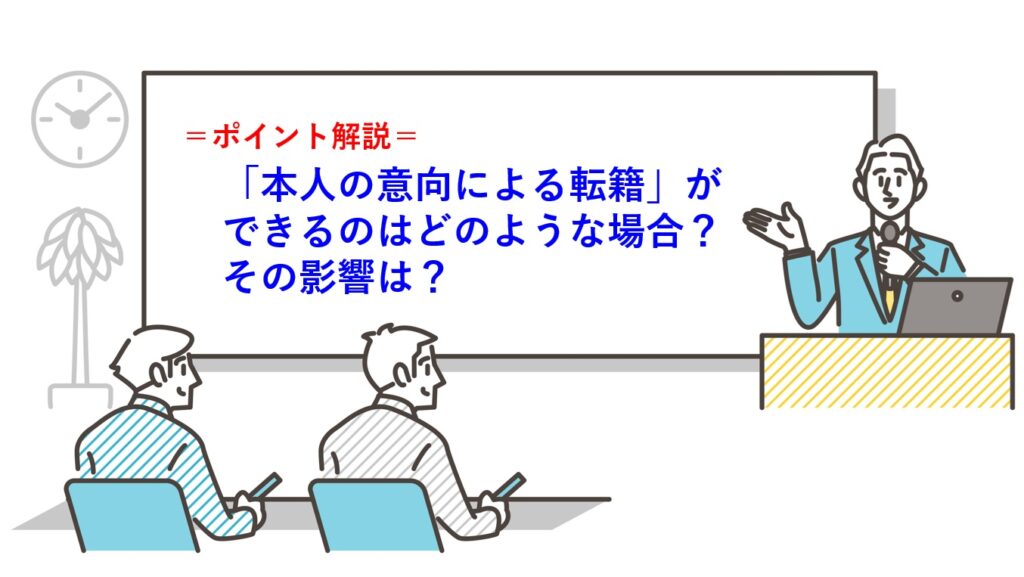
新制度:「本人の意向による転籍」の導入
◎技能実習制度では、自己都合で職場を変わる「転籍」が原則3年間認められていませんが、育成就労制度では、労働者の権利として「本人の意向による転籍」が認められることになります。
◎本人意向転籍は育成開始から1~2年経過後に認められます。その時期は受け入れ対象分野ごとに省令で決められます。
◎本人意向転籍が可能になる時期を育成開始から1年を超えて設定する場合、1年を超えた時点での昇給など待遇向上が条件となります。
新制度:1、2年で特定技能への変更も可能に
◎新制度では、本人意向転籍が可能な時期になれば、必要な試験(各分野の技能試験と日本語試験)への合格を条件に特定技能1号に在留資格を変更できることになります。
新制度:本人意向転籍の日本語要件
◎本人意向転籍には、 技能検定試験基礎級への合格などに加え日本語能力も必要になります。具体的には、分野ごとに日本語能力試験N5相当~N4相当の範囲内で設定されます。
新制度:転籍外国人の受け入れ要件
◎転籍外国人を受け入れる企業には、在籍外国人のうち転籍してきた人の割合が一定以下であることや、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるなど、転籍先として適切であると認められることが必要です。
新制度:初期費用等の分担
◎本人の意向による転籍者を受け入れる場合、新しい受け入れ事業者は、元の受け入れ事業者が負担した初期費用や育成コストの一部を元の企業に補填しなければなりません。
新制度:転籍ブローカーの排除
◎手数料ほしさにやみくもに転籍を促すブローカーが存在すると、外国人の適正なキャリア構築を阻害したり、最初の受け入れ企業での定着を不当に妨げたりするため、転籍には当面は民間業者の関与を認めず、監理支援機関が中心となって転籍を支援します。
本人の意向による転籍導入の影響
◎新制度では、育成就労よりも特定技能1号を重視する企業が増える可能性があります。
◎ただし、育成就労は原則3年間で、転籍する場合も日本語能力などの条件があることから、地方等での定着率は特定技能より高くなる可能性があります。地方の事業者でも、待遇に配慮するなど定着への努力を十分に行えば、育成就労外国人が3年間働いてくれる可能性は十分にありそうです。
◆このページの内容
- ポイント解説〈時間のない方はこちらだけ!〉
- 「転籍禁止」の改善
- 新制度:「本人の意向による転籍」の導入
- 新制度:1、2年で特定技能への変更も可能に
- 新制度:本人意向転籍の日本語要件とは?
- 新制度:転籍の育成就労外国人を受け入れる際の事業者側の要件
- 新制度:初期費用等の分担
- 新制度:転籍ブローカーの排除
- 本人意向転籍の導入による影響
- まとめ
「転籍禁止」の改善

技能実習制度の目的は「技術・技能・知識の移転を通じた国際貢献」です。外国人に日本の職場で技能を身に付けてもらい、その技能を母国に持ち帰って役立ててもらうことで、各国の経済発展に貢献するという狙いです。この目的を達成するためには、技能を計画的・継続的に学ぶ必要があるという理由で、技能実習制度では、職場を変える「転籍」を原則3年間認めていません。
しかし、転籍ができないことによって使用者と技能実習生との間に過度の支配従属関係が生まれ、暴力・暴言やいじめなどの人権侵害や残業代不払いなどの労働法令違反を助長する背景・原因になっていると指摘されています。
その結果、実習生の失踪が多発するなどし、外国から「日本の技能実習は奴隷制度」と酷評されるようになりました。そこで、有識者会議の最終報告(2023年)を受けた閣議(2024年)は新制度「育成就労」で働く外国人の転籍要件を緩和することを決定し、2024年、関連法案が成立しました。新制度では、技能実習制度にも存在する「やむを得ない事情がある場合」の転籍の運用を改善するとともに、「本人の意向による転籍」が導入されることになりました。
それでは、「本人の意向による転籍」の要件や影響についてくわしく説明します。
新制度:「本人の意向による転籍」の導入

2024年2月の閣議決定では、「3年間を通じて一つの受け入れ機関での就労が効果的であり望ましい」としつつも、「一つの職場で就労した期間が一定期間を超えている場合」に、外国人本人の意向による転籍を認めることにしました。ただし、人手不足分野における人材確保と人材育成という制度目的に照らし、転籍先は現に就労している業務区分と同一の業務区分内に限られることになりました。
ここで言う「一定期間」とは、当分の間、各受け入れ対象分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに育成開始から1~2年の範囲内で設定されます。1年を超える期間を設定する場合、2年目は昇給などの待遇向上が条件となります。
① 労働者の権利として本人の意向による転籍を認める
育成就労制度には人材育成に加えて人材確保という目的もあるため、労働者としての権利を保障しなければなりません。そこで、「やむを得ない事情がある場合」の転籍の運用改善に加え、外国人労働者本人の意向による転籍も認められることになりました。
2023年11月の有識者会議最終報告は「人材育成の実効性を確保するための一定の転籍制限は残しつつも、 人材確保も目的とする新たな制度の趣旨を踏まえ、外国人の労働者としての権利性をより高める観点から、一定の要件の下での本人の意向による転籍も認める」としています。
② 昇給など条件に2年まで転籍制限可
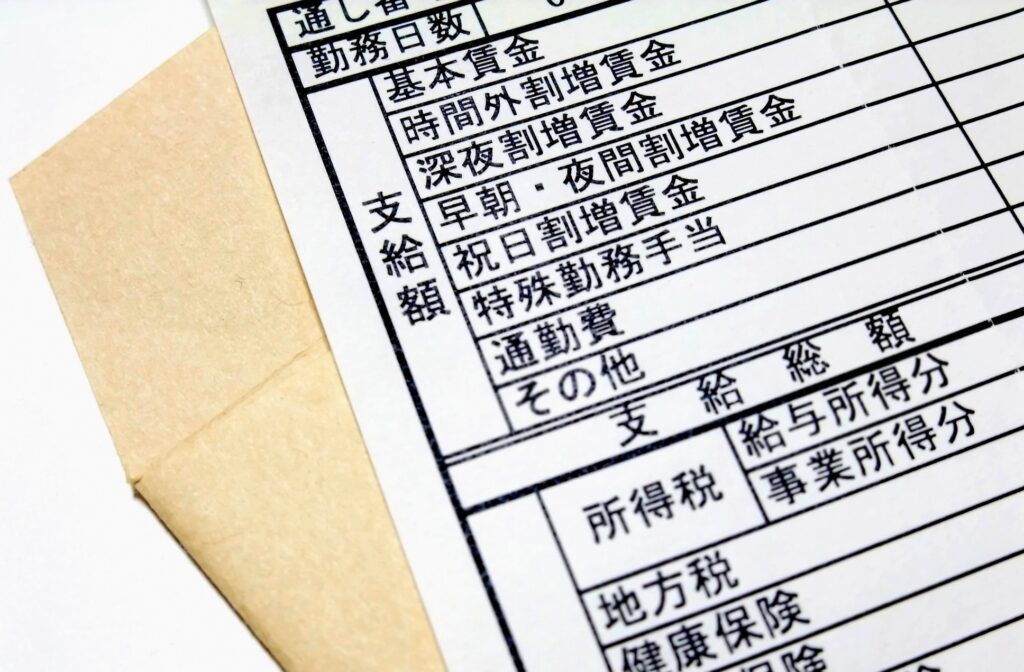
本人の意向による転籍を導入するにあたり最大の焦点になったのは、それを外国人の育成開始後いつから可能にするかでした。民法や労働基準法では、有期雇用契約の場合は1年を超えれば退職が可能であることなどから、最終報告では、育成開始から1年で自己都合転籍を可能にすることが提案されました。
ただし、「当分の間、受け入れ対象分野によっては1年を超える期間を設定することを認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討」とも言及されました。これは、短期間での転籍によって地方等での人材確保に深刻な支障が出るという懸念の声が多かったためです。
そして、2024年2月の閣議は「当分の間、各受け入れ対象分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに(育成開始から)1~2年の範囲内で設定する。人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討する」と決めました。
つまり、受け入れ分野によっては、育成開始から1年経過後に昇給など待遇改善を行うことを条件に、最長2年まで転籍を制限できることにしたのです。
なお、人手不足分野における人材確保と人材育成という制度目的に照らし、転籍先は現に就労している業務区分と同一の業務区分内に限るとされました。異なる業務区分への転籍を認めると、賃金水準が高い産業に人材が流出する懸念があることも背景にあります。
新制度:1、2年で特定技能への変更も可能に

新制度では、本人の意向による転籍が可能な時期になれば、必要な試験(各分野の技能試験と日本語試験)への合格を条件に特定技能1号に在留資格(通称・ビザ)を変更できることになります。
技能実習制度では2号技能実習を終えた実習生(来日から3年)や3号を終えた実習生(同5年)が、日本語試験を免除されて特定技能1号に移行(同じ業務区分内で移行する場合は技能試験も免除)するケースが主流でした。しかし、育成就労制度では、育成開始から1~2年で試験合格を経て特定技能に移行する事例が生まれそうです。
本人の意向による転籍については、育成開始から2年を経て転籍する場合、残り1年弱しか育成就労期間が残っていない人材を雇用する企業は見つかりにくいという指摘もありました。しかし、試験に合格して特定技能外国人として転職できるのであれば、新たな受け入れ先の確保は容易になります。
ただし、その場合は日本語試験(日本語能力試験N4など)への合格が必要となるため、だれもが簡単に特定技能に変更できるわけではありません。また、企業としては、本人が満足する待遇を提供することで、特定技能の資格を取得した上で残留してもらうことも可能です。
新制度:本人意向転籍の日本語要件とは?

本人の意向による転籍には、 技能検定試験基礎級等への合格以外に、日本語能力の要件も加わりました。具体的には、各分野で「日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内」で設定されます。
「日本語能力A1相当の水準」とは、日本語能力試験(JLPT)で言えばN5(5段階の中の最も初級のランク)以上に合格していることです。また、「特定技能1号移行時に必要な日本語能力の水準」とは、JLPTではN4以上です。つまり、本人意向転籍に必要な日本語能力の要件はN4相当~N5相当の間で分野ごとに設定されることになります。
本人の意向による転籍の日本語要件がもしN4相当に設定されると、育成開始から1、2年でJLPT・N4等に合格しなければなりません。しかし、現在の技能実習生の中でN4相当に合格している人はそれほど多くはなく、日本語要件は転籍をある程度抑制するハードルになると思われます。
※本人意向転籍に必要な日本語要件については、1年を超える場合の転籍制限の期間とともに、各分野を所管する省庁の省令等で規定されます。
新制度:転籍の育成就労外国人を受け入れる際の事業者側の要件

本人の意向による転籍者を受け入れることのできる事業者には一定の要件が設けられることになりました。
① 転籍者の割合など
労働者は便利な地域や待遇の良い企業に魅力を感じ、受け入れ事業者は、時間と費用がかかる海外からの受け入れより初期費用や育成の苦労が少ない転籍者受け入れに大きなメリットを感じます。したがって、転籍を希望する外国人は潜在的に多く、受け入れ需要もあります。しかし、もっぱら転籍者だけを受け入れる手法が受容されるのであれば、海外から受け入れて最初に育てる企業が報われません。
このため、新制度では、転籍外国人を受け入れる事業者には、例えば在籍外国人のうち転籍してきた人の割合が一定以下であることや、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていることなど、転籍先として適切であると認められる要件が求められることになりました。
② 受け入れ後の育成
また、転籍者を受け入れた事業者も育成就労計画に基づいて適正な人材育成を行うよう、外国人育成就労機構(今の外国人技能実習機構)と監理支援機関(今の監理団体)が監督します。
2024年の閣議決定はさらに「転籍等に係る制度の悪用を防止し、適切な人材育成を促すため、受け入れた外国人の技能検定試験、日本語能力を測る試験等の合格率等を受け入れ機関及び監理支援機関の許可等の要件や優良認定の指標とする」と定め、転籍者受け入れ後の育成状況を許可更新や優良認定の際に勘案する方針も打ち出しました。
新制度では、このように、外国人の初期の育成をもっぱら他社に任せ、ある程度戦力になった段階で人材を引き抜くといったもくろみを抑制するための措置が講じられています。
新制度:初期費用等の分担

育成就労では、本人の意向で転籍する場合、転籍前の受け入れ事業者が負担した初期費用等の一部を転籍後の受け入れ事業者に分担させることになりました。
外国人労働者を海外から最初に受け入れる企業が負担する初期費用は多額です。また、来日当初の外国人に仕事の手順や日本の企業文化などを覚えてもらうには大変な労力・時間がかかります。
そのような外国人労働者が1、2年で他社に転籍してしまった場合、初期費用や当初の育成コストを元の会社だけが負担するのは不公平です。このため、元の受け入れ事業者が負担した初期費用や育成コストの一部を新たな受け入れ事業者からある程度補填してもらう仕組みが導入されます。ただし、負担割合を具体的にどのように算定するかはまだ決まっていません。元の受け入れ事業者が新しい受け入れ事業者から確実に費用を受け取れるような仕組み作りが求められます。
新制度:転籍ブローカーの排除

〇 転籍については、受け入れ機関、送出機関および外国人の間の調整が必要となることに鑑み、転籍支援は、まずは監理支援機関(今の監理団体)が中心となって行うこととしつつ、ハローワークは外国人育成就労機構(今の外国人技能実習機構)等と連携するなどして支援を行うこととする。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。
〇 転籍ブローカー等の排除を担保するため、転籍の仲介状況等に係る情報を把握できる仕組みを設けるとともに、不法就労助長罪の法定刑を引き上げつつ適切な取締りを行う。
〈2024年2月の閣議決定より〉
育成就労外国人を海外から最初に受け入れ育てる事業者にとっては、労力と時間をかけてやっと一人前に育てた外国人材にできれば3年間働いてもらいたいと思うのが普通です。逆に、ある程度育成された外国人を転籍によって受け入れることができれば、これは楽です。
外国人本人の強い希望による転籍なら、それでも仕方がないとしても、手数料ほしさに転籍をそそのかす業者(ブローカー)が暗躍し、就労1~2年での転籍が過度に多くなると、育成就労外国人を最初に受け入れ大切に育成する企業が大きな損失を被ります。
また、転籍先の職場をよく調べず、本人のキャリアにとって何がよいかも考えず、手数料ほしさにやみくもに転籍を促すブローカーが存在すると、外国人の適正なキャリア構築を阻害することにもなります。
そこで、当面は民間の職業紹介業者の関与を認めず、監理支援機関が中心となって転籍を支援し、ハローワークも外国人育成就労機構と連携して転籍支援を進めることになりました。具体的には、その監理支援機関や提携する他の監理支援機関が監理する事業者の中から新たな受け入れ先を探す手法が中心になると予想されます。しかし、監理支援機関だけで適切な転籍先を見つけられない場合、ハローワーク等がいかに役割を発揮できるかが今後の注目点です。
また、転籍ブローカーの排除を後押しする目的もあり、2024年の入管法改正で不法就労助長罪の法定刑が「3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方」から「5年以下の懲役、500万円以下の罰金、またはその両方」に引き上げられました。育成就労制度のもとでは、不法就労助長などの取り締まりも強化される方向です。
本人意向転籍の導入による影響

① 全体的な影響
育成就労では1、2年で転籍するリスクがあるため、「育成就労と特定技能1号との大きな違いは就労開始時の日本語能力ぐらい」ととらえる事業者もいます。また、現在の技能実習制度の事務量は特定技能より大きくなっています。このため、新制度では特定技能1号を中心にすえる企業が増える可能性があります。
ただし、育成就労は原則3年間となっており、転籍する場合も日本語能力などの条件があることから、地方等での定着率は特定技能より高くなることが想定されます。このため、育成就労を重視する受け入れ事業者もある程度残ると予想されます。
② 地方事業者の苦境
本人の意向による転籍の導入によって、大都市圏や人気職種、好条件で雇える大手企業等では大きな影響はないと思われますが、それ以外の受け入れ事業者にとっては、育成就労外国人の定着が従来より困難になる可能性があります。
労働者は便利な地域や給料の高い企業に行きたがるので、地方の中小事業者の場合、育成就労外国人の定着に向けて今まで以上に待遇改善などの努力が求められます。
③ 「地方でも人材定着は可能」

一方、地方で技能実習生をたくさんサポートしてきた経験豊かな監理団体職員は次のように話しています。
「新制度になっても地方で外国人材に長く定着してもらうことは可能です。それには、手取り給料(額面給料から税金・社会保険料・寮費を引いた額)が地域や業種の相場以上に達していることが一番大切です。その上で、寮の質や立地、日ごろの気遣いなども生きてきます」
また、別の専門家は「大都会や周辺の企業では特定技能外国人が多数定着するので、育成就労外国人が大都市圏の企業に転籍しようと思っても、十分な受け入れ先があるとは限らない」と話しています。
地方の中小企業であっても、育成就労外国人の定着に向けて相応の努力をした場合、3年間継続勤務してもらえる可能性は十分にあると考えられます。
まとめ

このページのまとめ
- 技能実習制度では、「転籍」が原則3年間認められていませんが、育成就労制度では、本人の意向による転籍が育成開始から1、2年経過後に認められます。その時期は受け入れ対象分野ごとに決められます。
- 本人意向転籍が可能になる時期を育成開始から1年を超えて設定する場合、1年を超えた時点で待遇の改善が必要です。
- 本人の意向による転籍が可能な時期になれば、技能試験と日本語試験への合格を条件に特定技能1号に在留資格を変更することもできるようになります。
- 本人意向転籍には日本語能力も必要とされます。具体的には、分野ごとに日本語能力試験N5相当~N4相当の範囲内で設定されます。
- 転籍外国人を受け入れる企業には、在籍外国人のうち転籍してきた人の割合が一定以下であることなど、転籍先として適切であると認められることが必要です。
- 本人の意向による転籍者を受け入れる場合、新しい受け入れ事業者は、元の受け入れ事業者が負担した初期費用や育成コストの一部を補填しなければなりません。
- 転籍ブローカーを排除するため、転籍には、当面は民間の職業紹介業者の仲介を認めず、監理支援機関が中心となって転籍を支援します。
- 育成就労導入後は、特定技能1号を中心にすえる事業者が増える可能性があります。ただし、育成就労は原則3年間となっており、転籍の際に日本語能力の条件もあることから、地方等での定着率は特定技能より高くなる可能性もあります。地方でも、待遇などに配慮することで、育成就労外国人が3年間定着してくれる可能性はありそうです。
